かこがわの福祉制度
このページは、福祉に関する制度の事業内容や関連する部署、問い合わせ先などを一覧にまとめて掲載しています。事業内容などは簡潔に記載していますので、詳しくはリンク先のホームページをご確認いただくか、各問合せ先までお問合せください。
※内容については、令和7年4月1日現在における内容を掲載していますが、今後制度改正により変更になる場合がありますので、ご注意ください。
1 地域福祉
(1)地域福祉
|
施策・事業 |
内容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
「民生委員」は、社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っている。また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っている。 |
地域福祉課 |
|
|
障害がある住民も、住みなれた地域で暮らし続けていけるように支援する活動 |
社会福祉協議会 |
|
|
善意銀行 |
市民のみなさんからの善意(寄付)を預託としてお預かりし、市内の当事者団体や福祉施設、地域の福祉活動などに払い出す取組 |
|
|
共同募金としていただいた寄付を、こどもたち、高齢者、障がい者などを支援するさまざな福祉活動や災害時支援に役立てる活動 |
||
|
ボランティア活動が地域で広がるよう啓発し、活動しやすい環境をつくる事業 |
ボランティアセンター |
|
|
認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などの判断能力が不十分な方の支援制度 |
成年後見支援センター |
|
|
高齢者や障がい者など災害時に支援が必要な方について「避難行動要支援者名簿」を作成し、その情報を町内会などに提供することで、災害時の安否確認や避難誘導などに役立てる制度 |
防災対策課 地域福祉課 障がい者支援課 |
|
|
災害時に自ら避難することが難しい高齢者、障がい者等(災害時避難行動要支援者)が、災害時にどのような避難行動をとればよいのかについて、福祉専門職がフォローしながら、本人・家族・地域と確認し作成する、一人一人の状況に合わせた個別の避難行動計画を作成する事業 |
防災対策課 地域福祉課 障がい者支援課 介護保険課 |
(2)その他
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
戦没者遺族等に対する特別給付金、 特別弔慰金等申請 |
一定の基準日において、公務扶助料などの受給権を有する戦没者の妻、戦没者の遺族が支給の対象となる給付金 |
地域福祉課 |
|
災害見舞金支給事業 |
本市で発生した暴風・洪水等の自然災害、その他異常な自然現象又は火災による被災者に対して、見舞金等を支給する事業 |
|
|
本市は、日本赤十字社兵庫県支部加古川市地区となっており、以下の業務を行っています。 (1) 赤十字会員増強運動 (2) 義援金・海外救援金の受付 (3) 救急法等講習会の実施 |
2 高齢者
(1)高齢者を地域で支えるために
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
高齢者の総合相談 |
||
|
高齢者虐待に関すること |
||
|
社会的に孤立しがちな環境にあるひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、営業や宅配で直接対面する民間事業者と連携し、日常業務の範囲内で何らかの異変を察知した場合、市に情報提供を行う協定 |
高齢者支援課 |
|
|
認知症などの病気により、行方不明となる可能性のある方が、各地区の地域包括支援センターに登録することで、万が一行方不明となった時にネットワーク関係機関に情報提供し、早期発見・保護に努める制度 |
高齢者支援課 |
|
|
認知症について、正しい知識をもち、認知症の人や家族を温かく見守る応援者となる「認知症サポーター」を養成する制度 |
||
|
認知症の人やその家族、地域住民、専門職など誰もが気軽に集い、お互いの悩みを話したり、情報交換などをしながら、楽しく過ごす場 |
(2)生きがい対策
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、地域住民の敬老意識の高揚を図るため、地域団体が実施する敬老事業に補助する制度 |
高齢者支援課 |
|
|
高齢者相互の親睦を深め、社会奉仕活動、教養活動及び健康増進活動を推進する老人クラブを育成し、その運営を援助する制度 |
||
|
敬老記念品贈呈事業 |
満100歳を迎えられる方に記念品を贈呈する事業 |
|
|
おおむね65歳以上で構成された団体(心身障がい者団体など)が利用できるバスを運行する事業 |
(3)在宅福祉サービス
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
おおむね65歳以上でひとり暮らしの人、または要介護3以上の人がいる高齢者のみの世帯に、緊急時にボタンを押すだけで緊急通報できる相談機能のついた機器を貸出する事業 |
高齢者支援課 |
|
|
市内に住所を有し、要介護4または5の認定を受けた高齢者を同居して在宅介護をする介護者に介護用品を支給する事業 |
||
|
在宅で寝たきり等のため理美容院で散髪をすることが困難な65歳以上の高齢者又は障がい者に対して、自宅で理美容サービスを利用する場合の理美容師出張費を助成する事業 |
||
|
車いすの貸出 (1)高齢者の方に2週間以内(4週間まで延長可能) (2)2週間~3カ月以内 |
高齢者支援課 社会福祉協議会 |
|
|
認知症により行方不明のおそれがある高齢者等の安全を確保し、家族等の身体的・精神的負担の軽減を図るため、見守りサービス(見守りタグ)を利用しようとする場合の費用について市が負担 |
高齢者支援課 |
(4)その他の高齢者対策
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
おおむね65歳以上で環境上の理由及び経済上の理由により、居宅において生活することが困難な高齢者の養護老人ホームへの入所手続きを実施 |
高齢者支援課 |
|
|
成年後見制度の利用が必要だが、申立人や申立費用、報酬等の支払いが困難な場合に、申立てや費用等について支援を行います。 |
||
|
年金の制度的な理由により年金を受けることができない外国籍等の高齢者に対して、給付金を支給する事業 |
医療助成年金課 |
(5)介護保険制度
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
65歳以上の高齢者または40~64歳の特定疾病患者のうち介護が必要になった人を社会全体で支える制度 |
介護保険課 |
|
|
介護保険料の賦課に関すること (※納付に関することは債権管理課) |
介護保険課 |
|
|
介護保険サービスの利用(施設入所、居宅サービス等) |
利用者の意向や状況にあったサービスを利用するための高齢者の総合窓口 |
|
|
介護保険のサービスを利用するために、要介護(要支援)認定の申請により、介護や支援が必要な状態であるかどうかについての認定を受けます。 |
介護保険課 |
|
|
|
要介護(支援)認定者が入浴や排泄などに使用する特定福祉用具を購入する場合に購入費を給付する制度 要介護(支援)認定者およびその介護者の生活の質の向上を図るため、住宅の一部を改修する場合に対象工事に対して改修費を給付する制度 ※購入できる福祉用具・工事内容の条件、支給限度額あり |
介護保険課 |
|
既存住宅を要介護(支援)認定者および障がい者に対応した住宅に改造するためのバリアフリー化工事に対して、着工前の申請により費用の一部を助成する事業 |
||
|
同じ月に利用した介護サービスの1割~3割の自己負担の合計額が、その世帯の限度額を超えた場合に、「高額介護サービス費」として給付する制度 ※施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険対象外の費用、福祉用具購入および住宅改修費の利用者負担分、支給限度額を超える利用者負担は含まれません |
||
|
介護保険施設に入所した場合や短期入所を利用した場合で、一定の要件(所得および預貯金等)を満たす場合に、食費・居住費について負担を軽減する制度 |
3 障がい者
(1)手帳等の交付と相談
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・自立支援医療費(精神通院)受給者証 |
障がい者支援課 |
|
|
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、すべての障害に対応した総合的・専門的な相談業務を行う。 ◆相談支援の内容 |
加古川市障がい者基幹相談支援センター |
|
|
障がい者が日常生活の中で直面するあらゆる問題について、同様の立場にある相談員が相談に応じ、問題解決のための指導や助言を行う。 1.身体障がい者相談 2.知的障がい者相談 3.精神障がい者相談 |
障がい者支援課 |
(2)経済的支援
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
重度心身障がい者(児)の介護者に手当を支給することにより、障がい者(児)及び介護者の負担を軽減し、福祉の向上を図る制度 |
障がい者支援課 |
|
|
重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の障がい者本人に支給することにより福祉の向上を図る国の制度 |
||
|
重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい児本人に支給することにより福祉の向上を図る国の制度 |
||
|
身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合、ならびに第1種身体障害者及び第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合 |
||
|
身体障がい者が運転免許を取得する経費の一部を助成する制度 |
障がい者支援課 |
|
|
上肢、下肢又は体幹機能障がい者が、就労等のため、自ら使用し運転する車を改造する場合、その経費の一部を助成する制度 |
||
|
グループホーム利用者への家賃助成 |
グループホーム入居者に対し、家賃の一部を助成する制度 |
障がい者支援課 |
|
所得税 ・・・加古川税務署 (電話079-421-2951) 自動車税・自動車取得税 |
||
|
年金の制度的な理由により年金を受けることができない外国籍等の障がい者に対して、給付金を支給することにより福祉の向上を図る事業 |
医療助成年金課 |
|
|
1.JR、私鉄運賃の割引 2.バス運賃の割引 第1種、第2種心身障害者が単独で乗車するとき |
1.各駅窓口
2.各バス会社
|
|
|
航空運賃の割引制度 |
各航空会社 |
|
|
身体障害者手帳、療育手帳の所持者 |
各タクシー会社 |
|
|
視覚、肢体障害などの身体障がい者、知的障がい者、または精神障がい者が無料で番号案内を受けることができる制度 |
NTT営業窓口 |
|
|
【全額減免】 【半額減免】 |
NHK神戸放送局 |
|
(3)日常生活支援
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
駐車禁止区域の緩和を図る制度 |
加古川警察署 |
|
|
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人等で歩行が困難な方に対して交付し、県が登録した「兵庫ゆずりあい駐車場」の標示がある駐車区画に駐車することができる制度 |
障がい者支援課 兵庫県ユニバーサル推進課 加古川健康福祉事務所 |
|
|
聴覚障がい者が公的機関へ出かけるときや、 手話通訳を必要とする場合、 手話通訳者を派遣する制度 |
障がい者支援課 |
|
|
聴覚障がい者が公的機関へ出かけるときや、 要約筆記を必要とする場合、 要約筆記者を派遣する制度 |
||
|
身体障がい者 (児) 及び難病患者の身体の損傷や失った機能を補完するため、 義肢、 装具、 車いす、 補聴器等の補装具費の支給を行う制度 |
||
|
早期に補聴器の装用を行うことで言語の習得、教育等における健全な発達を支援するために、児童の補聴器購入費等の一部を助成する制度 |
||
|
身体・知的障がい者(児)及び難病患者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付する事業 |
||
|
小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付する事業 |
||
|
重度心身障がい者 (児) の生活行動範囲の拡大と積極的な社会参加のために、 利用されるタクシー料金の一部を助成する制度 |
||
|
障害者通所費用助成 |
作業所等に通所している人に対して、 交通費の一部を助成する制度 |
|
|
手話奉仕員養成事業 |
聴覚障がい者が日常生活及び社会生活でコミュニケーションを円滑に図ることができるよう、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した人を養成する事業 |
|
|
点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業 |
視覚障がい者が日常生活及び社会生活で円滑に情報を取得することができるよう、点訳・朗読技術を習得した人を養成する事業 |
|
|
地域活動支援センター補助事業 |
障がい者に創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進させる地域活動支援センターの運営を補助する事業 |
|
|
福祉ホーム補助事業 |
住居を求めている障がい者に対し低額な料金で居住させ、日常生活を支援する福祉ホームの運営を補助する事業 |
|
|
ふれあいスポーツ教室 |
障がい者(児)の健康と体力の維持増進及び残存機能の回復を図るため、適切なスポーツの紹介と指導、障がい者スポーツの普及を目指す教室 |
|
|
ふれあい作品展 |
障がい者(児)が日頃の趣味・学習活動の中から製作した作品を展示する事業 |
|
|
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する事業 |
障がい者支援課 |
|
|
家庭において入浴が困難な重度身体障がい者のいる世帯に対し、巡回入浴車を派遣する事業 |
||
|
居宅において、介護を行う方の疾病等の理由により、障がい者支援施設等での日中の預かりが必要な障がい者等について、当該施設で宿泊を伴わない範囲で一時預かりを行う事業 |
||
|
兵庫県心身障害者扶養共済制度 |
心身障がい者 (児) の将来に対する保護者の不安を解消するため、 保護者の相互扶助の精神に基づく共済制度によって、 保護者が死亡したり、 重度の障がい者になった場合、 一定額の年金を支給する制度 |
障がい者支援課 |
|
兵庫県在宅重度障害者生活環境改善資金の貸付 |
在宅重度心身障がい者 (児) の日常生活並びに介護を容易にするため、 家屋の玄関、 浴場、便所、 居所等の改善に要する資金を貸し付ける制度 |
財団法人 兵庫県身体障害者福祉協会 財団法人 兵庫県手をつなぐ育成会 |
|
障がいのある方や高齢の方など支援や配慮を必要とする方が身に着けることで、日常生活や緊急時等の困った時に、周囲の人へ必要な支援や配慮を伝えるためのカード |
【障がい者】 【高齢者】 |
|
|
内部障害や難病の方など外見から分かりにくくても援助や配慮を必要としている方々が周囲の方にそのことを伝えるためのマーク |
障がい者支援課 兵庫県ユニバーサル推進課 |
(4)医療
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
精神疾患を有し、通院による継続的な精神医療を受ける時にかかる費用の一部を公費で負担する制度 |
障がい者支援課 |
|
|
身体障がい者の障害を軽減して、 日常生活を容易にすることを目的とした医療にかかる費用の一部を公費で負担する制度 |
||
|
自立支援医療(更生医療)自己負担額の助成 |
自立支援医療(更生医療)の受給者に対して、自立支援医療(更生医療)に要した自己負担額の一部を助成する制度 |
|
|
身体上の障がいや疾患を有する満18歳未満の児童の障害や疾患を軽減して、 日常生活を容易にすることを目的とした医療にかかる費用の一部を公費で負担する制度 |
||
|
自立支援医療(育成医療)自己負担額の助成 |
自立支援医療(育成医療)の受給者に対して、自立支援医療(育成医療)に要した自己負担額の一部を助成する制度 |
(5)福祉サービス
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
障害者総合支援法制度 |
障がいのある人が日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに係る給付・地域生活支援やその他の支援を総合的に行う事業 【介護の給付サービス】 【訓練等給付のサービス】 |
障がい者支援課 |
|
児童福祉法制度 |
障がいのある児童が、通所サービスを利用することができる制度 【サービス内容】 |
4 子育て・児童
(1)児童の健全育成・虐待
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
公認心理士による子育て相談 |
子育ての悩みやこどもへの接し方に関する相談に応じ、必要な助言を行っています。 |
家庭支援課 |
|
こどもの虐待が疑われるときは、早急に市(家庭支援課)やこども家庭センターなど関係機関に通告・相談してください。 |
家庭支援課 ◎夜間、休日、緊急時 加古川警察署 児童相談所全国共通ダイヤル189 |
|
|
地域のボランティアや民間団体などが、主にこどもや親子に対し、無料または安価で食事を提供する場 |
社会福祉協議会 |
(2)児童手当等
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度 |
家庭支援課 |
|
|
精神または身体に障がいを有する児童について特別児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度 |
(3)母子保健事業
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
妊娠・出産・育児に関する一貫した記録を行う手帳として、また予防接種済証として使用 妊娠・出産・子育てに関する子育て支援事業の案内と妊婦相談を実施 |
育児保健課 |
|
|
産前教室 |
妊娠、出産、育児に対する妊婦の不安軽減を図るため、知識の普及のみならず、実習を通した体験学習の場として実施する教室 |
|
|
妊婦に対し、 妊娠・出産・育児について適切な指導を行い、 母体の健康の保持増進と心身ともに健全な子どもの出生をはかることを目的として実施する訪問 |
||
|
生後1年未満の赤ちゃんとその母親を対象に、医療機関や助産所等で母親の心身のケアや育児指導・相談が受けられる事業 |
||
|
乳児期に保健指導を充実させ、育児不安を軽減し、スムーズな子育てができるよう援助するとともに、母親同士の交流を図ることにより、育児の仲間づくりを支援する場 |
||
|
新生児訪問 |
新生児は抵抗力が弱く、いろいろな疾病にかかりやすく、育児上最も注意が必要な時期であるため、出生連絡票等により保健指導を要する家庭を把握し、保健師または助産師による訪問を実施 |
育児保健課
|
|
こんにちは赤ちゃん訪問 |
生後2~3か月の乳児がいる全ての家庭を訪問し、不安や悩み等を聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、こどもの健やかな育成を図ることを目的として実施する訪問 |
|
|
低体重児の届出と未熟児訪問 |
未熟児は、正常児とくらべて身体の発達が未発達で、疾病にもかかりやすいため、低体重児の届出等により対象者を速やかに把握し、養育上の必要に応じ、保健師または助産師が家庭の訪問を実施 |
|
|
乳幼児健診未受診者の家庭訪問 |
乳幼児健診の未受診は、児童虐待のリスクの要因のひとつとして挙げられていることから、未受診者の家庭を訪問し状況の把握に努め、受診勧奨するとともに、子どもの安全確認を行う訪問 |
|
| 不妊・不育症治療費助成事業 | 不妊・不育症治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減することで当該治療を受けやすくし、安心して結婚・出産できるよう治療費の一部を助成する事業 |
育児保健課 |
|
4か月児健康診査 |
乳児期は、 心身の成長、 発達が急速に進む時期であることから、 健康状態を確認し、 疾病の早期発見、 適切な治療や療育に努め、より健やかな発達を促すとともに、保護者への育児支援を行うことを目的として実施する健康診査 |
育児保健課 |
|
10か月児健康診査 |
心身の成長発達が急速に進み、 成長に大きな影響を与える時期であることから、異常の早期発見、 早期治療を図るとともに、保護者への育児支援をとおして、よりよい親子関係や児の健やかな成長を促すことを目的として指定医療機関での個別受診で実施する健康診査 |
|
|
1歳6か月児健康診査 |
心身の発達や歯の健康、 疾病を早期に発見し、 健やかな発育増進を図るとともに保護者への育児支援を行うことを目的として実施する健康診査 |
|
|
3歳児健康診査 |
幼児の健全な育成のために、 心身の発達や歯の健康、 視聴覚の問題を早期に発見するとともに、 保護者への育児支援を行うことを目的として実施する健康診査 |
|
|
各乳幼児健診・電話相談・家庭訪問等で、主に精神運動発達等の経過観察が必要と思われる乳幼児とその保護者を対象に、小児科医・心理士・保健師による発達相談を実施する事業 |
||
|
健診後のフォロー教室 |
こどもの発達に不安があったり、育児不安・ストレス等、育児に悩む保護者を対象に親子のふれあい遊びの体験学習やグループ相談を行い、心身の発達を促すことを目的に実施する教室 |
|
|
子育て相談事業 |
心理相談員が、育児の悩みやこどもの発達に関する電話や面接相談を行い、乳幼児をもつ親の不安解消を図る相談事業 |
|
|
こどもの発達や特性について理解を深めるため、5歳児とその保護者を対象に、心理士・保健師による相談を実施する事業 |
(4)保育所等
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
保育所等に関すること |
幼児保育課 |
|
|
保育料に関すること |
||
|
保育所等で一時的に児童をお預かりする制度 |
幼児保育課 |
|
|
医療機関による入院治療の必要はないが、集団保育が困難であると医師が認めたときに、その児童の状態により施設で一時的に預かる制度 |
幼児保育課 |
|
|
児童の保護者が病気、出産など社会的な事由で、一時的に家庭で児童の養育ができない場合、児童養護施設、里親の居宅等で預り、養育する制度 |
家庭支援課 |
|
|
産前、産後に、家事や育児の支援を希望する家庭に対して家事ヘルパーを派遣する事業 |
||
|
こどもの一時預かりや保育所・習い事への送迎などの援助を受けたい方に、その援助をしたい地域のボランティアをご紹介しています。生後6ヵ月未満の子どもを養育する方には、在宅時に育児のお手伝いをするあかちゃんサポーターをご紹介しています。 |
ファミリーサポートセンター |
(5)ひとり親家庭の福祉
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、 当該児童について児童扶養手当を支給し、 もって児童の福祉の増進を図ることを目的する手当 |
家庭支援課 |
|
|
母子父子自立支援員が母子父子寡婦福祉資金の貸付相談や、 母子家庭・父子家庭の各種の相談に応じ、 その自立に必要な助言を行っています。 |
家庭支援課 |
|
|
母子父子寡婦福祉資金の貸付制度 |
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を増進することを目的とした修学資金等の貸付制度 |
|
|
ひとり親家庭の親の能力開発を支援し自立促進を図るため、指定する教育訓練講座の修了後に受講料の一部を支給する制度 |
||
|
ひとり親家庭の親が、仕事に結びつく資格(看護師、介護福祉士、保育士など)の取得を目的とした学校などへ1年以上通学するため仕事に就くことができない場合に訓練促進給付金を支給する制度 |
||
|
ひとり親家庭の親かその子どもが、高等学校卒業程度認定試験の対策講座を受講した場合、受講料の一部を支給する制度 |
||
|
一時的に生活援助が必要なひとり親家庭にヘルパーを派遣する事業 |
||
|
ひとり親家庭の小学4年生から小学6年生のこどもに生活習慣の習得や学習支援、勉強の相談を受ける事業 |
5 低所得者
(1)生活保護等
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
生活保護は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、 必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度 |
生活福祉課 |
|
|
宿題をしない、できないなど、学習習慣が身についていない子ども及びその保護者に対し、学習意欲の向上を図るなど将来的な自立に向けての支援を行う事業 |
||
|
生活困窮者に対して自立支援策の強化を図るために、本人の尊厳と意思を十分尊重しながら、どのような支援が必要かを一緒に考え、就労、ひきこもり、その他の課題に対する支援プランを作成 |
地域福祉課 |
|
|
離職等により住宅を失った又は失う恐れのある人で、一定の要件を満たす場合、家賃相当額の「住居確保給付金」を支給する制度 |
||
|
ホームレス等、一定の住居を持たない生活困窮者に対して、一時的な宿泊場所や衣食の提供等の支援を行う事業 |
||
| 債務整理を支援するほか、家計収支の均衡を目的として支援する事業 | ||
|
仕事をしたことがない、働く自信がないといった方に対し、生活習慣・日常生活の立直しなどを通して、就労に向けた支援を行う事業 |
6 健康増進・福祉医療
(1)成人保健事業
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
生活習慣病の予防及び疾病の早期発見・早期治療を目的に基本健康診査や各種がん検診等を実施 |
市民健康課 |
|
|
がんの治療に伴う外見の悩みを抱えるがん患者に対し、医療用ウィッグや乳房補整具の購入費用の一部を助成する事業 |
||
|
健康教育 |
生活習慣病などの健康に関する正しい知識の普及 |
市民健康課 |
|
心身の健康に関する相談への個別対応 |
||
|
1.対面相談事業 |
(2)一般介護予防事業
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
介護予防普及啓発事業 |
一般高齢者に対して、介護予防に関する知識の普及・啓発を行い自主的な活動を支援する事業 |
高齢者支援課 |
|
1.いきいき百歳体操活動支援事業 2.いきいき百歳体操サポーター養成事業「いきいき百歳体操」の普及にむけ、参加の声かけや教室運営の手伝い、教室の立ち上げなどを行うサポーターを養成する事業 |
(3)予防接種・救急医療事業
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法に基づき、予防接種を実施 |
育児保健課 地域医療課 |
|
|
救急医療事業 |
(1)日曜・祝日・年末年始の救急診療体制(軽症患者対象) 2.外科系 3.眼科・耳鼻咽喉科 4.歯科 (2)東はりま夜間休日応急診療センター (3)加古川歯科保健センター 2.障害児(者)歯科診療 3.歯科保健指導 |
|
(4)福祉医療費助成事業
|
施策・事業 |
内 容 |
問い合わせ先等 |
|---|---|---|
|
非課税世帯の65歳から69歳までの人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度 |
医療助成年金課 |
|
|
一定の等級の障害者手帳を所持している人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度 |
||
|
後期高齢者医療保険の加入者で一定の等級の障害者手帳を所持している人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度 |
||
|
死別・離婚などにより、児童を育てるひとり親とその児童に対し、所得要件を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度 |
||
|
0歳から18歳までの人に対して、医療費を助成する制度 |
||
|
他の公費助成制度との差額請求について |
福祉医療受給者が、対象となる公費助成制度を利用した場合の医療費の自己負担額から、福祉医療費助成制度の一部負担金に相当する額を控除した額を助成する制度 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
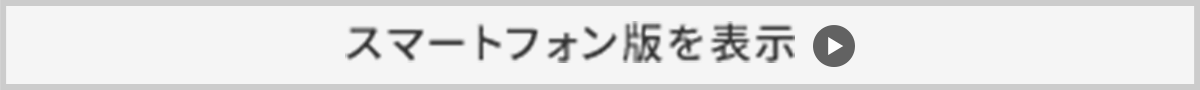








更新日:2025年05月07日