施政方針
令和7年度施政方針
令和7年第1回市議会定例会の初日(令和7年2月20日)に行われた令和7年度施政方針演説の内容です。
本日、令和7年第1回市議会定例会が開会され、令和7年度当初予算案をはじめとする重要案件をご審議いただくにあたり、市政運営における理念や中長期的な方向性、令和7年度に取り組む施策等について申しあげます。
(一歩先を見据えた果敢なチャレンジ、希望を切り拓く一年に)
昨年は、日本社会全体が、ようやくコロナ禍を乗り越え、様々な経済・社会活動が本格的に再始動しました。しかしながら、不安定な国際情勢に伴う資源・原材料価格の高騰や金融政策の差異による円安等により、物価が高騰し続けており、企業経営・市民生活双方にとって、厳しい状況が続いています。
また、地域社会においては、都市部への人口集中が進む中、労働力不足や、各地域における様々な役割の担い手不足が生じています。一方、ケアを必要とする高齢者人口は、今後増加することが見込まれており、これらに伴う課題がより顕在化していくものと思われます。
このように、私たちを取り巻く環境は、以前にも増して、急速に変化し続けています。従来の発想にとらわれない、果敢なチャレンジが求められています。本地域に暮らす市民一人一人が、より大きな幸せを実感できるよう、常に一歩先を見据え、本地域がさらに発展していく明るい道筋を切り拓いてまいります。
(一人一人が幸せ「ウェルビーイング」を実感できるまちをめざして)
近年、人口減少や経済成長の停滞を背景に、これまでの「物質的な豊かさ」から「生活の質」や「心の豊かさ」を重視する価値観への転換が進んでいます。本市では、総合計画に「夢と希望を描き 幸せを実感できるまち 加古川」を掲げ、市民の幸福感の向上をめざし、様々な取組を進めてまいりました。
全国に先駆けて令和4年度から導入しているウェルビーイング指標に基づく調査によりますと、市民の幸福感は全国平均を上回る高い水準を維持しています。
「健康状況」や「地域とのつながり」、「文化・芸術」、「自己効力感」などの分野で、全国と比較しても満足度が高く、これらの分野が市民の幸福感と強い相関関係にあることが示されています。こうした調査結果は、市民の暮らしやすさや幸福感を向上させるための今後の重要な指針となります。
引き続き、加古川市民全体としての幸福感の向上をめざしつつ、すべての人が住み慣れた地域で安全に、安心して暮らし続けられるよう、SDGsの理念である、持続可能で、“誰一人取り残さない”地域づくりにもしっかりと取り組んでまいります。
(加古川ならではの魅力づくり)
本市では、加古川をはじめとする自然環境などの特性を生かし、市民の皆さまが加古川市を「自分たちのまち」として誇りに思えるよう、「加古川ならではの魅力づくり」を中長期的なまちづくりの方向性として掲げています。新年度においても、この方針に基づき、引き続き3つの柱を重点的に取り組んでまいります。
一つ目は、「身近な自然を活(い)かした魅力づくり」です。加古川河川敷を活用した「かわまちづくり」につきましては、イベント活動支援や情報発信により、その認知度は年々高まり、市民の皆さまの憩いの場としての大きな期待を感じております。昨年は、賑わい交流拠点の整備運営を行う民間事業者が決定しました。令和10年4月のオープンをめざし、引き続き国とも連携して河川敷の整備を進め、賑わいと憩いの空間の創出に努めてまいります。
また、本年3月末には、大型遊具やサイクリストの休憩施設を備えた権現総合公園がいよいよオープンします。さらに日岡山公園におきましてもスケートボードや3x3(スリーエックススリー)のプレイエリアを整備したニュースポーツゾーンが先行してオープンします。これらの新たな施設を通じて、本市ならではの新たな魅力につなげてまいります。
二つ目は、「駅周辺のにぎわいづくり」です。今年度は、JR加古川駅の駅南広場に人工芝の整備やストリートファニチャーを設置する社会実験を行い、様々な世代の方々に新しい広場での過ごし方を体験いただきました。現在、再整備に向けた基本計画の策定を進めており、新年度には複合施設や駅前広場の基本方針の公表を予定しています。本市の玄関口にふさわしい空間となるよう、引き続きJR加古川駅から河川敷を含む一帯を「居心地が良く、歩きたくなるまちなか」とするウォーカブルなまちづくりを進めてまいります。
三つ目は、「産業誘致による雇用の創出」です。新たな産業用地を創出するため、旧公設地方卸売市場跡地につきましては、昨年から解体工事を進めており、新年度には跡地活用事業者の募集要項を整理するなど、公募に向けた取組を進めてまいります。また、志方中央地区においても、業務代行方式を活用した組合施行による土地区画整理事業の準備を進めております。これらの取組を着実に進め、本地域の活性化及び商工業の発展につなげてまいります。
(未来を見据えた社会課題への挑戦)
日本社会全体に共通する社会課題の解決に向けて、引き続き、果敢にチャレンジしてまいります。
高齢化の進行や生産年齢人口の減少などに伴う課題解決を図るため、AI技術などのデジタル技術の導入が急速に進んでいます。本市におきましても、「見守りカメラ」の増設やAI機能を搭載した「高度化見守りカメラ」の運用、公共施設の予約システムの導入など、市民の利便性の向上や安全・安心のまちづくりを支える「スマートシティ」の実現に向けて、より一層推進してまいります。
また、地球温暖化や環境問題への対応は喫緊の課題であり、持続可能な社会の実現に向け、1自治体としても不断に取り組んでいくことが求められています。本市では太陽光発電設備や省エネ設備の導入支援制度に加えて、エコクリーンピアはりまでごみ焼却時に発電される電力を東播磨2市2町の公共施設で活用すべく準備を進めています。地域内でのエネルギーの循環を促進し、カーボンニュートラル社会の実現をめざしてまいります。
さらに、未来を担うこどもや若者、子育て世代への支援を充実させることも重要です。妊娠期から子育て、教育、社会への自立に至るまでの切れ目のない支援を通じて、一人一人が夢や希望を持ち、日々の歩みを進められるよう、全力を尽くしてまいります。
そして、高齢化が進む中、支援を必要とする高齢者が安心して暮らせる地域を築くことも急務となっています。本市では、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現に向け、健康増進はもとより、地域包括ケアのさらなる充実など、すべての世代が安心して暮らせるまちをめざして取り組んでまいります。
以上、今後の市政運営にあたっての理念や中長期的な方向性、関連する一部施策などについて申しあげました。ここからは、重複する部分もございますが、総合計画に掲げる基本目標及びまちづくりの進め方に従い、順次、重点的な施策について述べさせていただきます。
1.【心豊かに暮らせるまち】
一つ目に、「心豊かに暮らせるまち」についてです。
近年、急速な少子化や人口減少、共働き家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、こども・若者や子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした課題に対応し、若い世代が結婚・出産・子育ての希望が叶えられるまちをめざして、本年3月に策定する「こども・若者計画」に基づき、こどもや若者、子育て家庭のライフステージに応じて切れ目のない支援を展開してまいります。
若い世代の支援につきましては、これからの未来を担う高校生から大学生世代にあたる16歳から22歳の若者に対して、物価高騰による負担軽減を図り、安心して学び、生活できるよう応援することを目的として、1人あたり1万5千円相当のデジタルクーポンを配付する事業を実施してまいります。事業実施に際して対象者にWEBアンケートを実施し、若者の声を市政に反映できるよう努めてまいります。
結婚支援につきましては、引き続き兵庫県が運営する「ひょうご出会いサポートセンター」の会員登録料を全額助成するとともに、結婚新生活支援事業による経済的支援を継続し、結婚を希望する方々を支援してまいります。
子育て世代への支援につきましては、これまで実施している乳幼児健診に加え、新たに「5歳児発達相談」を実施いたします。この相談では、こどもの発達や特性について保護者の理解を深め、育児不安の軽減を図るとともに、こどもがその能力を十分に発揮できるよう、就学に向けた早い段階から適切な支援につなげてまいります。これにより出産後から就学までの切れ目のない相談体制を整備してまいります。
就学前の教育・保育につきましては、子育て家庭の孤立感や不安感を軽減し、すべてのこどもの健やかな成長を支援するため、保護者の就労状況や理由を問わず、0歳から2歳の未就園児が保育施設を時間単位で利用できる「こども誰でも通園制度」の開始に向けた準備を進めてまいります。また、子育て世代の負担を軽減し、こどもを育てる喜びを改めて実感していただくことを目的に、これまで試行的に実施していた市立幼稚園と市立認定こども園に通う園児を対象とした、リフレッシュのための一時預かりを本格的に開始いたします。
さらに、昨年より建設に着手している「かこいろこども園」につきましては、令和8年4月の開園に向けた準備を着実に進めるとともに、「就学前教育・保育施設の再編計画」に基づき、幼児教育に望ましい集団規模の確保を図ってまいります。
次に、このたび、教育委員会において、本市の教育を振興するための施策に関する基本的な計画である「かこがわ教育ビジョン」が策定されました。この策定を受けて、総合教育会議で教育委員会と協議・調整した結果を踏まえ、この「かこがわ教育ビジョン」を「教育大綱」として位置付けたところです。「ともに生きる こころ豊かな 人づくり」という教育の基本理念のもと、教育委員会と力をあわせて教育施策に取り組んでまいります。
義務教育の充実につきましては、本市では先駆的に協同的探究学習の取組を進めており、「わかる学力」の育成と自己肯定感の向上に良い効果が表れているものと実感しています。これまでの成果を生かし、さらなる授業改善と研究に取り組み、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた質の高い授業づくりを進め、本市の魅力としてその効果を広く発信してまいります。
英語教育につきましては、ALTの活用に加え、1人1台の端末を活用したオンライン英会話や学習コンテンツの導入により、対面型と非対面型のハイブリッド型英語教育を進めてまいりました。外部検定試験から得た客観的評価結果を基にした授業改善を図りながら、引き続きグローバル化に対応した英語力の育成に取り組んでまいります。
次に、中学校部活動の地域移行につきましては、国において、学校内で行われてきた部活動から、地域クラブ活動として地域全体で支え、豊かで幅広い活動へ展開していくことを明確にするため、「地域展開」へ名称が変更されます。本市におきましては、令和3年度から「部活動のあり方検討委員会」において協議を開始し、試行プランの実施や関係者へのアンケート調査のほか、国や県、そして先進的に取り組んでいる市町の動向を注視しながら、検証を重ねてまいりました。そして、このたび、令和9年8月にすべての部活動を終了し、こどもたちと地域の方がともに活動する「(仮称)加古川地域クラブ活動」を新たに開始することとします。新しくはじまる地域クラブ活動においては、将来にわたってこどもたちが主体的に選択し、多様な活動に参加できる機会を確保することをめざすとともに、教職員の働き方改革を図ります。新年度におきましては、中学校部活動から「(仮称)加古川地域クラブ活動」への地域展開に関する関係者への周知・理解促進を図るとともに、活動団体の確保に向けて準備を進めます。活動場所の整備など課題も様々あることから、国や県と連携しながら、取組を着実に進めてまいります。
いじめ防止対策につきましては、未然防止、見逃しゼロをめざして、学校生活に関するアンケートや心の相談アンケート、教育相談等を通じて、いじめの早期発見・早期対応に、教育委員会とともに引き続き全力で取り組んでまいります。
次に、本市の不登校児童生徒数は、全国や県内の状況と同様に年々増加傾向にあります。そのため、今年度は、わかば教室をリニューアルし、そのサテライト教室についても1教室増設して通いやすい体制を整えるなど、支援の拡充を図ってまいりました。新年度におきましては、学校内の支援として、メンタルサポーターを中学校だけでなく、すべての小学校へ配置すべく、新たに6校に配置するなど段階的に増員を進めます。また、校内サポートルームの環境整備を図り、学校内の居場所づくりにより、不登校及び不登校傾向の児童生徒への支援の充実を図ってまいります。そのほか、学びのリスタートができるよう、引き続き学びの多様化学校の早期設置に向けて検討を進めてまいります。
両荘みらい学園は、地域をはじめ非常に多くの方々の協力を得て、令和6年4月に開校し、学校教育目標である「ふるさとを愛し、こころ豊かに、学びあう子どもの育成」を推進しているところです。また、両荘みらい学園学校図書館の地域開放サービスも開始しております。読書に親しめる環境を身近な場所に整備し、地域の方々の読書活動を一層推進させるとともに、学校図書館を介した児童生徒と地域との交流機会を創出するなど、地域に愛される学校図書館として、引き続き運用してまいります。
安全で快適な学習環境の整備につきましては、学校プール施設の老朽化対策とあわせて、小中学校における水泳授業の指導体制の充実、教員の負担軽減に向けた検証を行うことを目的に、昨年度から水泳授業指導業務の民間委託を試行実施してまいりました。そして、児童生徒、保護者及び教員を対象にしたアンケート調査の結果も踏まえ、昨年、「加古川市立学校プール施設及び水泳授業のあり方に関する基本方針」を定めました。今後は、本方針に基づき、すべての小学校において、民間施設活用型と指導者派遣型による水泳授業指導業務の民間委託を進めてまいります。一方、中学校においては、現行と同様、自校のプール施設で体育専科の教員が水泳授業指導を行うことを基本としつつ、今後の児童生徒数の状況や民間事業者の受入体制の拡充状況を注視しながら、より効果的な授業の実施方法について、引き続き検討してまいります。
そのほかの学校の施設面につきましては、トイレの洋式化は、新年度で校舎トイレの改修工事を完了させることとしております。小中学校のエアコンの整備につきましては、児童生徒が使用する特別教室への整備を引き続き進めてまいります。そして、体育館への整備につきましては、熱中症対策や災害時の避難所環境の向上などの課題に対応すべく、より効率的で効果的な整備方法について検証しながら、早期設置に向けて準備を進めてまいります。また、学校施設の多くが建築後30年以上を経過し老朽化が進んでいるため、長寿命化改修も計画的に進めてまいります。
市内の児童クラブにつきましては、今年度から全体の約半分を占める36クラブにおいて、民間委託による運営を開始しました。児童クラブの需要を注視しながら、安心してこどもたちが利用できるよう、民間委託による効果検証をしっかり行い、全クラブへの民間委託の拡充の検討も含め、安定的な運営の確立と均一かつ良質なサービスの提供等のさらなる充実をめざしてまいります。
次に、スポーツ・レクリエーション活動の推進につきましては、漕艇センターにおいて今年度からカヌーの一般利用を開始し、初心者や幅広い年代の方に楽しんでいただけることから、引き続き、ローイング競技もあわせて普及促進に取り組んでまいります。また、障がい者スポーツにつきましては、かこパラスポーツ王国やボッチャの交流大会などを通じて、引き続き、障がい者スポーツへの理解と普及促進を図ってまいります。なお、加古川マラソン大会につきましては、毎年、加古川河川敷マラソンコースを利用して開催しておりますが、今年度からマラソンコース周辺の道路工事等により、従来どおりの開催が困難な期間が生じる見込みです。そうした中にあっても、スポーツの魅力を感じることができる機会の創出に向けて取り組んでまいります。
文化・芸術の振興につきましては、将棋文化を取り入れたまちづくりの推進を図るため、公益社団法人日本将棋連盟主催で将棋界最大のイベントである「将棋の日」を本年11月に開催いたします。イベントの様子はNHKの公開収録番組として全国放送される予定です。今後とも、将棋に触れる機会を充実し、「棋士のまち加古川」としての魅力をさらに発信してまいります。また、「音楽のまち加古川」につきましても、「ウェルネスティーンズコンサート」や「ケイオンコンサート」などの音楽イベントをはじめ、地域の身近な場所でのコンサートなど、市民の皆さまが音楽に触れる機会の提供や、地域で音楽活動をされる方々の発表の場の創出に努めてまいります。そして、これらの取組をともに進める一般財団法人加古川市ウェルネス協会の経営基盤の強化を図り、連携を深めてまいります。
加古川総合文化センターにつきましては、隣接する旧加古川総合保健センターも含めた一帯を「加古川総合文化センターエリア」として位置付け、賑わいが生まれる施設となるよう、現在、基本構想の策定を進めており、引き続き検討してまいります。
互いに尊重しあって暮らせる社会の実現につきましては、性の多様性の尊重に関する取組として、今年度は、児童生徒に対する普及啓発を図ってまいりました。新年度におきましても、これらの取組を継続し、性の多様性に関する正しい知識の普及啓発をさらに進めてまいります。また、社会環境の変化に伴い多様化・複雑化する人権課題に対しましても、引き続き人権教育や啓発を推進してまいります。
2.【安心して暮らせるまち】
次に、「安心して暮らせるまち」についてです。
社会・経済情勢が急速に変化する中、生産年齢人口の減少、高齢化がさらに進み、地域における安心な暮らしをどのように維持していくのか、今後大きな課題となってまいります。従来のつながりだけでなく、地域に暮らす、あらゆる人や関係団体等が分野を超えてつながり、それぞれが持つ強みを生かして、重層的なネットワークや支援体制を構築することが必要になってまいります。
そのような中、高齢者の安心な暮らしを社会全体で守っていくため、まず、介護保険制度における総合事業の見直しを進めてまいります。今後、介護サービスを必要とする人が増加する一方で、支える人材の減少が進んでいきます。本市の地域特性を生かした制度づくりを検討し、すべての人が必要な支援を受けられる仕組みの構築をめざします。
また、「ささえあい協議会」を中心に、地域課題の解決に取り組む担い手を支援し、地域での支え合いをさらに強化してまいります。例えば、高齢者の買い物支援や外出サポートなど、地域内での助け合いの環境を整備するための補助制度を設け、各地域の自発的な取組の充実を図ってまいります。
さらに、将来を見据えた地域包括ケアシステムの構築をめざし、在宅医療と介護の連携を中長期的に強化していくため、ICTを活用した新たな取組に着手します。在宅医療・介護従事者による具体的かつ効率的なケアの促進を図り、高齢者やその家族が、住み慣れた自宅での生活を積極的に選択できるようにすることで、介護にかかわるすべての方々のウェルビーイングの向上につなげてまいります。
また、相談機能を充実させるため、新年度から成年後見支援センターの体制を強化し、権利擁護支援の役割を充実させるとともに、終活事業についても検討を進めます。地域全体が一丸となって支え合い、本人の意思と尊厳が守られ、誰もが安心して暮らせるまちの実現をめざしてまいります。
健康の保持・増進につきましては、新年度から、患者数が増加する65歳をはじめとして、70歳から5歳刻みの方を対象に、帯状疱疹ワクチンの定期接種を開始します。定期接種の対象外となる50歳以上の方についても、今年度に引き続き接種費用の一部を助成いたします。今後とも、予防接種や早期治療の重要性についての周知を継続し、疾病予防に努めてまいります。
また、歯周病検診の無料対象者を拡充し、従来の40歳・50歳・60歳・70歳に加え、新年度より20歳・25歳・30歳・35歳も対象とすることで、若い世代からの歯周病予防と定期的な受診の習慣化を図ってまいります。
地域医療の充実につきましては、県が実施予定の救急安心センター事業(#7119)に参画いたします。急な病気やケガで、救急車を呼ぶべきか迷った場合に、24時間365日、専門家のアドバイスが電話で受けられます。これらの事業を通じて、増加傾向にある救急需要に対応してまいります。
次に、防災対策についてです。昨今、自然災害が激甚化・頻発化しています。
まず、地域防災力の向上に向けた取組として、自助、共助による備えについて、より一層推進してまいります。出前講座の実施や、市民が多様な視点から防災を考える機会を提供し、防災への理解と関心を深めるとともに、自主防災組織が整備する資機材の購入や防災訓練など、防災活動に対する補助制度の見直しを行います。
また、迅速かつ適切な防災情報の発信力を強化するため、警報や気象情報をLINEをはじめとした市公式のSNSアカウントに自動発信する仕組みを整備してまいります。
消防・救急体制の充実につきましては、市民の安全と生命を守るため、新年度に消防指令センターの更新整備を行い、令和8年度からの稼働をめざします。新システムでは、バックアップ指令装置や救急搬送支援システムなどの新たな機能を追加し、災害などで消防指令センターが機能不全となった場合でも、東消防署で119番通報を受信し、部隊編成や指令を行える体制を整備します。また、救急現場では、タブレットを使用して傷病者の情報を免許証等から読み取り、現場の状況を撮影して転送することで、医療機関との情報共有や、受け入れまでの時間短縮をめざし、傷病者の早期搬送につなげてまいります。
防犯・交通安全対策につきましては、見守りカメラ・見守りサービスのさらなる活用を進めてまいります。とりわけ見守りカメラにつきましては、昨年10月から、AIを搭載した150台の高度化見守りカメラが本格稼働を開始いたしました。稼働開始に伴い、カメラの運用状況についての課題の把握、分析などの効果検証や、適正配置の検討を行いました。新年度におきましては、これらの結果を踏まえた設置場所に見守りカメラを82台増設し、犯罪の抑止や交通事故の未然防止などにつなげてまいります。
消費者保護対策につきましては、デジタル化の進展に伴い、より巧妙化した消費者被害が増加しています。高齢者や情報リテラシーが十分でない児童、生徒だけでなく、高校生や大学生などの若い世代も含めた消費者教育など、幅広い世代に伝わる効果的な消費者啓発に努めてまいります。
3.【活力とにぎわいのあるまち】
次に、「活力とにぎわいのあるまち」についてです。
海外の政治経済動向や資源価格の変動、さらには企業の賃金動向など、わが国の経済や物価を取り巻く状況は依然として不確実性が高く、市民生活や事業者の経営に大きな影響を与えています。特に物価の急激な上昇や全産業にわたる人手不足が及ぼす影響は深刻であり、市民の皆さまの暮らしを支え、まちの活力やにぎわいを維持・向上させるため、引き続き国や県などの関係機関と連携し、効果的な施策を推進してまいります。
その一環として、市内消費を喚起し、地域産業の活性化を図るため、加古川商工会議所が実施する「市内店舗応援キャンペーン」への補助を行い、市内事業者を支援するとともに特産品の認知度の向上を図ってまいります。
農業の振興につきましては、今年度より開始した「アグリスタート補助金」や新規就農者への伴走支援に引き続き取り組むことで、農業者の高齢化や後継者不足への対策を推進してまいります。また、国が策定した「みどりの食料システム戦略」に基づき、持続可能な農業の実現に向けて、新年度は有機農業の効果的な促進につなげるため、次代の農業を担う人材を専門的に育成している兵庫県立農業高校と連携し、有機農業に関する授業や作物の栽培、土壌分析などを実施し、その取組も発信してまいります。
「加古川和牛」や「加古川パスタ」などの特産品につきましては、今年度は阪急電車内の広告活用や、特産品専用のホームページの公開など、積極的なPR活動を展開してまいりました。新年度は、特産品の広告掲載を、生活圏の異なる阪神電車とし、さらなるPR活動を行ってまいります。
また、本市の貴重な森林環境につきましては、森林環境譲与税を有効に活用し、森林整備や保全活動のほか、資源の有効活用等の取組を効果的に進めてまいります。
旧公設地方卸売市場の跡地につきましては、昨年より着手した解体工事を新年度も継続して進め、産業誘致に伴う雇用機会の創出や地域経済の活性化につなげるため、跡地売却に向けた取組を推進してまいります。
観光振興につきましては、本市の観光施策の方向性を示した「観光まちづくり戦略」を改定し、新年度からの5年間を対象とした「加古川市観光まちづくりプラン」を本年3月に策定いたします。このプランに基づき、観光協会と連携しながら、本市の魅力をさらに引き出し、積極的に発信することで市外からの誘客を促進し、交流人口の増加につなげるとともに、歴史や文化、食、自然、産業といった本市の多彩な魅力を市民の皆さまにも楽しんでいただけるような取組を進めてまいります。
4.【快適なまち】
次に、「快適なまち」についてです。
全国的に進行する人口減少や高齢化に対応した持続可能なまちづくりを進めるため、地域の特性と課題に応じた都市基盤の整備と土地利用の適正化を進める必要があります。各拠点の規模や役割に応じた都市機能の誘導と集積を進め、地域間の連携を強化してまいります。
JR加古川駅周辺地区におきましては、駅周辺の再整備に向けた公共機能を導入する複合施設計画や駅前広場の基本設計、事業に伴い変化する交通体系など、複数年をかけた検討業務をスタートしました。新年度には再整備の基本方針を公表し、シンポジウムやワークショップを通じて将来のイメージを共有することで、再整備に対する市民や関係者の皆さまの期待感や機運を高めてまいります。また、社会実験として、今年度の駅前広場に加え、周辺道路にも範囲を広げることで、公共空間における多様な利用シーンを想定した空間づくりの可能性について検討を進めてまいります。そして、JR加古川駅から河川敷を含む一帯のエリアが「居心地が良く、歩きたくなるまちなか」となるよう、加古川ならではのウォーカブルなまちづくりを市民や関係者とともに進めてまいります。あわせて、防災道路の延伸に向けた事業推進と本町河原線とJR山陽本線との交差部の暫定整備を着実に進め、中心市街地における回遊性及び防災性の向上を図ってまいります。
一方、副都心であるJR東加古川駅周辺におきましては、鉄道を高架化する連続立体交差事業について、事業主体である兵庫県や鉄道事業者と協力し、課題整理と検討を進めてまいります。山陽電鉄別府駅周辺におきましては、本年2月のダイヤ改正により直通特急列車及び特急列車が終日停車することになります。利用者の増加が見込まれる中で、駅前広場の待合いスペース等の環境整備をはじめ、リニューアルに向けた取組を進め、さらに魅力ある副都心の形成を進めてまいります。
公共交通につきましては、本年2月からJR加古川駅においてデジタルサイネージの運用を開始したほか、4月からは、かこバスに定期を導入することで、さらなる利便性の向上と利用促進を図ってまいります。また、かこバスミニ・山手ルートを拡充するなど、引き続き、地域ニーズの把握に努めながら公共交通空白地域の解消に向け、公共交通サービスの改善を図ってまいります。
災害に強い都市基盤の整備につきましては、引き続き、社会インフラの適切な維持と、災害時における被害を軽減するため、「強靱化(きょうじんか)計画」に基づく必要な対策を着実に推進してまいります。特に、頻発化する豪雨による浸水被害への対応として、雨水幹線の整備や排水路の改築、さらに市内水路の清掃や浚渫(しゅんせつ)作業を行い、流下(りゅうか)能力を確保することに取り組んでおります。また、老朽化したため池の改修にも計画的に着手し、豪雨時の水害リスクを低減してまいります。加えて、主要河川の管理者である国や県、流域の市町と連携し、加古川水系全体での流域治水対策を進めるとともに、市民、事業者、行政が一体となって協力することで、災害に強く、しなやかな地域社会の構築をめざしてまいります。
幹線道路の整備につきましては、中心市街地に集中する交通量の分散と渋滞緩和をめざし、関係機関と協力して着実に取り組んでまいります。神吉中津線につきましては、国との連携のもと橋梁(きょうりょう)部分の整備を進めてまいります。また、国道2号線の加古川橋工区、平野工区及び寺家町工区につきましても事業主体である兵庫県と協力しながら、長期にわたる事業となりますが、幹線道路ネットワークの整備及び交通インフラの強化を着実に進めてまいります。播磨臨海地域道路につきましては、国・県・市が連携しながら住民説明会などを実施し、地域の声も聞きながら、引き続き都市計画手続を着実に進めてまいります。
志方中央地区につきましては、本年1月にまちづくり協議会、事業化アドバイザーと覚書を締結し、土地区画整理事業の事業化に向けて本格的な検討をスタートいたしました。新年度には、地区内の土地利用や事業計画などの検討に加え、アクセス道路の測量を進めるなど、まちづくり協議会との連携のもと、スピード感を持って産業用地の創出に取り組んでまいります。
水道事業及び下水道事業につきましては、市民生活を支えるライフラインを維持するため持続可能な経営を進めてまいります。水道事業におきましては、平常時はもちろんのこと、災害時にも安定して水を供給するため、ポンプ場や管路の更新・耐震化を進めるとともに、良質な水道水の供給に向けた施設整備を行います。また、下水道事業におきましては、老朽化した施設の更新や維持管理をより効率的・効果的に進めるため、新たな官民連携手法であるウォーターPPPの導入を進めてまいります。本市は、国土交通省の導入促進に向けたモデル都市に選定されており、今後、国の支援を受けながら具体的な検討を進めてまいります。あわせて、引き続き未普及地域の解消を進めるなど、地域の安全で快適な生活環境を支えていきます。
5.【うるおいのあるまち】
次に、「うるおいのあるまち」についてです。
近年、地球温暖化の進行による気温の上昇が続き、異常気象や自然災害が頻発しています。これらは私たちの日常生活に深刻な影響を与えており、気候変動への対応は急務となっています。
本市では、こうした環境問題に真摯に向き合い、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組をさらに加速させてまいります。地球温暖化の進行を食い止めるためには、エネルギー利用の効率化や資源の循環が不可欠です。次代を担うこどもたちの未来を守るためにも、市民の皆さまとともに、環境に優しい施策を一層進め、持続可能な社会の実現をめざしてまいります。
新年度におきましては、エコクリーンピアはりまでごみ焼却時に発電されたCO2フリーの電力を2市2町の公共施設で有効活用するため、「地域新電力会社」の立ち上げに取り組んでまいります。
また、今年度から実施している市民や事業者の皆さまへの太陽光発電設備や省エネ設備の導入費用の助成を継続し、再生可能エネルギーの普及や省エネルギー化に努めてまいります。
公共用水域の保全対策につきましては、老朽化に伴い再整備を行っていた尾上処理工場が今年度中に完成します。この施設は、従来のし尿等の処理機能だけでなく、汚泥再生処理センターとして施設から回収した汚泥やリンを資源化することにより、循環型社会の形成を推進します。公共用水域の保全と合わせて、環境負荷の低減を実現することで、循環型社会の構築を進め、市民生活の安全と自然環境の調和を図ります。
親水空間の活用につきましては、「身近な自然を活(い)かした魅力づくり」として、JR加古川駅から歩いていくことができる加古川河川敷に賑わいと憩いの空間を創出する「かわまちづくり」の取組を進めています。市民意識調査でお聞きしている「かわまちづくり」に対する認知度も年々高まってきており、市民活動団体等の皆さまが開催されるイベントや情報発信などにより、期待の高まりを感じております。昨年には、「かわまちづくり計画」において「賑わい交流拠点」と位置付ける、一級河川加古川左岸堤防(ていぼう)上の事業用地に、飲食施設等を整備運営する民間事業者が決定いたしました。新年度におきましては、令和10年4月の全体オープンに向けて民間事業者と設計の調整を進めるとともに、引き続き国と市が連携し、河川敷や護岸の整備のほか、河川空間のオープン化に向けた手続を着実に進めてまいります。
本年3月末には権現総合公園、新年度には日岡山公園のニュースポーツゾーンのオープンも予定しており、加古川の新たな魅力となることを期待しております。日岡山公園につきましては、Park-PFI、指定管理及び設計・施工を一体的に実施する事業者を再公募し、多世代が集い憩える空間づくりに引き続き取り組んでまいります。また、尾上公園につきましては進入路の整備を行い、多目的に利用できる広場の整備を進めてまいります。
一方、今後見込まれる需要増加と施設の老朽化に対応するための斎場の整備につきましては、令和9年度以降の改修に向けて、火葬炉の更新及び維持補修並びに斎場全般の運営を行う事業者を選定し、計画的に取組を進めてまいります。
6.【まちづくりの進め方】
最後に、「まちづくりの進め方」についてです。
社会状況を反映し、本市では、社会保障関係費をはじめとする経常経費が今後も増加すると見込まれています。厳しい財政状況を踏まえながら、多様化する課題に対応していくためには、新たな事業展開とともに、既存事業の継続的な検証や見直しに取り組んで行く必要があります。限られた財源のもと、市民にも理解を求めながら、将来を見据え、市民にとって真に必要な施策を慎重に選択してまいります。
また、市民が幸せを実感できるまちづくりと、持続可能な財政運営を両立させるためにも、多様な主体が連携して課題解決に取り組む「協働のまちづくり」を進めているところであり、今まで地域を支えて来られた方や団体に加えて、様々な主体の参画を得て、地域全体で支え合うことが大切です。
多様な主体と行政との協働によるまちづくりにつきましては、協働のまちづくり推進事業補助金のスタート応援型(学生枠)において、事業を実施する前年度に提案を受ける現行のスキームに加え、実施年度においても募集を受け付けることで、学年毎に状況が変わる学生の皆さまにとって、より使いやすい制度になるよう工夫してまいります。
あわせて、本市では新年度以降、令和9年度からの5年間を見据えた総合計画の策定準備を本格化してまいります。3月には高校生を対象に未来のまちづくりについて考えていただくワークショップを実施するなど、計画には若い世代の意見も取り入れ、次世代を見据えたまちづくりを進めてまいります。
また、官民協働で実施しているウェルピーポイント制度につきましては、リニューアルした見守り検知アプリ「みまもりアプリ」による「ながら見守り」ボランティアを新たにポイント付与の対象にするなど、対象事業を拡充いたします。引き続き、社会貢献や健康づくりに取り組むきっかけや、継続する楽しみとなるよう、本制度の普及・啓発に取り組んでまいります。
地域コミュニティ団体の活性化につきましては、昨年度に実施した町内会長・自治会長へのアンケート結果を踏まえ、町内会運営に関する相談支援をはじめ、公園管理業務の見直しなど負担軽減に向けて取り組んできたところです。新年度におきましては、地域住民の活動拠点である自治集会所を整備するための補助上限額を、昨今の物価高騰や建築資材の値上げの状況を踏まえて引き上げることで、地域の絆づくりにとって重要な活動拠点の維持を支援します。町内会・自治会の持続可能性を高めるさらなる負担軽減に向けて、引き続き町内会連合会や関係部局との協議を進めてまいります。
次に、デジタル技術を活用した取組についてですが、本市は、新しいデジタル技術やデータを有効に活用した取組により「スマートシティ」として全国から注目を集めています。これまで、見守りカメラ・見守りサービスの拡充に加え、ワンコイン浸水センサなどの広域展開を進め、市民の安全・安心を支える取組を推進してまいりました。さらに、加古川市版Decidimにつきましては、デザインや機能の改善を図り、より使いやすい形で市民の意見を反映できる仕組みづくりを進めています。
新年度においては、公共施設の予約システムを新たに導入いたします。これまでスポーツ施設を対象としていた予約システムを、文化施設や市民交流ひろばをはじめとした多くの施設に拡充するとともに、オンライン決済による支払いを可能とするなど、利用者の利便性を大幅に向上させてまいります。これにより、市民の皆さまが地域の公共施設をより気軽に利用しやすい環境を整えてまいります。
シティプロモーションにつきましては、市民の皆さまにまちへの愛着や誇りを持っていただけるよう、メディア向けの広報やSNS、WEB広告など様々な媒体を活用して本市の取組や地域の魅力を発信してまいりました。
新年度は、加古川市まちの魅力発信キャラクター「かこのちゃん」の戦略的展開として、さらなる認知度向上を図るため、公用車やかこバスへのラッピングやミント神戸大型ビジョンでの動画放映など、幅広いPR活動を行います。また、大阪・関西万博会場の兵庫県ゾーンでは、「ひょうご EXPO 41-HYOGO REGIONAL DAY」が開催されます。8月3日は加古川市の日となっており、動画の放映等により本市をPRしてまいります。さらに、本年は市制施行75周年にあたります。5年前の市制70周年では、新型コロナウイルス感染症の影響で、式典等が開催できませんでした。本年6月15日の「ふるさとの日」には、市制70周年時にお渡しできなかった感謝状を贈呈する表彰式を予定しております。大規模な周年事業等は実施いたしませんが、新年度に予定している様々なイベントを「市制75周年記念事業」の一環として実施することで、市民の皆さまだけでなく、本市にゆかりのある皆さまに「ふるさと加古川」への愛着と誇りを深めていただけるよう、市内外へ広くPRしてまいります。
広域的なまちづくりとしましては、本市とともに東播臨海広域行政協議会を構成する高砂市、稲美町、播磨町との連携のもと、エコクリーンピアはりまでの電力地産地消事業の推進など、新たな課題にも取り組んでまいります。また、加古川歯科保健センターにおける、障がい者歯科診療を充実するなど、広域行政の枠組みを有効に活用してまいります。
姫路市を中心として形成する播磨圏域連携中枢都市圏における取組につきましても、本年4月から5年間の「第3期播磨圏域連携中枢都市圏ビジョン」に基づいて連携事業を進め、圏域全体のさらなる活性化を図ってまいります。
おわりに
以上、市政運営における理念や中長期的な重点取組、新年度に予定する各分野の施策等について申し述べてまいりました。
新たな課題と可能性が交差する中、引き続き「夢と希望を描き 幸せを実感できるまち 加古川」の実現に向け、ウェルビーイングの視点を生かした取組を進めてまいります。
未来への挑戦に全力を尽くし、市民一人一人が安心と将来への希望を持てるまちを築くため、議員各位並びに市民の皆さまのご理解とご協力をお願い申しあげ、令和7年度施政方針といたします。
(注釈)当日の演説と表現その他に若干の違いがあることをご了承ください。
過去の施政方針
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画広報課(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9113
ファックス番号:079-424-1370
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
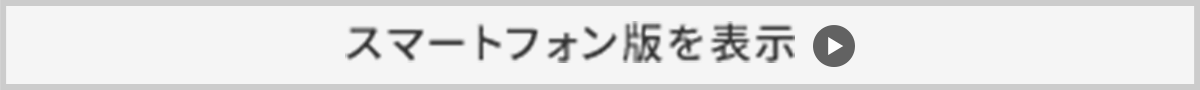








更新日:2025年02月20日