平成31年度施政方針
平成31年第1回市議会定例会の初日(平成31年2月25日)に行われた平成31年度施政方針演説の内容です。
本日、平成31年第1回市議会定例会が開会され、平成31年度当初予算案をはじめ重要案件をご審議いただくにあたり、新年度における施政の方針を申しあげます。
はじめに
私たちを取り巻く環境は、さらなる高齢化、人口減少など、急速に変化し続けています。行政の予算案は、向こう1年間のものとなりますが、市民の皆さまの大切な税や保険料をお預かりし、その使途を提案、執行していく立場といたしましては、常に中長期的な視点で諸課題に取り組んでまいりたいと考えております。そうした中、課題解決へ向けて拡充する分野がある一方で、環境の変化にあわせた改廃が必要な施策も出てまいります。これまで以上の積極的な広報活動により、風通し良くご意見をお寄せいただきながら、その解決に、市民の皆さまと協働して取り組むことができるよう努力してまいります。
市議会議員の皆さまと同じく、私自身、昨年7月に新たな任期を踏み出したところでございますが、「オープン&チャレンジ」というスローガンのもと、「一人一人が生活の中に幸せを実感できる、郷土愛あふれるまちづくり」をめざして、市の魅力をさらに高められるよう、全力で取り組んでまいります。
それでは、後期総合基本計画に掲げる5つの基本目標及びまちづくりの進め方に従い、順次、重点的な施策についての方針を述べさせていただきます。
1.【安心して暮らせるまちをめざして】
一つ目に、「安心して暮らせるまちをめざして」についてです。
安全や安心は、人の幸せや市の魅力を語るうえでは、欠くことができない最も根本的な部分と言えます。各世代の皆さまが、安心して、充実した生活を送ることができるよう、様々な施策に取り組んでまいります。
まず、安心して妊娠、出産、子育てができる支援体制の確保についてです。本市においても大きな課題でありました待機児童につきましては、子ども・子育て支援新制度が始まった平成27年度からの3年間で保育所等の受入枠を1,589人拡大し、大きく改善することができました。しかしながら、本年10月からは幼児教育の無償化がスタートすることとなっており、大きく入園希望者が増加する可能性があることから、今後の状況を注視しつつ、適切に対応してまいります。
一方で、同時に大きな課題となっております、保育士の確保についてですが、今年度から実施している、新規採用及び5年間継続勤務した保育士に一時金を支給する事業者への補助制度に加え、離職されている保育士が、不安なくスムーズに保育現場に復帰できるよう、復職希望者に対する講座や実習の機会を提供いたします。また、奨学金返還支援事業の対象を拡大し、社会福祉法人等に就職し、奨学金を返還されている保育士の方を、新たに補助対象として追加いたします。
さらに、私立認可保育所等における看護師配置事業の補助基準額を大きく拡充し、看護師の配置を促進いたします。保育所等における病気の予防から、保育中に体調不良となる園児への対応の充実を図り、働く子育て世代を支援するとともに、保育士にとっても安心して働くことができる環境の整備につなげてまいります。
また、妊婦への風しんの感染予防を図り、生まれてくる子どもの先天性風しん症候群の発生を予防するため、予防接種が定期接種の対象に追加された男性に加え、妊娠を希望する女性や妊婦の同居家族に対しても予防接種の費用の一部を助成してまいります。
本市では、出産後の乳児を養育する家庭に対し、以前から家事援助等のヘルパーを派遣する事業を実施しているところであり、新年度には、出産前においても妊婦を支援するため、ヘルパー派遣の対象といたします。そして本年4月には、加古川駅南子育てプラザを拡張し、機能を充実させてリニューアルオープンいたします。さらに、加古川駅南子育てプラザで実施している託児サービスを、東加古川子育てプラザにおいても実施することとし、保護者の育児によるストレスの軽減や就職活動のための時間を確保するなど、子育てがしやすいまちづくりを、より一層進めてまいります。
小学校の児童クラブにつきましては、待機児童の解消や高学年への対応、また、一人当たりの床面積の拡充に向けて、順次、整備を進めてまいりました。新年度からは、28小学校のすべてにおいて全学年の受入れを実施いたします。このタイミングにあわせ、利用者負担については、引き上げさせていただきますが、年末年始における開所日の拡大や開所時間の延長を行ってまいります。今後も、利用者ニーズを踏まえたサービスの量の確保及び質の向上に、引き続き取り組んでまいります。
障がい者福祉につきましては、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」に基づき、合理的配慮の提供を促進する助成制度の創設や、「加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション促進条例」を制定するなど、様々な取組を進めているところです。新年度におきましては、重度障がい者の日常生活行動の充実と社会参画の促進を図るため、タクシー料金助成券の複数枚利用を可能にいたします。また、グループホームや医療的ケアサービス提供施設の開設補助制度について、短期入所事業所を対象に加えることで、包括的に施設開設を支援し、障がいのある方や、そのご家族が安心して暮らせる環境整備を促進してまいります。
一方、本市においても高齢化が進んでおり、本年1月時点の65歳以上人口は71,610人で、市民の3.7人に1人となっています。とりわけ、日常生活上の支援が必要な高齢者の増加が予想されるため、多様な主体による、きめ細やかな生活支援サービスの提供体制を構築する必要があります。新年度におきましては、「ささえあい協議会」の充実・強化をめざし、生活支援コーディネーターの配置を拡充してまいります。
また、判断能力に不安を抱える方の自立した生活を支援するため、成年後見制度の利用促進や権利擁護を行う、(仮称)成年後見支援センターの設置に向けた準備を進めてまいります。
介護保険事業につきましては、一般介護予防事業として65歳以上の被保険者が介護施設内で行うボランティア活動を、新たにウェルピーポイントの対象といたします。本年1月時点で市内112会場において行われている、いきいき百歳体操等とともに、高齢者の自発的な健康増進や介護予防を促進してまいります。
さらに、本市独自の基準を満たす手厚い在宅サービスの普及を図るため、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護サービスに、介護給付上の「市独自加算」を新たに設定いたします。
そのほか、健康づくりにつきましては、民間事業者と連携した健康イベントに加え、食育推進のため、野菜摂取量の増加に向けた取組などを展開してまいります。また、生活習慣病の発症及び重症化を予防するため、誰でも気軽に実践できるウォーキングについて、普及啓発及び継続支援を行うとともに、ウェルピーポイントを活用したきっかけづくりにも取り組んでまいります。
国民健康保険事業につきましては、「データヘルス計画」に基づき保健事業を進めているところです。新年度におきましては、39歳の被保険者を対象に、自宅で簡単にできる血液検査を、早期介入簡易検査(サンキュー検査)として実施し、健康への気づきを提供することで40歳からの特定健診の受診率向上につなげてまいります。さらに、歯周病の早期発見・早期治療の機会を提供するとともに、歯周病と深く関わりがある糖尿病の重症化予防を図るため、新たに、30歳の被保険者を対象に歯周病検診を実施するなど、引き続き効果的な事業運営に取り組んでまいります。
次に、防災対策につきましては、昨年頻発した大雨への対応を教訓に、災害発生時に適切な行動をとっていただくことができるよう、平常時からの啓発や災害時の避難の呼びかけなどの情報発信を工夫する必要があると考えています。現在、市からは緊急速報メール、防災ネットかこがわ、ホームページに加え、かこがわ防災アプリやSNS、防災ラジオ、固定電話への自動音声配信など、様々な手段を用いて災害情報をお伝えしているところですが、より分かりやすく、的確な情報伝達に努めてまいります。
一方で、各地では、避難勧告の発令に気づかず避難が遅れた事例も報道されています。今後ますます、自分の身は自分で守るという「自助」、ご近所同士の声掛け、支え合いという「共助」の強化が重要となってまいります。このため、新年度におきましては、自主防災組織のさらなる活性化を図り、自助と共助をより一層促進するため、補助制度を拡充し、資機材の整備だけでなく、避難支援活動に必要な用具の購入、防災訓練や講習会などの防災活動の実施についても支援してまいります。また、避難行動要支援システムの導入により、避難行動要支援者の情報を的確に把握し、自主防災組織等の皆さまへ効果的に提供することで、地域の避難体制の充実に努めてまいります。
消防・救急体制につきましては、年々増加傾向にある救急需要に対し、医師会をはじめ、医療機関とのさらなる連携強化を図り、迅速かつ適切に対応してまいります。
防犯と交通安全対策につきましては、平成29年度から、市内の通学路や公園の周辺、主要道路の交差点などを中心に、順次「見守りカメラ」の設置を進めており、今年度末には1,475台の設置が完了いたします。また、民間事業者との協働により、子どもや認知症の方などの位置情報をご家族にお知らせする「見守りサービス」を、「見守りカメラ」の整備とあわせて導入いたしました。さらに、見守りタグの検知器を、「見守りカメラ」をはじめ、市が所有する公用車や日本郵便株式会社の郵便配達用バイクに設置したほか、市公式アプリ「かこがわアプリ」においても、見守りタグを検知できる機能を付与することで、市内を「網の目」で見守ることができる環境を整備することができました。官民の連携によるこれらの取組は、先日、国土交通省による「第3回先進的まちづくりシティコンペ」において、国土交通大臣賞を受賞しております。今後は、より一層これらの取組の周知に力を入れ、サービスの利用拡大により、市民の皆さまの安全・安心につなげてまいります。
また、消費者保護対策につきましては、身に覚えのない架空請求やインターネットに関するトラブルなどの相談が、消費生活センターに寄せられています。消費生活がますます多様化・複雑化する中で、「わがこと意識」を持ち、正しい知識と情報を基に被害を未然に防止することができるよう、出前講座や街頭啓発などをはじめ、地域や関係機関等と連携した取組を、今後とも推進してまいります。
そのほか、犯罪をした者等が、社会で孤立することなく、円滑に社会復帰することができるよう、「再犯防止推進法」に基づく「再犯防止推進計画」の策定に向けて準備を進めてまいります。
2.【心豊かに暮らせるまちをめざして】
次に、「心豊かに暮らせるまちをめざして」についてです。
変化の激しい時代にあっても、子どもたちが未来を切り拓(ひら)くために必要な資質・能力を育成するため、新学習指導要領に沿った効果的な教育の実践が求められています。昨年4月から市内すべての小中学校で実践している「協同的探究学習」につきましては、その成果を広く全校で共有し展開することで、授業の質の向上を図り、「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざしてまいります。「協同的探究学習」を活用した授業改善により、思考力・判断力・表現力等を培い、「わかる学力」の向上をめざす、本市ならではの教育を実践することで、子どもたちの「生きる力」をしっかりと育んでまいります。また、新年度におきましては、学びの基盤となる「ことばの力」のさらなる育成を図るため、幼児期と児童期の学びの連続性・一貫性を重視した取組を推進してまいります。
いじめの防止対策につきましては、「いじめ防止対策評価検証委員会」の委員の皆さまの助言もいただきながら、教育委員会及び各学校において、「いじめ防止対策改善基本5か年計画」や「いじめ防止対策改善プログラム」に基づく未然防止、早期発見・早期対応に係る様々な施策に取り組んでいるところです。とりわけ、学校環境適応感尺度(アセス)や心の相談アンケート、全児童生徒を対象とした教育相談の実施など、相談体制の充実を図ってまいりました。新年度におきましては、不登校や発達障害など、心理面に関する相談体制の充実を図るため、教育相談センターの心理相談員を増員するとともに、全12中学校区にスクールソーシャルワーカーを拡充して配置し、児童生徒や家庭への迅速かつ効果的な支援を行ってまいります。
学校園の施設整備につきましては、安全で快適な学習環境を子どもたちに提供できるよう、学校園敷地内のブロック塀の安全対策を進めるとともに、空調設備の設置工事については、来年1月に全小学校で、続いて、7月には全中学校での使用開始をめざし、スピード感を持って取り組んでまいります。さらに、老朽化に伴う施設の修繕やトイレの洋式化を着実に進めながらも、今年度実施いたしました市内学校園の老朽化状況調査を踏まえ、「学校園施設長寿命化計画」を策定してまいります。
中学校給食につきましては、今年度、(仮称)日岡山学校給食センターの実施設計を行っており、来年9月からの稼働に向けた建設工事に着手してまいります。また、当初の計画から前倒しし、稼働時期を2021年9月といたしました(仮称)神野台学校給食センターについても、その整備及び運営を行う事業者の選定を行ってまいります。そのほか、学校給食費については、会計の透明性の向上や教職員の事務負担の軽減などを図るため、小学校の学校給食費とあわせて、公会計処理に向けた取組を進めてまいります。
特別支援教育の充実につきましては、とりわけ、加古川養護学校における、医療的ケアが必要な幼児・児童・生徒への通学手段の確保が長年の課題となっており、多数のご要望もいただいているところです。新年度におきましては、通学手段として、看護師が同乗する福祉タクシーの活用を試行的に実施し、保護者の皆さまの負担軽減を図ってまいります。
放課後に小学校の空き教室を利用して、児童が地域の皆さまと様々な文化・スポーツ体験活動を行う「放課後子ども教室(チャレンジクラブ)」につきましては、多くの皆さまのご理解とご協力によって、新年度から、全28小学校において実施することができる見通しとなりました。この取組を生かし、地域の皆さまとともに、児童の健全な育成や安全・安心な居場所づくりを進めてまいります。
また、市内の小中学校の吹奏楽活動や音楽活動を支援するため、ご家庭などで使わなくなった楽器の寄附を募り活用していく取組を、新たに実施してまいります。
学校が抱える課題が、多様化・複雑化する中、地域の皆さまや保護者の皆さまの参画を得た学校運営がますます重要となっています。昨年10月には、加古川中学校が、市内で初めて学校運営協議会制度を導入した学校、いわゆるコミュニティ・スクールとなりました。コミュニティ・スクールでは、地域と一体となった学校づくりを進めることにより、課題の共有や相互支援体制が一層強くなり、地域と学校の活性化が期待できることから、市内の全小中学校に導入することを目標に、各地域との調整を進めてまいります。
文化・芸術活動の振興につきましては、JR加古川駅前の商業施設内に開設している「かこがわ将棋プラザ」の施設面積の拡大を図ることで、これまで以上に市民の皆さまが将棋文化に触れる機会を創出するとともに、子どもたちが将棋に親しみや興味を持つことができるよう取り組んでまいります。また、昨年度に心理学の手法を用いて調査した成果をもとに、「将棋を楽しむことによる健康面の効能」について、多くの皆さまに積極的に啓発することで、「棋士のまち加古川」としての認知度のさらなる向上を図ってまいります。
歴史資源の保存と活用につきましては、今年度末に策定いたします「歴史文化基本構想」に基づき、まちづくりや文化財の関連施策の展開を通じて、郷土への愛着や誇りを育むとともに、歴史文化遺産を核とした地域の魅力の増進や活性化に努めてまいります。
人権文化の確立につきましては、引き続き「人権教育及び人権啓発に関する基本計画」に基づき、すべての市民が日々の暮らしの中で人権を大切にし、尊重し合うまちづくりをめざしてまいります。
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催が来年に迫る中、ブラジル連邦共和国パラリンピック委員会に加え、新たにツバルオリンピック委員会との事前合宿等に関する覚書を締結したところです。新年度におきましては、ホストタウンとして選手団の受入れに全市を挙げて取り組むことはもとより、大会へのさらなる機運醸成に努めてまいります。また、大会後も年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが安全かつ快適にスポーツを楽しめるよう、市内のスポーツ施設の環境整備を行ってまいります。加えて、「ホストタウン交流計画」に基づき、シッティングバレーボールをはじめとしたパラスポーツの体験会や、異文化交流事業の開催などを通して、多様性への理解が深められるよう、取り組んでまいります。
3.【うるおいのある環境の中で暮らせるまちをめざして】
次に、「うるおいのある環境の中で暮らせるまちをめざして」についてです。
進行する温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす中、本市では、環境負荷の低減を図り、持続的な発展を可能とする循環型社会の実現をめざし、ごみの減量化・資源化・再利用化を、市民の皆さまと事業者の皆さま、行政が一体となって推進しています。とりわけ、ごみの減量化につきましては「加古川市民27万人の力で20%ごみ減量を!」をスローガンに、あらゆる手段を尽くして取り組んでおり、今年度からは、分別収集と資源化の徹底に向け、新クリーンセンターにおける事業系廃棄物の搬入時検査の強化をはじめ、家庭系剪定枝(せんていし)の資源化などを開始したところです。本市の取組に対する、市民の皆さまや事業者の皆さまのご理解とご協力により、昨年4月から本年1月までの燃やすごみ処理量は、平成25年度の同期間と比較して22.4%削減することができておりますが、新年度におきましても、引き続き、資源物の分別や食品ロスの削減に向けた啓発を行うとともに、新たな取組を検討するなど、削減量のさらなる向上に努めてまいります。また、高砂市、稲美町、播磨町との連携のもと取り組んでいる広域ごみ処理については、3年後の実施に向けて、本年1月から本格的な建設工事が高砂市において開始されており、引き続き、関係市町と連携して取り組んでまいります。
生活排水処理対策につきましては、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道整備区域を除く地域における、合併処理浄化槽の設置や維持管理に対する補助制度を積極的に啓発してまいります。また、し尿や浄化槽汚泥の受入施設である尾上処理工場については、老朽化に伴う施設の再整備に向けた事前調査を実施してまいります。
4.【にぎわいの中で暮らせるまちをめざして】
次に、「にぎわいの中で暮らせるまちをめざして」についてです。
地方創生を進めるには、交流人口や、市外からの通勤・通学者等、地域に関わりがある人の増加などによる地域経済の活性化が不可欠です。しかしながら、全国的に大都市圏への人口流入、とりわけ東京都への一極集中に歯止めはかからず、むしろ加速する傾向すら見受けられることに加え、中小企業だけでなく、介護、保育など様々な分野における人材不足が深刻化し、大きな課題となっているところです。そのような中、本市では今年度から、若年勤労者の地元就職の促進と中小企業の人材確保を目的に奨学金返還支援制度を開始いたしました。新年度におきましては、さらなる人材の確保と定着を図るとともに、市内への移住・定住をより一層促すため、先ほども申しあげましたように、新たに社会福祉法人等に就職された方についても対象といたします。制度の周知につきましては、大学等を通じた就職活動中の学生へのPRを行うなど、積極的に取り組んでまいります。そのほか、兵庫県と連携し、東京23区に5年以上在住または通勤していた方が、一定の要件を満たす県内の企業に就職し、加古川市に移住した場合に支援金を支給してまいります。
次に、工業の振興につきましては、現在、野口町の「水足戸ヶ池周辺地区まちづくり協議会」が、ため池と周辺の農地を産業団地へと転換し有効活用するための取組を着実に進めておられます。本市といたしましても、新たな産業用地を創出する重要な機会であることから、引き続き、まちづくり協議会の取組を積極的に支援してまいります。さらに、中小企業が直面している労働生産性の向上や人手不足の解消、また、時代に即した経営強化が図られるよう、IoT(Internet of Things)設備の導入に要する初期費用についての補助制度を創設いたします。
農業の振興につきましては、デュラム小麦の「セトデュール」を原材料に開発した「加古川パスタ」の地域ブランド化をさらに促進するため、その作付面積の拡大を引き続き支援してまいります。加えて、「加古川パスタ」を使用した学校給食を実施するなど、地元産食材への理解を深め、地産地消を推進してまいります。
商業の振興につきましては、本年10月には消費税10%への引上げが予定されており、低所得者並びに0歳児から2歳児に係る子育て世帯の、増税に伴う負担を軽減するため、プレミアム付商品券を発行し、本市域における消費の喚起や下支えにも取り組んでまいります。また、老朽化等の課題を抱えております公設地方卸売市場につきましては、場内事業者と合意形成を図りながら市場の再整備に向けた取組を進めてまいります。
観光の振興につきましては、JR加古川駅周辺のにぎわいを創出するとともに、来年度で計画期間が終了する「観光まちづくり戦略」については、市内外の方へのアンケート調査などを活用した効果測定及び評価のもと、新たな戦略の策定に取り組んでまいります。また、来月には、市民の皆さまや事業者の皆さまと開発を進めてまいりました「新ご当地スイーツ」のお披露目を予定しております。「かつめし」や「加古川ギュッとメシ」、「恵幸川(えこがわ)鍋」に続く新たなご当地グルメで、来訪される方を迎え入れ、既存の観光資源と掛けあわせた加古川の楽しみ方を提案してまいります。
魅力あふれる地場産品や観光資源の数々を詰め込んだ、本市のふるさと納税につきましては、記念品を提供いただく市内事業者の皆さまのご協力のもと、全国から応援をいただき、平成29年度の寄附総額が2億円に到達いたしました。新年度は、受付サイトを3サイトに増やし、さらなるPRを行うとともに、より寄附しやすい環境を整え、一人でも多くの方に加古川市に興味を持っていただき、応援していただけるよう取り組んでまいります。
5.【快適に暮らせるまちをめざして】
次に、「快適に暮らせるまちをめざして」についてです。
本格的な人口減少社会を迎える中、計画的な土地利用を進め、持続可能な都市機能を備えた利便性の高い魅力あるまちづくりを進める必要があります。とりわけ、都心として、交通機能はもとより、商業機能の集積など、本市の発展を牽引(けんいん)する重要な拠点であるJR加古川駅周辺のさらなる活性化をめざした、まちづくり構想の策定に取り組んでまいります。集客力の高い都市機能の誘導、既存の商業や居住機能のより一層の充実、そして人が行き交い、とどまり、憩う空間の創出など、様々な機能の在り方を模索し、実現可能なものとすることができるよう、地域の皆さまや事業者の皆さまのご意見も踏まえながら、検討を進めてまいります。
また、公共交通につきましては、これまで社会情勢の変化や地域の移動需要に応じた交通政策に取り組んでまいりましたが、市民の皆さまから寄せられるご意見や市民意識調査の結果を見ましても、十分に満足していただけるものとなっておらず、公共交通の再編は喫緊の課題であると認識しております。一方で、全国的に利用者の減少や運転手の不足による路線バスの廃止・縮小が相次ぐなど、地域の公共交通を取り巻く環境は、さらに厳しさが増しております。そのような中、路線バスや「かこバス」、日常生活の移動をきめ細やかに補完する「かこバスミニ」等の地域公共交通の在り方を総合的な視点に立って見直し、直面する高齢化と人口減少社会に対応した公共交通網の再構築に取り組んでまいります。新年度におきましては、2020年度中の事業展開をめざした「かこバス」ルートの増設・再編に加え、加古川以西における「かこバスミニ」の新たなルートの導入など、通勤・通学等の利便性を高める取組を積極的に進めてまいります。また、住民提案制度によるコミュニティ交通の導入につきましても、引き続き地元町内会と連携し、協議を進めてまいります。さらに、バスの利用を促進し、バス路線を維持するため、2020年度を目途に市内を運行する民営路線バスに上限運賃制度を新設することとし、利用環境の整備に取り組んでまいります。
災害に強い都市基盤の整備につきましては、昨年、局地的豪雨や台風が数多く発生したことを踏まえ、市民の皆さまと事業者の皆さま、行政が相互に連携・協力した総合治水対策を、より一層進めていく必要があると考えております。新年度におきましては、泊川等の河川水位が確認でき、流域住民の主体的な避難を促進できるよう、河川ライブカメラの供用を開始するなど、災害に強いまちづくりを積極的に進めてまいります。
幹線道路の整備につきましては、平野神野線、中津水足線及び神吉中津線の早期完了に向けた取組を、計画的かつ着実に推進してまいります。また、幹線道路によるネットワークの構築を図るため、本市中心部の東西交通の要である国道2号線につきましては、事業主体である兵庫県と密接に連携を図りながら、平野工区の整備及び加古川橋梁(きょうりょう)の架け替えを含め、4車線対面通行化に向けた取組を推進してまいります。また、東播磨道の整備につきましても、県において八幡稲美ランプから国道175号までの北工区について整備が進められているところであり、今後も県との十分な連携を図ってまいります。
一方、播磨臨海地域道路につきましては、現在、国において概略ルート及び構造等が検討されている段階であり、今後、国の動向に対応しながら、周辺の土地利用計画や幹線道路ネットワークの再編などについて検討を進めてまいります。
また、現在、事業調査を進めているJR東加古川駅周辺の連続立体交差事業については、県及び鉄道事業者と緊密に連携し、課題となっている緊急対策踏切の解消をはじめ、周辺道路や土地利用計画を見直すことで、副都心にふさわしい魅力あるまちづくりが進められるよう検討してまいります。
公園の整備につきましては、とりわけ、市民に広く親しまれている日岡山公園の駐車場部分の整備工事を、2020年度にかけて進めてまいります。
さらに、JR日岡駅については、駅舎等に係る基本設計及び実施設計に着手し、地域拠点の一つとしての再整備に取り組んでまいります。
水道事業及び下水道事業につきましては、今後の事業運営の方向性を示す「水道ビジョン2028」及び「下水道ビジョン2028」を、今年度末に策定いたします。新しいビジョンのもと、施設の老朽化対策や耐震化を進め、危機に強く安全で安心な上下水道の構築を図るとともに、将来にわたり良質なサービスを継続して提供するために、アセットマネジメントを取り入れた中長期的な視点での経営を進めてまいります。加えて、水道事業では、大規模地震など災害発生時における応急給水体制の強化を図るため、指定避難所である小中学校の一部に「災害用応急給水栓」の整備を進めてまいります。また、下水道事業では、官民連携手法を取り入れ進めている志方地区の下水道整備事業を引き続き実施するなど、公共下水道区域内の未普及エリアの早期解消に取り組んでまいります。
6.【まちづくりの進め方】
最後に、まちづくりの進め方についてです。
総合計画では、まちづくりの進め方として、「市民と行政との協働」、「効果的・効率的なまちづくり」及び「広域的な都市間連携」の3項目を掲げております。
冒頭にも申しあげましたが、厳しい財政状況の中で各課題を乗り越えていくためには、市民の皆さまとの信頼関係に基づく協働が不可欠です。その実現に向けて、本市の魅力や各施策、抱えている課題等をより多くの方々に知っていただくためにも、これまで以上の情報発信が必要であると考えております。
新年度におきましては、情報発信の所管を秘書室から企画部に移し、より包括的かつ積極的な広報広聴活動やシティプロモーションを戦略的に推進してまいります。
また、市民の皆さまとの協働のまちづくりを具体的に推進する施策として、兵庫大学で構築された「熟議」のスキームに加わる形で、高校生や大学生を含む市民の皆さまによる市民会議を開催いたします。市民会議では、ワークショップを通じて、本市のまちづくりに対する提言をとりまとめていただくことを考えております。さらに、地域の課題解決に向けて、市民活動団体が行っている様々な取組を、広く市民の皆さまに知っていただき、新たな活動意欲の喚起、ひいては地域の活性化につなげられるよう、活動内容を掲載した事例集を市民活動団体と協力して作成してまいります。一方、「協働のまちづくり推進事業補助金」につきましては、補助制度の一つであるテーマ設定型を、「結婚から子育てまで“ぐうっと”応援するまち」として、出会い・結婚・出産・子育てを応援する事業に特化いたします。また、スタート応援型に学生枠を採り入れ、若い世代がまちづくりに関わる仕組みを構築し、地域課題の解決に参画することで、ふるさと意識の醸成を図ってまいります。
次に、効果的・効率的に進めるまちづくりといたしましては、地域課題の解決を図るため、情報通信技術(ICT)や市内部が保有するデータを活用するなど、スマートシティをめざした取組を推進してまいります。とりわけ、データに基づく政策立案、いわゆるEBPM(Evidence Based Policy Making)の推進をめざし、市民意識調査や行政評価等のさらなる活用手法を検討してまいります。さらに、多くのデータ入力業務等にRPA(Robotic Process Automation)を導入することで、庁内における事務の効率化を図ってまいります。
そして、公共施設等の今後の管理計画につきましては、次世代に負担を残さず、将来にわたり、より質の高い行政サービスを提供するためにも、公共施設等の再編に大局的な観点から取り組むことが必要であると考えております。そのため、この度、市役所周辺施設及びスポーツ施設の方向性を示す再編計画を策定いたしました。今後は2020年度までに、個別施設の具体的な対応を定める「個別施設計画」を策定すべく、引き続き、施設類型別再編計画の策定を進めてまいります。なお、加古川東市民病院跡地の活用については、本年中には解体工事を終え、新たな複合施設の整備に取り組んでまいります。
広域的な都市間連携につきましては、2022年度から稼働予定の広域ごみ処理施設の建設や、休日昼間及び夜間の一次救急医療を提供する拠点施設の整備に向け、必要な調整を進めてまいります。そのほか、広く東播磨地域、さらには播磨地域全体としての効果的なPRを行うことができるよう、東播臨海広域行政協議会や播磨圏域連携中枢都市圏を構成する市町との連携を深めてまいります。
おわりに
以上、平成31年度の市政運営の方針と基本的な考え方を申し述べてまいりました。本年5月には、平成という一つの時代が節目を迎え、新たな時代が幕を明けます。また、来年6月には、本市も市制70周年という節目を迎えます。そのような中、私たちを取り巻く環境は、めまぐるしく変化を続けていますが、市民の皆さまとスクラムを組みながら、一つ一つの課題に果敢にチャレンジを続けてまいります。
「一人一人が生活の中に幸せを実感できる、郷土愛あふれるまちづくり」をめざして、全力で取り組んでまいりますので、議員各位並びに市民の皆さまの一層のご理解、ご協力をお願い申しあげまして、平成31年度の施政方針といたします。
(注釈)当日の演説と表現その他に若干の違いがあることをご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:企画広報課(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9113
ファックス番号:079-424-1370
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
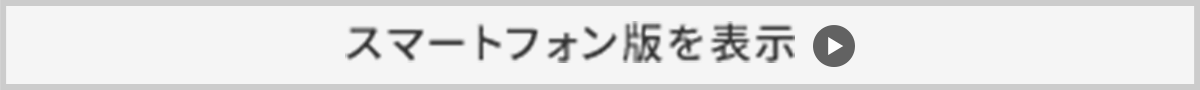








更新日:2020年02月26日