ヒトパピローマウイルス(HPV/子宮頸がん)ワクチンについて
子宮頸がんのほとんどが、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染で生じるとされています。定期接種で受けられるHPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすい高リスク型の16型と18型を含む複数のヒトパピローマウイルスの感染を防ぐことができます。
HPVワクチンについては、厚生労働省の通知により、平成25年6月14日以降、市から接種券を一斉送付するなどの積極的勧奨は見合わせていたところですが、国の審議会において、最新の知見をふまえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、令和3年11月26日付の厚生労働省通知により、積極的接種勧奨が再開されることとなりました。
詳しくは厚生労働省ホームページの「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~」をご覧ください。
HPVワクチン定期接種について
対象
小学校6年から高校1年相当までの女子
ワクチンの効果
サーバリックス(2価ワクチン)およびガーダシル(4価ワクチン)は、子宮頸がんをおこしやすい種類(型)であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。
そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
シルガード9(9価ワクチン)は、 HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
HPVワクチンの接種により、感染予防効果を示す抗体は少なくとも12年維持される可能性があることが、これまでの研究でわかっています。
また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。HPVワクチンの接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かる、と試算されています。
接種間隔
ワクチンの種類によって接種間隔が異なります。最初に受けたワクチンと同じ種類を接種することが原則ですが、2価または4価を接種した場合でも、医師と相談のうえ、シルガード9に変更することも可能です。
以下の(1)と(2)いずれかの方法で接種することができます。
(1)3回接種
| ワクチン名 | サーバリックス(2価) |
ガーダシル(4価) シルガード9(9価) |
|
接種間隔 |
2回目:1回目から1か月以上間隔をおく 3回目:1回目から6か月以上間隔をおく |
2回目:1回目から2か月以上間隔をおく 3回目:1回目から6か月以上間隔をおく |
|
上記の間隔で 接種できない場合 |
2回目:1回目から1か月以上間隔をおく 3回目:1回目から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上の間隔をおく |
2回目:1回目から1か月以上間隔をおく 3回目:2回目から3か月以上の間隔をおく |
(2)2回接種
|
ワクチン名 |
シルガード9(9価) |
| 対象 |
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 |
| 接種間隔 | 6か月以上の間隔をおいて2回接種する |
|
上記の間隔で 接種できない場合 |
5か月以上の間隔をおいて2回接種する ※5か月未満の場合、3回目の接種を実施することになります |
接種にあたって
※市外に転出後は、加古川市の予防接種券は使用できません。転入届(新住所地の市町村へ提出する届出)に記入する「異動日」の前日までが、加古川市にお住まいであったと記録されます。異動日以降は使用できませんので、ご注意ください。
【HPV】2025予防接種等_協力医療機関一覧表 (PDFファイル: 465.8KB)
上記の予防接種協力医療機関で予約し、接種を受けてください。
ワクチン接種後は注射による痛みや心因性の反応等による失神などがあらわれることがあります。接種後30分は、接種を受けた医療機関で、座って様子を見ることになります。
満16歳未満の方の接種には、原則は保護者が同伴してください。ただし、接種を受ける方が13歳以上の場合は、「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票(保護者が同伴しない場合)」を熟読の上、予診票に、保護者が同意する旨の自署をすることで、保護者の同伴なしで予防接種をうけることができます。
[持ち物]
・予防接種券
・予診票(保護者の署名が必要)
・母子健康手帳
・健康保険証
ワクチンのリスク
HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。
| 発生頻度 | サーバリックス (2価ワクチン) |
ガーダシル (4価ワクチン) |
シルガード9 (9価ワクチン) |
| 50%以上 | 疼痛、発赤、腫脹、疲労 | 疼痛 | 疼痛 |
| 10~50%未満 | 掻痒(かゆみ)、 腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など |
紅斑、腫脹 | 腫脹、紅斑、頭痛 |
| 1~10%未満 | じんましん、めまい、発熱など | 頭痛、そう痒感、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血など |
| 1%未満 | 知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感など | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結など |
| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛など |
まれですが、重い症状が起こることがあります。
| 病気の名前 | 主な症状 |
| アナフィラキシー | 呼吸困難やじんましんなど |
| ギラン・バレー症候群 | 手足の力が入りにくいなど |
| 急性散在性脳脊髄炎 | 頭痛・嘔吐・意識低下など |
因果関係があるかどうかわからないものや、接種後短期間で回復した症状もふくめて、HPVワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人あたり、サーバリックスまたはガーダシルでは約9人、シルガード9では約3人です。このうち、報告した医師や企業が重篤と判断した人は、接種1万人あたり、サーバリックスまたはガーダシルでは約5人、シルガード9では約3人です。
〈出典〉
厚生労働省作成リーフレット
HPVワクチンについて知ってください~あなたと関係のある“がん”があります~(詳細版) (PDFファイル: 7.2MB)
上記と併せて、下記のリーフレットもお読みいただき、ワクチンの効果とリスクについてご確認ください。
シルガード9について(定期) (PDFファイル: 597.6KB)
子宮頸がんワクチンリーフレット(概要版) (PDFファイル: 5.9MB)
HPVワクチンキャッチアップの経過措置(接種期間の延長)について
令和6年11月29日に厚生労働省より、キャッチアップ接種経過措置(接種期間の延長)の方針が発表されました。
最新の情報については、こちらをご参照ください。
経過措置の対象者
キャッチアップ対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
令和6年度高校1年生相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
経過措置の期間
キャッチアップ接種期間及び定期接種期間終了後、1年間
(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
HPVワクチンキャッチアップ接種については、こちらをご確認ください。
注意事項
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間内に1回も接種を受けていない方
⇒経過措置(接種期間延長)の対象外です
- 公費で3回接種の完了を希望される方
⇒令和7年3月31日までに1回以上の接種をお受けください
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-454-4188
問合せメールはこちら
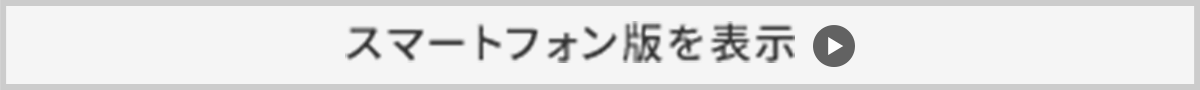








更新日:2024年07月01日