家屋の評価について
家屋の固定資産税・都市計画税の算出方法
家屋の固定資産税は、課税標準額×税率により算出します。
原則として評価額がそのまま課税標準額になります。
| 固定資産税 | 課税標準額×1.4パーセント |
|---|---|
| 都市計画税(市街化区域のみ) | 課税標準額×0.3パーセント |
年税額は、「固定資産税額」+「都市計画税額」です。
家屋の評価額の算出方法については、下記の説明を参照してください。
1.固定資産税における家屋の評価
固定資産税における家屋の評価は、「再建築価格」を基準として評価する方法によって求めることとされています。
「再建築価格」とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価する時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費のことです。
また、この「再建築価格」に、家屋の建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価などを考慮し、家屋の評価額を算出します。
1-1.課税対象となる家屋
固定資産税の課税対象となる家屋の要件は、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものとされており、具体的には以下の3つです。
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| 外気分断性 | 屋根や周壁などにより、外気を分断しうる構造を備えているか。 |
| 土地への定着性 | 基礎工事などにより、土地から容易に移動できず、永続的に利用できるか。 |
| 用途性 | 建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵など)を有し、その目的のために利用できる一定の空間があるか。 |
よくある質問を紹介します
| ケース | 課税対象となるかどうか |
|---|---|
| 庭に設置するような物置(イナバ物置など) |
コンクリートブロックの上に乗せているだけのような置き方であれば、課税対象になりません。 コンクリートブロック基礎や布基礎などの基礎工事を施し、土地に定着していると、課税対象になります。 |
| カーポート | 屋根だけのカーポートであれば、課税対象になりません。 |
| ウッドデッキ | 屋根や周壁がなければ、課税対象になりません。 |
| サンルーム(ガラスなどで囲まれた空間) | 課税対象になります。 |
| 門や塀 | 課税対象になりません。 |
2.新築家屋の評価
2-1.家屋調査
|
家屋調査の実施にあたっては、事前に文書で案内します。ご都合が悪い場合などは、日程調整など個別に対応させていただきますので、資産税課家屋係までお問合せください。
家屋調査の所要時間は、家屋の構造や規模により異なります。一般的な住宅であれば30分以内で完了しますが、大規模な家屋であれば60分以上要する場合もあります。
よくある質問を紹介します
【質問】どのような建築設備が評価対象になるのか
一般的な住宅に採用される建築設備であれば、電気・ガス・給水給湯・排水設備、ドアホン、給湯器、便器、洗面器(手洗い器など)、洗面化粧台、ユニットバス、浴室換気乾燥機、システムキッチン、床暖房、空調設備(全館空調や、ビルトインエアコンなど)、換気設備などがあります。なお、他にも評価対象となるものがありますので、詳しくは資産税課家屋係へお問い合わせください。
壁掛けタイプのルームエアコンなど、家屋と一体になっていないものは評価対象になりません。
【質問】屋根裏や小屋裏は、固定資産税がかからないのか
家屋の床面積には算入されませんが、評価額の算出にあたっては、評点数の付設対象となりますので、「固定資産税がかからない」というのは誤りです。なお、家屋の床面積に算入されないのは、屋根裏や小屋裏の室内高が1.5メートル未満であるためです。
2-2.新築家屋の評価額の算出
家屋評価は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行います。
具体的には、家屋調査の結果を元にして、屋根・基礎・外壁・柱・壁体・内壁・天井・床・建築設備などの「部分別」ごとに、「固定資産評価基準」に定められた資材や建築設備の「評点数」を付設していきます。
「評点数」は、資材や建築設備によって異なります。たとえば、屋根の場合、金属板鋼板(ガルバリウム鋼板など)、繊維強化セメント板(カラーベストなど)、かわら、建材型ソーラーパネルの順に、評点数が高くなります。
そのため、家屋の面積が同じであったとしても、使用資材や建築設備などが異なれば、評価額は同じにはなりません。
また、評価額は、家屋の購入価格などの金額と連動して決まるものではありません。たとえば、購入価格が2000万円だったから、評価額はその7割の1400万円というのは誤りです。
新築家屋の評価額の算出式
「再建築費評点数」×「経年減点補正率」×「評点一点当たりの価格」により算出します。
「再建築費評点数」
「部分別」ごとに積算した「評点数」をすべて合計し、床面積で除して「1平方メートル当たり再建築費評点数」を算出し、100点未満の端数を切り捨てます。そこに床面積を乗じて、「再建築費評点数」を算出します。
「経年減点補正率」
家屋に通常の維持管理を行うものとした場合において、その経過年数に応じて通常生じる減価を定めたものです。新築家屋の場合、1年目の経年減点補正率を適用します。
経年減点補正率は、構造や用途により異なります。専用住宅の場合、1年目の経年減点補正率は0.8です。
「評点一点当たりの価格」
木造家屋は1.05円、非木造家屋は1.10円です。
3.在来分家屋(すでにある家屋)の評価
3-1.評価替え
家屋の評価額は、3年ごとに適正な価格に見直す制度になっています。これを「評価替え」といいます。
直近で「評価替え」を実施したのは令和6年度でした。このとき見直された評価額は、次回の「評価替え」まで据え置かれます。なお、次回の「評価替え」は令和9年度です。
在来分家屋の評価額の算出式
「前年度における再建築費評点数」×「再建築費評点補正率」×「経年減点補正率」×「評点一点当たりの価格」により算出します。
なお、算出した評価額が前年度の評価額を上回る場合、前年度の評価額が据え置かれます。そのため、増築などが無い限り、家屋の固定資産税額が、評価替えによって上がることはありません。
「再建築費評点補正率」
前回の評価替えから今回の評価替えにおける3年間の、建築にかかる物価の変動を反映した率のことです。
「経年減点補正率」
家屋に通常の維持管理を行うものとした場合において、その経過年数に応じて通常生じる減価を定めたものです。
「評点一点当たりの価格」
木造家屋は1.05円、非木造家屋は1.10円です。
よくある質問を紹介します
【質問】家屋が古くなっているのに、評価額が下がらないのはなぜか
考えられる理由が2点あります。
「再建築費評点補正率」が上昇している
物価上昇局面においては、「再建築費評点補正率」が上昇します。この上昇幅が「経年減点補正率」による減価率の幅を上回っている場合、家屋の評価額が上がります。ただし、この場合は、前年度の評価額のまま据え置きとなりますので、同額のままとなり下がりません。
「経年減点補正率」が下限値に到達している
「経年減点補正率」は、減価率の下限値は2割として設定されています。そのため、どれだけ建築年次が古くても、評価額は0円にはなりません。
また、経年減点補正率が下限値に到達するまでの期間は、構造や用途により異なります。たとえば、一般的な木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート造のマンションは60年かかります。
このため、一般的な木造専用住宅の場合、築25年以上経過すると経年減点補正率による減価がなくなるため、評価額は下がらなくなります。
参考:評価額が下がらない理由 (PDFファイル: 29.0KB)
4.評価に関する基準等について
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
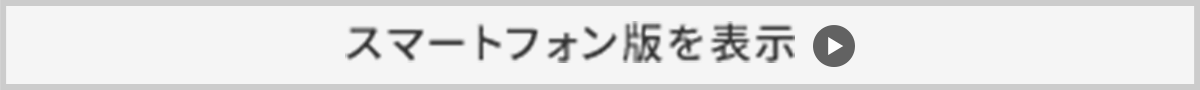








更新日:2025年04月01日