支援プログラム
【事業所における基本情報】
- 事業所名:加古川市立こども療育センター 児童発達支援「 かなで 」
- 作成年月日:2025 年 2 月7 日
- 事業所理念:こどものすこやかな成長をうながし こども一人一人がそれぞれの幸せをつかむ力をはぐくむ。こども一人一人のそれぞれの幸せを支える社会をめざす。
- 支援方針:乳幼児に必要な経験を積み重ねることで、こどもの育ちを支援するとともに、保護者も一緒に集団療育に参加し、こどもの特性や関わり方について 学ぶことで良好な親子関係を形成します。また、診療所スタッフと連携のもと、環境・日課・遊びの工夫や関わり方を検討し、保護者とともに確認することにより、家庭生活が安定し、安心して子育てができるように関わります。
- 営業時間:9:30~14:00 肢体グループ(月・水・木) 発達グループ(火・金)ただし、国民の祝日、 8 月 お盆の 1 週間、年末年始( 12 月 29 日~ 1 月 3 日)春休み( 3 月 20 日頃~ 4 月 5 日頃)を除く
- 送迎実施の有無:無し
【支援内容】
こども療育センターの児童発達支援「かなで 」では、次の 3 つの支援を行います。
●発達支援(本人支援・移行支援) ● 家族支援 ● 地域支援
7.本人支援
- 「健康・生活」「運動・感覚」 「認知・行動」 「言語・コミュニケーション」 「人間関係・社会性」の 5 領域に対する支援を行います。
- 5 領域一つ一つの項目をスモールステップで達成していく事で成功体験を積み重ねられるよう支援していきます。
- お子さん一人一人にあった個別支援計画書を作成する際には、5 領域の項目を明記して説明させていただきます。
- 5 領域についての支援内容は、下記の表で確認していただけます。
支援プログラム(本人支援の内容と5領域の関連性) (PDFファイル: 625.1KB)
本人支援の内容と5領域の関連性
a 健康・生活
1.健康状態の維持・改善
【共通】
- 登園時に、体温・体調チェックをする。
- こどもの平常とは異なる状態を速やかに見つけ、対応できるように常日頃から観察する。
- 意思表出の難しいこどもの特性や状態に配慮し、小さなサインに気づき、異変があればセンターに併設する診療所の看護師や医師が対応する。
- 定期的に内科健診、耳鼻科診、歯科健診を行い、健康維持に努める。
- 管理栄養士が栄養バランスを考えた給食を提供する。
- こどもの口腔機能に応じて、初期食(ペースト食)や中期食、後期食、幼児食に加え、経管栄養の児にはミキサー食を提供する。
2.生活のリズムや生活習慣の形成
【共通】
- 気温・気候に合わせて衣服の調節、室温の調整をする。
- 生活習慣を身につけられるよう、更衣の時に必要な段差や姿勢保持、手指の運動機能に応じた椅子や自助具を準備する。
- こどもの睡眠リズムに合わせ、必要な時は睡眠時間を確保する。
- 時間を決めて便座に座ったり、オムツ交換をする。
3.基本的生活スキルの習得
【共通】
- 登園時に所持品の始末ができるよう、タオル掛けや水筒かご、カバンを置く棚を設置し、絵カードやマークでする内容や場所を伝えられるようにする。
- 更衣の段階や食具の使用状況を保護者と確認し、介助する場所やタイミング、姿勢や自助具の提案をするなど、適切な時期に適切な支援をすることで日常生活動作の向上を図る。
- 障害の特性に応じて、見通しをもてるようカードで時間を伝えたり、集中できるよう空間を仕切ったりすることで、こどもが安心できるようにする。
b 運動・感覚
1.姿勢と運動・動作の向上
【共通】
- 生活の基本的な動作(靴の着脱、手洗い・うがい、排泄、食事等)を身につけられるように介助したり、見本を見せる。
- 遊びの中でも基本的動作を取り入れ、(手づかみ→感触遊び→手遊び等)経験を積めるようにする。
- 遊戯室や保育室で、巧技台、トランポリン、一本橋、律動(歩く・走る・ジャンプ・片足立ち・ギャロップ・ストップ等)をすることで、体幹が鍛えられるようにする。
- 戸外では、ブランコの揺れやウッドジムの上り下りの経験を積めるようにする。
【肢体】
- ずりばいや四つ這い姿勢における上肢・下肢を使う遊びをしたり、足底をつけて踏ん張る・膝を使う動きを遊びに取り入れる。
2.姿勢と運動・動作の補助的手段の活用
【共通】
- トイレでは、オマルや補助便座に加え、必要であれば、足台を使用することで力が入りやすいようにする。
- 段差に座って、ズボンや靴の着脱ができるようにする。
- 給食時に一人ですくうことができるようにUD(ユニバーサルデザイン)の食器を使用する。
【肢体】
- 姿勢保持や上肢の操作がしやすいよう、個人に合った器具(立位台や座位保持椅子)、保育椅子、机、だてじめ、クッション等を使用したり、装具を身につけたりする。
- スプーンやフォークに布を巻いて持ち手を太くしたり、筆を手に固定できるような補助具を用いるなど自分で持てるように工夫する。
【発達】
- 足裏に刺激が入るマットを使用することで集中して座れるようにする。
3.保有する感覚の総合的な活用
【共通】
- 戸外ではブランコや滑り台等の大型遊具、砂場遊び、季節ならではの遊び(プールや芋掘り)、室内では絵の具、粘土、のり、スライム等の感触遊びなどを通して、いろいろな感覚を味わい、楽しい経験を積む。
- バランスボールやトランポリン、オーシャンスイング、トンネル等を使用する遊びを通して、バランス感覚やボディイメージを養い、身体の使い方を身につけられるように支援する。その遊びの中でスピードや揺れの強弱等も感じられるようにする。
- 感覚の過敏や鈍麻に対して、ボリュームや明暗の調整、間接的に触れる等の配慮をする。
- 眼鏡や補聴器を使用する時は、集中している環境の中で無理なく着用できるようにする。
c 認知・行動
1.認知の発達と行動の習得
【共通】
- 楽器や玩具をわかりやすいように見せる、音を鳴らして知らせる、実際に触って確かめることができるようにする。
- また、揺れやスピードを感じることができるような刺激を実際に受けることで、様々な感覚を味わう経験を増やしていく。
- 活動の参加に難しさがある時は、「活動の場にいる→興味をもって見る→少し参加してみる」というようなスモールステップで支援し、状況を理解できるようにする。
- 「活動の流れ」がわかるように、イラストや写真をボードに貼ったり、それを保育者が言葉やジェスチャーで伝えたりすることで、見て理解し、自ら行動できるよう支援する。
(例)体操の動きを伝える時は、身体を一緒に動かしたり、前で見本を見せたりする。
- こだわりについては、それに付き合いながら、やめてほしいことであればその場面に遭遇させないようにしたり、見通しを持たせたりすることで対処していく。
- 偏食については、なぜ食べられないのか理由を考えたうえで、安心して食べることができるよう、時間や声のかけ方、調理の仕方を工夫する。
2.空間・時間・数等の概念形成の習得
【共通】
- 遊びや生活の中で概念形成につながる働きかけをする。
(例)
- 待つ時やトイレの便座に座る時に10まで数えて終わりを伝える。
- ボードに番号をつけて活動の順を伝える。
- こどもにわかりやすい色を言葉と共に伝えたり、同色の箱に入れたりすることで一致できるようにする。
- 時計やタイムタイマーで時間を知らせる。
- ボールの大小を見て比べたり、穴に入れることができる玩具を使用する。
- 保育室の一部分にシートを敷いたり、衝立で空間を分けることで、活動する場所を知らせる。
3.対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得
【共通】
- 活動内容を見たり聞いたりして捉えられるよう、こどもが注目、認識できる伝え方をする。
- 欲しいものがある時は、保育者に写真カードを渡したり、指さしをするなど、伝えるともらえる成功体験を積み重ね、認知面の発達、行動につなげる力を伸ばす。
- 巧技台遊びをする時、矢印や足型を使って簡単な動きの見本を見せ、一緒に動くことで流れや待つことを理解して行動できるように支援する。
- 正しい表出が出来た時は称賛し、誤った表出に対しては、正しい行動を示して一緒にやってみることで、成功体験を積み重ねられるよう支援する。
d 言語・コミュニケーション
1.言語の形成と活用
【共通】
- 手遊び歌やことば遊び歌などを通して、言葉の真似をすることで発声する経験をしていく。
- 保育者が名称や事象を音や言葉にして伝えることで、一致できるようにする。
- 相手の気持ち(「嬉しい」「楽しい」「やめて」「痛い」等)を理解するツールとして保育者が動きや絵カードで示し、併せて言葉でも伝える。
- こどもなりの表出で意思が伝えられた時はしっかりと受け止め、保育者がその思いを言葉にして返す。
- 生活や遊びの中で具体的な体験と言葉を結び付けていく事で、言語の理解と表出が出来るよう支援する。
2.言語の受容及び表出
【共通】
- 自ら発信したい、伝えたいと思えるように、保育者と信頼関係を築く。
- 保育者の思いが伝わるように、わかりやすい言葉で端的に伝えるようにする。
- こどもが楽しい気持ちや嫌な気持ちを行動で示しているときに、それを受け止めながら保育者が具体的な言葉にし、こどもが反復することで言葉での表出につなげる。
(例)
- 玩具が欲しくて友だちの物を取った時は、「ちょうだい」と伝えられるように保育者が言葉を添える。
3.コミュニケーションの基礎的能力の向上と手段の選択と活用
【共通】
- コミュニケーションの取り方を把握するために、こどもを観察する。(表情、身振り、声色など)
- 言語だけでなく、ジェスチャーや指差し、絵カード、保育者の表情や声色で今の状況を伝えていく。
- 発語が難しい段階のこどもに対して、小さな動きや反応を見逃さず意味づける。また、コミュニケーション手段として、指差しやサイン、表情、手話、音声、スイッチやタブレットを活用する。
- 発語があるこどもには、正しい言葉でのやりとりを繰り返し伝えていく事で、自らの表出につなげていく。
e 人間関係・社会性
1.他者との関わり(人間関係)の形成
【共通】
- 親子通園の特徴を生かし、まずは親子で一緒に生活・遊びを経験することでアタッチメント(愛着)を形成するための支援を行う。
(例) 親子で身の回りのことをしたり、スキンシップをしたり、できたことを認めてもらったりする機会がもてるようにする。
- 保護者との分離の時間をつくり、他者と一緒に活動する楽しさを経験したり、伝えようとする意欲につなげる。
- 遊びを通じて人の動きを見ること、模倣することにより、社会性や対人関係の芽生えを支援する。注目できるような支援として、効果音や指さしを見て他者に気付けるようにする。
- 一人遊び→見立て遊び→ごっこ遊び等を通して、他児と関われるように保育者が介入し、社会性が育つよう支援する。
2.自己の理解と行動の調整
【共通】
- こどもの特性を保護者と共に理解し、声をかけるタイミングや切り替えられる方法を探り、安心して過ごせるように支援する。
(例)
- 好きな玩具で遊べない時に代わりの物を提案する。
- 気持ちを落ち着けるグッズや場所を提供する。
- 見通しをもてるように事前に次の活動を知らせる。
3.仲間づくりと集団への参加
【共通】
- 介助や仲立ちをすることで、こども同士が手を繋いだり、触れ合ったりできるようにする。
- 友だちを意識できるように、あえて場所や物を共有する場を作る。
- 大人が一緒に遊びに参加する、代弁する、促す、見守る等、一人一人の発達段階に応じた関わり方を工夫する。
- 必要なルール(待つ、順番を守る、交代する)が理解できるように、視覚支援で分かりやすく伝え、成功体験を積み重ねる。
8.家族支援(親子通園)
- 個別面談(年1~2回、必要に応じて)
- 参観日(肢体グループ 6月、11月/発達グループ 11月)
- 保護者会
- グループワーク(勉強会、座談会)
- 夏季登園中のきょうだい支援
9.移行支援
- 就園、就学についての意向の聞き取り、必要な情報を提供します。
- 他の事業所、保育園、幼稚園、こども園、小学校への見学、相談の案内をしています。
- サポートファイルの紹介やロールプレイを実施し、就園先との面談に向けた準備をします。
- 就園、就学に向けて申し送り書を作成するとともに、必要に応じて訪問や会議を行い、スムーズに移行できるよう支援します。
10.地域支援・地域連携の内容
- 近隣のこども園との交流保育(肢体グループのみ)を実施しています。
- こども療育センター児童発達支援かなでに通所しながら、就園しているお子さんについては、通園先と訪問や電話で情報交換を行い、支援の方向性を共有していきます。
11.職員の質の向上に資する取り組み
- 発達支援や肢体不自由児の介助等の勉強会、ケース検討会、個別支援計画連携会議を定期的に開催し、職員の資質向上を図っています。
- 近畿肢体不自由児療育施設連絡協議会の部会への参加、基礎研修やスキルアップ研修、発達支援についての研修、また各自興味ある分野の研修に参加し、報告会で発表するなどして研鑽に取り組んでいます。
12.主な行事
- 入園式
- 卒園式
- 保育参観
- 運動会
- 夏まつり
- 夏季登園(きょうだい登園)
- バス遠足
- ハロウィン
- クリスマス会 等
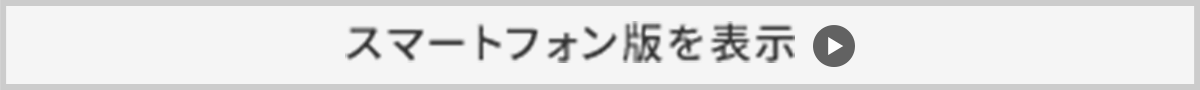








更新日:2025年02月07日