2007年10月号(特集・ミニ特集・タウンタウンなど)
特集
みんなでつくろう!魅力あるまち 地域のみなさんが主役のまちづくり
みなさんは自分の住んでいるまちにどのようなイメージを持っていますか。「緑豊かなゆとりある住宅地にしたい」「道路を広くして安心して歩けるまちにしたい」など、こんなまちにしたいと思ったことはありませんか。このような思いや地域の個性にあったまちづくりを、地域のみなさんが主体となって進めることができる制度として「地区計画」と「景観まちづくり」があります。今月の特集では、この二つの制度について紹介します。
「地区計画」で地域の実情に合ったルールを作ることができます
戸建て住宅地の中に高層のマンションが建設された、道路が狭くて通りにくい、地域に緑が少ないといったことはありませんか。市では市全体を住居地域、商業地域、工業地域などに分けて土地の使い方や建物の建て方など、大まかなルールを定めていますが、個々の地区の実情に合っていない場合もあります。そこで、そういった地区のみなさんが、自分たちできめ細かいルールを決めてまちづくりをしていくことができる「地区計画」制度を設けています。
左の図をご覧ください。地区計画では、道路の配置や建物の建て方、植栽などのルールを決めることにより、地域のみなさんが望む良好な街並みや景観をつくることができます。
すでに市内の五つの地区が、地域の実情に合ったルールを地区計画で定めて、まちづくりに取り組んでいます。まちの現状や目指す方向は地区によってさまざまですので、良いところを守ったり、問題点を改善したりする方法も地区ごとに違ってきます。次のページでは、実際にどのような思いや目標を持って取り組んでいるのかを紹介します。
現在の状況
農地の中に少しずつ建物が建ち始めています
放っておくと…
狭い道路が解消されず、建物の高さや種類もまちまちで、無秩序なまちになっています
地区計画を決めると…
狭い道路が広がり、整然とした街並みになります
昔からある集落を残しつつ便利でにぎわいのあるまちを
平岡町中野地区
中野地区は、昔からある集落のため、農地と住宅が混在しています。また、国道250号に面しているので、沿道には工場や店舗が建っています。地区内は道路の幅が狭く危ないところが多く、また、未利用の農地が増えてきています。そこで、緑豊かで住みやすく、活気あるまちづくりを目標に地区計画をつくりました。地区計画で定められたルールの一部を紹介します。
- 将来、狭い道路を広げられるように、建物の新築・改築などをするときは、道路となる部分を空けて建物を建てる
- 便利でにぎわいのあるまちになるように、地区内を住宅地区と沿道地区に分け、沿道地区には決められた種類の店舗が建てられるようにする
中野地域地区計画協議会会長 藤原 寅雄さん
役員による勉強会や住民への説明会を何度も行い、地区に住むみんなでこれからの中野地区について考えました。地区内の良いところや問題点を見つけるために、みんなで歩き、気づいたことを地図にまとめた「まち歩きウォッチング気づきマップ」は、まちづくりのルールを作る土台になりましたね。
何もしなければ新しい人は誰も住んでくれなくなる、道路が狭いと、もしものときに消防車や救急車が家の前まで来ることができない、そういった問題を解決できればと考えて取り組んでいます。今はまだ狭い道路も私たちの子や孫の代には広い道路になり、住みやすいまちになる…そう思っています。個人単位ではマイナスになる部分もありますが、まち全体が安全で快適になることは、将来はみんなのプラスになるという気持ちで理解しあい協力しあってまちづくりを進めています。
副都心の新しい顔は統一感のある美しい街並み
東加古川駅北第1地区
東加古川駅北第1地区内にあるつつじ野地区は、JR東加古川駅北側の道路や広場の整備にあわせて、民間事業者が開発しました。駅や学校、店舗、医療施設も近く、利便性の高い地区です。地区計画を活用することで、開発や建築などに一定の制限をし、加古川市の副都心の新しい顔として、まとまりのあるまちづくりを目標にしています。地区計画で定められたルールの一部を紹介します。
- まとまりのある街並みにするために、外壁や屋根を落ち着いた色にすることや、屋根を統一した形にするなど、建物の外観に一定の制限を設ける
- 開放的で緑豊かな街並みとなるよう、塀や門柱の高さを制限し、家の敷地の道路際にはなるべく花・芝生・植木などを植えるようにする
- 居住・生活することを中心としたまちとし、店舗を建てられる場所を特定したり、風俗施設の建築を禁止したりする
平岡町 村尾 友子さん
平岡町 立岩 由紀さん
家を建てるにあたり、屋根や外壁の選択肢は限られていましたが、そのおかげで統一感のある街並みや住環境がいつまでも変わることがないので安心して住めますね。みなさん、芝生を植えたり、花壇を作ったり、庭やデッキをそれぞれ工夫していて、一軒一軒個性があるんですよ。駅から近く、スーパーや医療機関もあるので、お年寄りから子どもまで便利で安心です。これからも、住んでいる人たちみんなで、安全で快適な街並みを守って暮らしていきたいですね。
ほかにも、加古川駅北地区、神野地区、坂元・野口地区が地区計画を定め、それぞれ地域にあったまちづくりのルールを決めています。
地域のみなさんが中心となり次のような進め方でまちづくりのルールを作っていきます
1. 困っていること・やりたいことを見つけよう
「周辺の環境を良くしたい」「道路や建物の整備のルールを作りたい」など、自分たちが住んでいる地域について何とかしたいと思ったら、まずは、市に相談してください。そこから、みなさんのまちづくりがスタートします。
2. 協議会を作って、話し合おう
地域のみなさんで、まちづくりを共に考える「まちづくり協議会」を立ち上げましょう。まちづくりのルールなどは、協議会を中心にみなさんで決めていきます。みんなでまちを歩いてみたり、勉強会やアンケート調査を行ったりして、まちの好きな点や問題点などを調べ、まちの課題を見つけましょう。市は、必要に応じて道路や建物の状況を調査したり、専門のまちづくりアドバイザーを派遣したりして、みなさんの活動を支援します。
3. まちづくりの目標を決め、住民案を作ろう
「こんなまちにしたい」という地区の大きな目標を決めます。そして、その目標を実現するための具体的なルールを作ります。建物を建てるときや、新しく道路を作るときのルールなど、地区のみなさんで話し合ってまちづくりのプラン(住民案)を作り上げてください。もちろん、市もみなさんが考えたプランが実現可能かどうか、プランを実現するために何が必要かなどを一緒に考えていきます。
【ルールの一例】
- 屋根などの形状を決めることができます
- 外構の材質や形状を決めることができます
- 建物の高さの制限を決めることができます
- 屋根や外壁の色彩を決めることができます
4. 地区計画の決定手続きをしよう
みなさんが作った地区計画のプランを市へ提出します。市は、法律や市の条例に基づき、地区計画として決定します。
5. 理想のまちづくりを実現しよう
地区計画が決定された地区内で建物を新築したり改築したりするときは、市への届け出が必要になります。地区のみなさん一人ひとりが地区計画のルールを意識し、守っていくことによって、目標とするまちづくりが進みます。
歴史的な資源や美しい景観を生かしてまちづくりをすることもできます
「景観まちづくり条例」は、貴重な建造物や風景を地域のみんなで守り育てるために作られた市独自の条例です。この条例を活用したまちづくりの進め方は、基本的には地区計画制度と同じです。地域の中で特に大切にしたい建造物や風景がある地区は「景観まちづくり条例」を活用してまちづくりのルールを作ることができます。
今年五月には、地域のみなさんの努力により、鶴林寺周辺地区が市内で初めて「景観形成地区」に指定されました。
歴史を感じる落ち着いた街並みづくりに取り組んでいます
鶴林寺は聖徳太子ゆかりの歴史あるお寺です。境内では季節ごとに美しい花が咲き、周囲の公園は市民の憩いの場にもなっていて、観光客や親子連れなど多くの人が訪れます。鶴林寺周辺地区は、落ち着いた雰囲気の家が多く、歴史を感じさせる街並みも残っています。このまとまりのある良好な街並みを守っていくことを目標に、まちづくりに取り組んでいます。景観まちづくりで定められたルールの一部を紹介します。
- 屋根の形や外壁に使える色の範囲を決めて、落ち着いた街並みにする
- 塀や門柱、カーポートなどには、自然な風合いを醸し出す素材や色を使う
- 道路際に設置するエアコンの室外機や自動販売機などは、周囲の景観と調和するように配慮する
- 道路舗装や照明などの公共施設についても、自然な風合いを醸し出す素材や色を使う
尾上町 山本 昇さん
加古川町 小西 正俊さん
加古川町 沼田 勝夫さん
生まれたときからここに住んでいる私たちにとって、この地区は歴史ある自慢の地区です。この景観を守り育てていくために取り組みを始めました。最初は、説明会になかなか人が集まらず苦労しました。みなさんに説明会に来てもらえるよう、地区内で出会う人に声をかけ続けるうちに参加者も増え、回数を重ねるごとに「参道の舗装はどうしよう」とか「建物の色はこんな色がいい」など活発な意見が出るようになりましたね。
最近では、「建てられるのは3階建てまでだったね」とか「壁を塗り替えるんだけどこの色は大丈夫かな」などお互いに聞き合うこともあるんですよ。決めたことをみんなで守っていくことは大変で難しいと思いますが、「自分の家や家の周りから良くしていこう」という気持ちを一人ひとりが持てば、理想のまちづくりは必ず実現すると思います。住んでいる私たちだけでなく、鶴林寺を訪れた人が魅力を感じられるような街並みをみんなで作っていきたいですね。
みなさんのまちづくりを応援します
都市計画課 杉山 主査
今回紹介した制度を活用したまちづくりは、特別な地区だけで行われるものではありません。「自分のまちを良くしたい」「いつまでも魅力あるまちであり続けたい」、そう思う地域のみなさんが集まれば、市内のどこの地域でもできることです。何より大事なのは「計画をつくる」ことではなく、自分たちのまちを良くしようと、いろいろな思いや悩みを話し合い、まちについて考えることなのです。そこから、地域の魅力や誇りが生まれ、わがまちへの愛着が生まれます。
市ではさまざまな課が協力し、みなさんのまちづくりを応援します。職員がみなさんの地域に出向いて、制度に関する説明など出前講座をすることもできます。まちづくりについて聞きたいことや取り組みたいことがありましたら、まずは気軽にご相談ください。
「地区計画」や「景観まちづくり」について、くわしくは市役所都市計画課(電話番号:427-9268)へ。
ミニ特集
応援します! あなたのチャレンジ男女共同参画センターのチャレンジ支援
市男女共同参画センターでは、結婚や出産を機に仕事を辞めた女性の再就職やキャリアアップ、起業、地域活動など、女性の幅広いチャレンジを応援するため、各種相談窓口やセミナーを開いています。このページでは、その内容を紹介します。
何気ない疑問から専門的なことまで気軽に相談してください
「はじめの一歩」をキャリアアドバイザーが後押し!
女性のチャレンジ相談
「私にはどんな仕事が向いているかしら」「子育てをしながら再就職したい」「起業ってだれでもできるのかしら」といった、就業・起業などに関する疑問・相談に、専門的な資格を持つキャリアアドバイザーがお応えします。みなさんの抱えているさまざまな思いや不安な気持ちをじっくり聴きながら、一緒に心の整理をしていきます。
【とき】毎週火曜日・水曜日午前10時から午後4時30分
要予約。相談は1回50分まで。一時保育を受け付けます。
パソコンを使った女性のためのチャレンジ相談
インターネットを使ったことのない人を対象に、ハローワーク求人情報の検索方法などを指導します。
【とき】毎週火曜日・水曜日午後1時30分から2時30分
要予約。一時保育を受け付けます。
【定員】3人(先着順)
子育て中でも働いていいんですよ
キャリアアドバイザー 瀧井 智美さん(33歳)
9年前、一人目の子どもを出産した後、働き方に悩んでいたときに、キャリアアドバイザーとの相談で勇気をもらったんです。私も悩んでいる人の背中を押してあげたいと思い、勉強してアドバイザーの資格を取りました。現在、3児の母ですが、 1 歳と 4 歳の子どもを保育園に預けてこの仕事をしています。
相談には30歳代の子育て中の女性がよく来られます。一時保育を利用したり、わが子を抱っこしたまま相談を受けたりする人もいますよ。
子どもを預けて働くことについて、マイナスのイメージを持つ女性もいますが、家族のためにも自分のためにもプラスになることもあると、私たちと話すことで気付いてもらいたいですね。
ここへ来れば「自分」を見つけられますよ
キャリアアドバイザー 中嶋 まゆみさん(42歳)
会社経営と3児の母をしながら、キャリアアドバイザーをしています。
チャレンジ相談では、再就職や起業などの相談だけでなく、「自分の思いを打ち明ける機会がない」「何かをはじめたいんだけど…」という漠然とした相談も結構寄せられています。そういったみなさんに「ここに来てよかった」「こんなにじっくりと話を聴いてもらえたことはない」と言ってもらえたときはうれしいですね。
チャレンジ相談に来て話をするうちに、頭の中が整理できて、何かに気付いたり、やりたいことを見つけたりできるかもしれません。自分の将来について、自分のためにじっくり時間を使ってほしいですね。
市男女共同参画センター(電話番号:424-7172)
【所在地】加古川町寺家町45 JAビル3階
【開館日時】年末年始を除く毎日午前8時から午後8時
駐車場は、ミニ市役所南にある「共同駐車場」をご利用ください。利用者には1時間無料券を渡します。
男女共同参画センターが主催する事業は、子育て中のみなさんが利用しやすいよう、一時保育を行っています(要予約)。
一人で悩まないで専門家の意見を聞いてみませんか?
働く女性の労働相談
「労働者としての扱いが男と女で違う」「突然解雇された」「セクシュアルハラスメントを受けているのだが…」といった職場の問題や、保険・年金など、働いた場合の社会保障制度について、社会保険労務士が法的にアドバイスします。
【とき】毎月第3木曜日午後2時から7時
2日前までに予約が必要です。一時保育を受け付けます。
職業能力開発相談
ポリテクセンター加古川の専門アドバイザーが、事務、情報システム、CADなど希望する職業に必要な技能の習得や就業に向けたアドバイスをします。
【とき】毎月第4月曜日(祝日の場合は翌日)午後1時から4時
一時保育を受け付けます(要予約)。
聞いて知っトク!体験してなっトク! 就業支援セミナー
就業を希望している人を対象に、さまざまな職業に関する知識や情報、自己啓発の機会を提供するセミナーや講座を開催しています。また、起業や自宅で働くSOHO(ソーホー)・在宅ワークなどに関心がある人についても、セミナーを通して経験者・成功者の生の声を届けるなどしています。
男女共同参画センターの講座参加無料
いずれも時間は午前10時15分から午後0時15分。会場は男女共同参画センター(JAビル3階)。定員は各30人(先着順)。一時保育を受け付けます(先着8人)。
ステップアップセミナー
- 実践!自分をひきたてるメイクアップ法
好印象を与えるメイクや個々の顔立ちに合った自分らしいメイク方法のポイントを、実際にメイクしながら学びます。
【とき】10月10日(水曜日) - 人とつながる!「コミュニケーション力」アップ講座
コミュニケーションを豊かにし、より良く人とかかわり合うコツを知り、気持ちを上手に伝える方法を学びます。
【とき】10月17日(水曜日)
就業支援セミナー「AiDEMに聞く!求められる人材」
就業するには、まず、自分を見つめ、自分にあった働き方を考えるとともに、就業の状況、企業が求めている人材を知ることが大切です。実際の就職活動をする前に、ポイントをおさえてみませんか。
【とき】10月23日(火曜日)
【対象】女性
気持ちいい自己表現講座
引っ込み思案でもなく、攻撃的でもない、自分の気持ちにぴったりな自分の言葉でさわやかな自己表現をしてみませんか。自分を大切にしながら、相手も尊重する表現方法を実践的トレーニングで身に付けます。
【とき】10月15日(月曜日)・22日(月曜日)・29日(月曜日)
3回コース。
【対象】女性
申込方法 10月5日午前9時から、電話で市男女共同参画センターへ。
チャレンジショップへ行ってみよう
好きなことや趣味を活動に生かしている女性たちの手作り作品、加工食品などを販売します。ぜひ、お越しください。
【とき】10月17日(水曜日)午前11時から午後2時
【ところ】男女共同参画センター(JAビル3階)
【内容】パン、おこわなど手作り加工食品、手芸品などの展示・即売
一時保育はありません。
子どもを預けて… ちょっと一息、読書タイム
男女共同参画センターには、子育て、女性の生き方、就業に関する図書があります。10月27日からはじまる読書週間にちなみ、子育て真っ最中のみなさんがゆっくり読書できるように、センターで子どもを預かります。センターにある本を読むもよし、お気に入りの本を持参するもよし。ぜひご活用ください。
【とき】10月31日(水曜日)、11月1日(木曜日)午前10時から正午、午後1時から3時
【ところ】男女共同参画センター(JAビル3階)
【定員】各 8人(先着順)
【参加費】無料
【申込方法】10月5日午前9時から、電話で市男女共同参画センターへ。
就職フェア 就職のための事業所面談会
加古川市や近隣市町事業所の人事担当者との個別面談を実施します。ほかにも、ハローワーク、職業訓練、チャレンジ相談などのブースを設置しています。
一時保育を受け付けます(要予約)。
【とき】10月30日(火曜日)午後2時から4時
【ところ】男女共同参画センター(JAビル3階)
【対象】就職・転職を希望する、女性かおおむね35歳までの人(新卒者を除く)
【参加費】無料
【持参するもの】履歴書(数枚)、筆記用具
タウンタウン
こんにちは現場の「空気」を自分の言葉で伝えたいBAN-BAN(バンバン)ラジオの「ジモーター」
鈴木 勝(すずき まさる)さん(28歳)
八幡町在住
「『楽しい!』『すごい!』といった現場の雰囲気を、分かりやすく伝えたいですね」と話すのは、鈴木勝さん。鈴木さんは、コミュニティFM局BAN-BAN(バンバン)ラジオの「ジモーター」だ。ジモーターとは、土・日曜日に放送されている番組に出演したり、番組の企画を立てたりしてラジオを支える「地元のサポーター」。十六歳から五十三歳まで、幅広い年代の十二人が活躍している。
普段は、大学職員として入試課で、学生募集に関する広報などを担当している鈴木さん。ジモーターに応募したのは、偶然ホームページで募集案内を見つけたことがきっかけだ。「小さいころから人前で何かすることが好きだったので、見つけた瞬間に『これだ!』と思いました。それに、言葉で何かを伝えるという経験は仕事でも役立つと思ったんです」。翌日、さっそく履歴書を書いて応募したところ、約七十人の応募者の中から見事選ばれた。
鈴木さんは、主にイベント会場などからのリポートを担当している。さまざまな場所に出向くたびに、リポートの奥の深さを感じるという。「現場で見て、聞いて、感じたことを、自分の言葉で表現するのがリポーター。特に、ラジオは音声だけで伝えなければならないので、難しいけれどやりがいがあります。川の絵画大賞展のリポートでは、スタジオから『会場にはどんな絵が展示されているんですか?』と聞かれ、どう伝えたらいいのかパニックになりそうでしたよ」と笑う。
リポーターの経験が、仕事にも生かされているという鈴木さん。「リポートは現場のようすを、入試課の仕事は大学の素晴らしさを、どちらも伝え、知ってもらう仕事です。『伝える』にはどうすればよいか、リポーターをすることで、違った側面から考えられるようになりました」と話す。リスナーから「リポートを聴いて、イベントに来てみました」と生放送中にメッセージをもらったときは、楽しそうなようすが伝わったと本当にうれしかったそうだ。
九月にはBAN-BAN(バンバン)テレビにもリポーターとして出演するなど活躍の場を広げている鈴木さん。これからも仕事と両立しながら活動を続けていく。「働きながら好きなことができるのは、周囲の理解や協力があるからこそ。本当に感謝しています。これからも、一回一回の現場を大事に、そこでの人との出会いを大切にリポートしていきます。そして、『リポートなら鈴木勝』と言われるくらいになりたいですね」と笑顔で語ってくれた。
- 大学のオープンキャンパスでは、入試を考えている高校生に分かりやすくアドバイス。
- インタビューでは、放送前にたくさん会話することでリラックスしてもらえるよう、心がけているそうだ。
市民リポーター阿部 英美の「行ってきまーす!」
地元に密着したFMラジオ局
このごろ、まちで見かけるステッカー…何だろうとよく見ると「BAN-BAN(バンバン)ラジオ」の文字! えっ?ラジオ始めたの? 知らなかった私は、さっそく、くわしいことを聞いてみたいと
いざラジオ局に潜入!
「BAN-BAN(バンバン)ラジオは、今年の四月に開局したコミュニティFM局です」と教えてくれたのはディレクターの大竹さん。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の地域を放送エリアとしているため、交通情報や天気予報も、地元情報が満載で役立つものばかり。普段は、個性豊かなパーソナリティたちが楽しいトークを聴かせてくれていますが、いったん災害が発生すると、避難場所や給水場所などの災害情報を発信する番組に切り替わるとか。「持ち運べ、電池でも動くラジオは、災害時、最後に残る情報伝達の手段です」と語る大竹さん。日ごろから身近なラジオ局でいたいという思いから、日夜番組内容を考えているようすに、「やりがいがありそうですね」などとお話していると、
「良かったら番組に出てみる?」
とのお誘いが! 待ってましたぁ。月から木曜日の夕方四時から七時まで放送中「ゆうがた じもとラジオ」にゲスト生出演することになりました。
さて本番当日。パーソナリティは、月曜日担当で主婦に絶大な人気を誇る矢野ゆかりさん。気分上々の中、本番がスタートしました。矢野さんの紹介で「阿部英美でーす」と第一声を上げた時、「私の声が電波に乗ってみんなの元へ届いている」と実感し大感動! 矢野さんの明るいトークとパワーに引っ張られ、ラジオ初出演の私も緊張しつつ楽しくおしゃべり。そして、いよいよ私が担当する、加古川市からの情報を伝えるコーナーです。約五分間で三つの記事を読むので、間違わないかと不安でしたが、練習のかいあって無事クリア♪ 浮かれる私の前で矢野さんは、分単位の番組スケジュールに沿ってトークを進めたり、CM中に原稿に目を通したりと大忙しです。が、そんなところをまったく感じさせず番組を進めていく技はさすがプロ!楽しい一時間の中、言葉だけで番組を展開していくラジオならではの難しさも感じましたが、苦労を上回るラジオの魅力に触れることができました。
番組で渋滞の状況を伝えると
その原因がリスナーからメールで届くこともあるとか。地元に密着したFM局ならではですね。週末には、地元のみなさんが「ジモーター」として活躍する番組があったり、トライやるウィークで中学生を受け入れたりと、地元と深くかかわっています。「作る側と聴く側、みんなで協力して番組作りしていきたいですね」と語る大竹さん。ラジオを身近に感じた体験になりました。普段はラジオを聞く習慣のない私ですが、これを機に「86・9メガヘルツ」に合わせて、車で、自宅で楽しもうと思います。
ここで一句
生活に すっと溶け込む 地元のラジオ
- スタジオには機材がいっぱい。オープニング曲や効果音などがボタン一つで流れます。大竹さんが押すたびに大はしゃぎの私でした。
- 友人より応援ファックスが届きました。番組で読まれるとクセになるそう。みなさんも送ってみては?
「こんにちは」のコーナーに登場していただける人を募集しています。 申込・問合先:ハガキに・住所・氏名・電話番号・活動内容を書いて、〒675-8501 市役所広報・行政経営課「タウンタウン」係(電話番号:427-9121)へ。
電話・ファクスでも受け付けています。
グラフ加古川
やったー! 手が届いたよ
9月2日、東加古川公民館主催の「木登り体験教室」が明石公園で行われました。参加した10人の小学生は、ロープを使った木登り「ツリーイング」にチャレンジ。初めは両足が地面から離れただけで怖がっていた子も、次第に高さに慣れ、最後には約15 の高さまで登りました。子どもたちは、木の上から眺める景色に「わあっ、高ーい」「気持ちいいー」と歓声をあげていました。
お父さん はやくはやくー!
8月25日、総合体育館で「にこにこファミリー運動会」が行われました。高校生ボランティアが中心となって企画・運営するこの催しには、小学生未満の子どもとその家族144組478人が参加。玉入れや大玉ころがしなど4種目に挑戦しました。大玉ころがしでは、大きなボールに子どもたちは大喜び! 親子で力を合わせてゴールを目指し、ふれあいのひとときを楽しみました。
エコらむ その3
「エコらむ」は、環境(エコ)に対する市の取り組みや提案などを紹介するコラムです。
市では「市役所も一つの大規模事業所である」という考えのもと、平成13年度から「環境配慮率先実行計画」に基づき、市役所内の省エネ・省資源に取り組んでいます。今回は、昨年度の取り組み結果を紹介します。
温室効果ガスの排出量を約3パーセント削減するなど、成果をあげています
昨年度は、取り組みの効果を測るための基準となる平成16年度と比べ、都市ガス使用量が約9パーセント、灯油使用量が約27パーセント、上水使用量は約3パーセント削減されました。電気使用量が約2パーセント、LPガス使用量は約10パーセント増えましたが、これは測定対象となる施設数の増加などによるものです。
こうしたエネルギーの使用などで生じる二酸化炭素など温室効果ガスの排出量は、約3パーセント(二酸化炭素に換算して672トン)削減されました。これだけの二酸化炭素を樹木に吸収してもらうには、杉の木なら4万8千本、森林面積にすると約57.6ヘクタールの森林が必要となります。これは、甲子園球場約15個分と同じ広さです。
今後も、市の事業が環境に与える影響をできるだけ少なくするよう、取り組みを進めていきます。
次回は、2月号で「市の環境啓発活動」について紹介します。
行政懇談会
さらに住みよいわがまちを目指して話し合いました
市では、市民のみなさんの意見をお聞きし、さらに住みよいまちにするために、毎年行政懇談会を開催しています。今年も八月二十五日に総合福祉会館で町内会連合会の理事や評議員のみなさんが、市長や副市長、各部局長と市のまちづくりについて懇談しました。 このページでは、話し合われた内容についてお知らせします。
県立病院移転後の跡地に病院の確保を
平成二十一年に県立加古川病院が移転することにより、周辺の地域が医療の空白地域とならないよう、市では県に要望を重ねています。その結果、県からは地元の意向を尊重した跡地利用を検討していきたいと回答を得ました。
移転後の跡地利用については、介護付きのマンションも考えられますが、市としても地元の意向を踏まえ、地域の医療サービスが低下しないよう、みなさんが安心して利用できる病院機能を中心とした跡地利用について、引き続き、県に要望していきます。
今年度から廃止された敬老会記念品に代わる助成金の交付を
敬老会が現在の開催方式になった昭和四十八年から、この三十五年間で対象者は約七千三百人から約三万五千人へと増大しています。今後の高齢化の進行を考えると、一カ所で開催することも近い将来には限界になるのではと危惧しています。
敬老会の地域での開催は、より多くの参加が見込まれることや地域でのコミュニティづくり、高齢者を取り巻くネットワークづくりなど、さまざまなメリットがあるものと思われます。提案の趣旨を踏まえ、来年からの敬老会のあり方について検討していきます。
別府川のしゅんせつと河口付近の危険水域標識とカメラの設置を
平成五年度からの本格的な下水道整備により、別府川の水質観測地点である別府橋地点の水質は年々改善され、環境基準内の水質となっています。しかし、別府町の対汐橋から野口町の良野大橋の区間については、改修後三十年が経過し、水質は改善されていますが、潮の干満が原因で水の流れが悪くなる「感潮河川区間」であることから、ヘドロが川底に堆積しているものと思います。市としても、ヘドロなどの堆積状況の把握に努めるとともに、環境対策面も考慮し、しゅんせつの実施に向けて強く県に要望していきます。
危険水域標識とカメラの設置については、河川の増水や高潮状況を確認し危険性を判断することができるため、標識については地元と協議し、また、カメラについては市内部ならびにBAN│BANテレビと調整していきます。
志方地区の下水道の早期整備を
志方町の下水道整備については、公共下水道事業と農業集落排水事業により順次整備を進めています。公共下水道の整備は、平成十五年度に市街化調整区域整備計画を策定し、効率的な下水道整備を進める中で、横大路地区などの一部が短期整備区域に前倒しできる状況になりました。なお、本年度は、横山台一円の整備に向けて、幹線管きょの整備を行います。
また、農業集落排水事業は、志方西部地区と志方中部地区について平成二十年度の完了を目指して順次管路を整備しています。
今後も、公共下水道事業の経営健全化を図りつつ、社会経済情勢を的確に把握し、三カ年をめどとした整備計画の見直しを行うなど、下水道整備の促進に努めていきます。
- 県立加古川病院は神野町に移転します。
- 満潮時には水の流れが停滞する別府川(写真は新野辺大橋付近)。
ファミリーサポートセンター
ご利用ください 便利で安心
ファミリーサポートセンターとは、おおむね生後6カ月から小学校6年生までの子どもを「預かってほしい人」と「預かりたい人」がそれぞれ依頼会員・提供会員になって、地域の中で助け合う会員組織です。現在、約1,700人のみなさんが会員になっています。
こんなときにご利用ください
- 急な残業で子どもを迎えにいけない
- 実家の親に急用があるため、子どもの面倒を見てもらえない
- 求職活動で面接に行く
- 町内の夜の会合に出席する
【利用料金】
【活動区分】
- 月曜日から金曜日 7時から19時 料金 700円
- 月曜日から金曜日 6時から7時、19時から22時 料金 800円
- 土曜日・日曜日、祝日、年末年始 料金 800円
料金は子ども一人当たり1時間の料金です。
ファミリーサポートセンター提供会員講習会
400人を超える提供会員が子育て中の家庭を応援しています。年齢層も20から70歳代まで幅広く、中には乳幼児の子育て真っ最中の人もいます。みなさんも提供会員になって、子育てを応援しませんか。
【とき】10月22日(月曜日)・24日(水曜日)・25日(木曜日)午前10時から午後3時
3回コース。25日は午後3時30分まで。3日間通して参加できない人は、次回補講を受けることができます。
【ところ】加古川駅南まちづくりセンター(JAビル4階)
【内容】子どもの世話と遊び、身体の発育と病気、事故と応急手当など
【対象】次のすべての条件に当てはまる人 (1)市内に住んでいる (2)育児に関心がある (3)提供会員としての活動(保育園の送迎、自宅で子どもを預かるなど)ができる
【定員】30人(申込者多数の場合は抽選)
【参加費】無料
一時保育を受け付けます。
【申込方法】電話または直接ファミリーサポートセンターへ。
提供会員として汐音くんの送迎などをしています。わが家で預かっているときは、子どもたち同士で楽しそうに遊んでいますよ。
鹿子尾 泰代(かこお やすよ)さん (40歳)
赤鹿 汐音(あかしか しおん)くん(別府西小学校2年)
萌(もえ)ちゃん (4歳)
賢(まさる)くん(1歳)
【問い合わせ先】ファミリーサポートセンター(JAビル4階 市コミュニティ協会内 電話番号:24-9933)
受付時間 午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
えんぴつ
グラフ加古川の撮影で、木登り体験教室に行きました。「子どものころ、近所の公会堂の木に登ったなあ」と思い出しながら現場へ向かうと、そこには、二十メートルを超える大きな木につり下げたロープを登る子どもたちの姿が。想像していた木登りとは違い、びっくりしました。でも、自然とふれあう子どもたちの笑顔は昔と同じ。カメラをのぞいていると、自分もあのころに戻って自然の中で遊んでいる、そんな錯覚を起こしそうでした。秋は自然を楽しむには絶好の季節。みなさんも、自然を感じに出かけてみませんか。 (岡)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
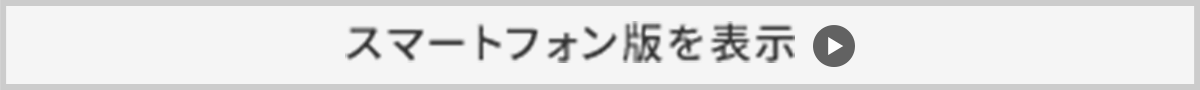








更新日:2019年12月23日