(記者)
Decidimは基本的にはスマホでの利用がほとんどというような感じですか。
【職員】
そうですね、パソコンで見られている方もおられますが、インターネットを見る時については、総務省の統計調査で見ましても、スマートフォンの世帯保有率が90%を超えており、インターネット機器としてスマートフォンで閲覧されている方が7割を超える状況があります。LINEとかFacebookに慣れている方にとっては文字量が多いのは、使いにくいのではないかということで、文字量を減らすなどの改良をしました。
(記者)
文字をちょっと大きくしたという感じですか。以前より見やすくなっていますね。
【職員】
そうですね。デジタル庁が示しているウェブアクセシビリティのガイドブックを参考に、いろんな人が見やすいシステムを意識して改良し、視認性も高めた上で改良を進めています。
(記者)
さきほど、庁内でもちょっと見にくいみたいな話があったっていうふうにおっしゃっていたんですけど、市民や利用者からも、そのようなお声があったんですか。
【職員】
そうですね、今回の改良に合わせ、10月、12月に開催した加古川駅前のまちづくりを考えるワークショップの際、ユーザーの方に実際にスマートフォンで使っている様子をユーザー調査というかたちで見る中で、文字が多くて読んでいないという状況でした。文字量を減らさないと見ていただきたい情報も見ていただけないだろうということで改良した次第です。
【市長】
もともとこのDecidimを導入しようとなった時のことを思い返しますと、本当にこういうものが、近々ですね、誰もが活用するようなツールになっていくはずだと直感的に思ったところがあります。今ではSNSでどんどん言いたいことを書くのが普及した時代になっておりますけども、登録したアカウントで利用していただく方式になっており、少し落ち着いたかたちで議論をしっかり建設的にしていきたいと思っています。私自身もこれまで、登録アカウント名では誰か分からないアカウントで、何回か書いて参加はしているんですが、来年度からもっと利用を広げていく意味で、自分自身も積極的に、場合によっては名前と顔写真付きで書いてもいいのかなと思ったりもしています。
(記者)
募集のテーマにもよるんですけど、やっぱり使ってほしい層とか、年代層みたいなデジタルに触れてもらえるような人に書き込んでほしいのでしょうか。
【職員】
はい、そういうかたちになってくると思います。最近もプレスリリースをしている、高校生に防災のことを考えてもらう取り組みがあります。利用される対象者に合わせて、使っていただく作り方をしていきたいと考えています。
【市長】
現状、担当課の職員が頑張ってくれてまして、登録アクセス数とか、ユーザー登録者数とかの分析をし、約4,000人のうち、20代が48%、30代が24%になっています。それは、何もせずに自然とそうなったというわけではなくて、職員が加古川東高校からの依頼でワークショップを行うなど、その中でDecidimを紹介しています。これからスムーズに利用してもらえるようにするため、基本的には若い人の市政参画を促進したいっていうところは大事だと思っています。ただ、60歳を超えている方もスマホを使う時代なので、ぜひ使っていただきたいですね。
(記者)
さきほど、市長がおっしゃっていた登録者数の内訳をお願いします。
【職員】
12月末時点で4,358人の方がユーザー登録をしていただいています。年齢層は75%を超える方が30代以下になっていまして、10代が5.9%、20代が48%、30代が24%で、若い方の参画が多いです。
(記者)
さきほどの高校のワークショップなどがありましたが、始まった当初は新聞やテレビの報道も多分あったと思うんですが、それ以降は継続的なPRというか、販促についてどのようなことをされているのでしょうか。
【職員】
加古川東高校は毎年授業に参加させていただいています。また、兵庫県立大学はスマートシティの取り組みが始まった時から連携しており、今年度は大学1年生の方に授業をさせていただいてDecidimを活用するということも行っています。その中では、加古川市が公開しているデータを使って大学生に分析していただいています。Decidimでは特定の方で意見交換する場を作ることができ、大学生と担当課で意見交換・議論するということも行っています。
(記者)
イメージとしては、テーマごとにスマートシティとか加古川駅周辺のまちづくりなどをここにスレッドみたいなかたちでするということですか。
【職員】
そうですね。スマートシティ構想であったり、駅周辺のまちづくりであったり、今年度は産業振興課が取り組んでいる観光まちづくりプランの策定に向けて活用しています。
(記者)
登録できるのは市民の方ですか。
【職員】
いえ、市民の方に限っていないです。
(記者)
例えば、近隣市町に住んでいる人や、加古川市に勤めていますっていうだけでも登録はできて、ただ、登録の時に実名を入力するということですか。
【職員】
実名は登録しますが、表向きにはニックネームで投稿できます。
(記者)
あまり悪意があるような書き込みは、すぐ分かるようになるわけですね。あと、さっきおっしゃったルールを伺っていいですか。
【職員】
オンライン上で誹謗中傷とかが起こらないように、誰もが気持ち良く過ごせるための三つのルールを定めています。いきなり否定するのではなく、そういう意見もいいですよねということや、先ほどお伝えしたニックネームで、投稿する前には最終的に自分の意見がインターネット上に出ていきますので、問題ないかっていうのをよく見ていただくということを定めています。
(記者)
あと、具体的に何か政策が生まれたり、こういう効果があったとか、改善に結び付いたとか、何かそういうものはありますか。
【職員】
加古川東高校と大学生の取り組みで、靴下を母の日や父の日に贈るということに取り組まれた高校生が進学して九州の大学に行かれているんですが、卒業した後にも加古川市でワークショップしますと案内したら、たまたま帰省の時と重なったのかもしれないですが、ワークショップに参加していただいたことが印象に残っています。このような取り組みが加古川市に愛着を持つことにつながっているのではないかと感じました。
【市長】
あとは、施設名称の候補を示して投票していただいたりとかで、そのような機能もありますね。
【職員】
そうですね。かこてらすという平岡町にある東加古川子育てプラザと東加古川公民館の複合施設で、施設名称を絞り込む際に投票機能を活用して、9案から3案にDecidimで絞りました。
(記者)
約4,000名の中で、市内外でいうと、どれぐらいの割合ですか。
【職員】
正確には把握できていないですが、市内と市外では、大体半々ぐらいです。
(記者)
これまでにどれぐらいのテーマで議論をしたっていう数字は出ていますか。
【職員】
これまで18個のテーマで議論しています。
(記者)
それの平均のレスっていうか、返信とかの数はどれぐらいなんでしょうか。
【職員】
これまでのコメント数の総数は、1,410のコメントをいただいています。
(記者)
例えば、パブリックコメントとかだったら一方通行じゃないですか。例えば、誰かが何かを言えば、またそれに対して誰かが言って、またそれに対してっていう、双方向というか、議論になるっていうのが大きいですかね。
【職員】
そうですね、パブリックコメントとは違い、自分が意見したことに対して、他の人がどう思っているのかを「いいね」のボタンがあることで、皆さんが賛同している意見なのかを投稿された方には感じていただけるのかなと思います。
【市長】
まさにそこですね。パブリックコメントを出しても、最後締め切ってから見解が一覧で出ているんですけれども、だいぶ先になりますから、どうしても書く気になれなくて、意見の数が非常に少なかったので、こういうものが大事だと思っています。また、課題として挙げるとすれば、例えば私自身や職員が回答、返答というか、ディスカッションに入っていけたら1番いいんですけど、例えば要望に近いことがあった時に、そこにどう書くかというのは、誰が責任を持ってどこまで書いていいのかというのはちょっと悩ましいこととして常にありますね。例えば、環境部のことについて他の部の職員が書けるかというと、経験があったとしてもやっぱり書きにくいですしね。そういうところで、どういうふうにそこに応対していくかという課題を持ちながら、デジタルの部署の職員が主に対応していますけども、ある程度の責任を持った人が書かないというのは課題としてあります。ただ、そういうのがうまく回っていき出したら非常に有効なツールになるのは間違いないと思っています。
(記者)
モデレーター的な、議論を整理するような方っていうのは置かれていないっていうことですね。その議論の中で、議論の交通整理みたいなことをやる人が必要かなっていうことが他の掲示板とかであるんですけれども、そういったことはされていないのですか。
【職員】
そうですね。そのような役割は、ワークショップを主催した講師の方、担当課や私どもがしています。
(記者)
それは匿名でやるんですね。職員として出すのですか。
【職員】
職員としてや、課の名前で出したりしています。
(記者)
繰り返しになるんですけど、掲示板って今、ネットやSNSも含めて賛否両論というか、功罪半ばするところがあると思うんですが、改めて使っていこうっていうことだと思うんですけど、期待されるところはありますか。
【市長】
まだこれも途上にあるものかなとは思うんですけどね。匿名で書いた内容に責任を負わなくていいような状態で、好き放題書かれて炎上しますので、他の自治体は分かりませんが、Decidimの場合は登録したアカウントで利用してもらっているんですけど、登録時に身分証明書まで照会して、確認しているかっていうと、そこまでやっていないわけなんですよ。ですから、偽名で登録したアカウントを作って書くこともできますので、そういう意味では、最終的にこれからどんなふうに進んでいくのか分かりませんけれども、やっぱりもう少し、いざ書いたことが問題を引き起こした時には、ちゃんと誰か分かるようにしていくことは必要なのかなとは思うんですが、あまりその個人名の登録に手間をかけると、登録者数が増えないってことになりかねないなという悩みで、まずはこういうやり方で運用して、何年か経っているということです。最初は野放しに解放するかっていう案もね、あったんですけどね。
(記者)
Decidimは国内で初めてということなんですけど、同じような機能を使った他のサービスでやっているところはあるんですか。
【職員】
Decidimを導入して運用した後に、他の企業などもこういうツールを開発されているのは把握しています。
(記者)
結構Decidimが主流というか先行していて、他の自治体も活用しているんですかね。
【職員】
そうですね、浜松市や福島県西会津町では活用されています。
(記者)
兵庫県内では、ありますか。
【職員】
県内では把握していないですが、大阪・関西万博でも使っているっていうのは聞いていて、チラシの裏側でも紹介しています。
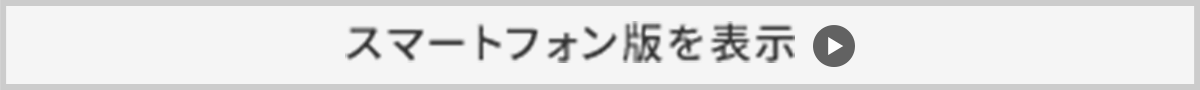








更新日:2025年01月31日