(記者)
かわまちづくりのリバサイトについてですが、全国で初めて規制緩和制度の先行事例になるということですか。
【市長】
そうですね、国が去年の5月から規制緩和に関する社会実験を始めてくれていますので、この制度を使って、20年を想定して何かしていくという事例は初めてになります。
【職員】
リバサイトの制度について、この制度が始まってからこのような制度を活用しようとする事例というのが初めてで、実際こちらを活用するタイミングが使用許可の手続きなどを進める時になりますので、まだ少し先になります。そのため、その間に他の事例が出てくる可能性もあるのですが、この制度をしっかり活用してこのスキームに乗って事業を進めていこうという事例は、今のところ全国で加古川市が初めてという状況です。
(記者)
こういう制度を使ってやりますよということですね。
【職員】
そういうことです。
【市長】
途中で抜かしていくのが出てくる可能性はありますけどね。
(記者)
そうですね。
(記者)
事業の枠組みについてですが、占用許可を市が国交省から受けて、それを民間事業者に貸し出すという仕組みですか。
【職員】
そうです。資料にありますように、このたびの事業用地については、国から全て占用許可を市が受けることになっております。 その上で、市が民間事業者に対して民間ゾーン部分の賃貸借契約を結びまして、貸すというかたちになります。
(記者)
公共部分に関しては?
【職員】
はい。同じく市が占有する部分になります。
(記者)
その公共部分の整備に関しての費用は、今回、民間は整備費用を負担して整備ということですか。
【市長】
今回提案を募集するに当たりまして、その公共部分の整備の提案内容の費用上限として1億2,000万円までを公共部分の整備として市が出せますよっていうふうに事前に言っていますので、民間事業者がそれを勘案して整備されていくということですね。
(記者)
民間ゾーンの整備部分の事業提案時での総事業費はどのぐらいでしょうか。
【職員】
そうですね、提案のあった事業計画などの中では約1億円となっています。
(記者)
面積はどれくらいでしょうか。
【職員】
はい。面積につきましては、事業用地全体で3,000平方メートルあるんですけれども、そのうち民間ゾーンが約760平方メートルで、公共ゾーンは残りの約2,240平方メートルです。こちらのパース図で、飲食施設の建物の部分と、この右側に隣接する半円形の広場が民間ゾーンになっています。そこからまた右にありますトンネルのような絵があるんですが、こちらの方が公共ゾーンとして整備をいたします。
(記者)
かわまちづくりの概要にある公共ゾーンのところですが、これが遊具広場とかになるのですか。
【職員】
そうですね。
(記者)
地形を生かしたというような、ちょっとイメージ的に滑り台とかあるのかなと思ったのですが、どういう感じでしょうか。
【職員】
はい。既存の遊具を置くような場所にはしたくないというのが提案者さん側の強い思いとしていただいておりまして、その中で、この堤防上にまた少し土を盛ったりしながら、高低差とか傾斜を使った空間を作られたいというような提案をいただいています。
遊具の部分につきましては、パース図の左下の絵の方を少し見ていただきますと、 左側にグレーの着色をしているところ、子どもさんがボルダリングの壁を登っているような絵とかネットがあったり、 また、トンネルを入れていって、遊べるような場所を作れたらいいなというようなご提案をいただいています。また、全体のパース図のところで、トンネルの横に階段があったり、ちょっと芝生のような広場があったりというようなイメージもされていまして、このようなところで寝転がって遊んだり、くつろいだりとかできるような場面を作っていきたいというようなご提案があります。
先ほど市長からもありましたように、実際の整備に当たっては、いろいろ堤防上の強度の問題とかもありますので、そういったところは国交省さんに詳細設計を進める中で相談させていただきながら、提案の内容にできるだけ沿うようなかたちで協議してまいりたいと考えています。
(記者)
あくまでこういうものが予定で設置されるかもということですね。
【職員】
はい。
(記者)
パース図で言うと、この赤い点線が公共ゾーンと民間ゾーンの境目でしょうか。
【職員】
赤の点線枠については事業用地になりますので、公共ゾーンと民間ゾーンを含んだ部分になります。
(記者)
これが大体3,000平方メートルで、盛土部分ということですね。
(記者)
かわまちづくりのエリア全体の広さってどのぐらいになるんですか。
【職員】
河川敷公園としてバイパスからJR南側までで約5ヘクタールです。
(記者)
あと、よく加古川って大雨の時に、結構なみなみと浸かる時がありますが、盛土部分には来ないということですか。
【市長】
そうです。
(記者)
河川敷公園部分は浸かっても。
【市長】
公園部分は以前から浸かっていまして、河川敷に高さのある建造物を作ると川の流れを阻害するため、難しいといわれています。それで、今回、先ほど説明にもありましたように堤防上に施設整備を行いますが、やっぱり堤防の強度を弱めるようなことは絶対あってはならないと思いますので、この盛土でより強化する。ただ、上に乗せるものがあまりにも多くなりすぎると本当に強度が足りるのかっていう問題もあるので、そこは相談しながらやっていくということです。
(記者)
盛土するっていうのは強化にもなるんですね。
【市長】
リバサイトのイメージ図でも盛土をして河川施設を整備するという絵もあるので、オッケーになっています。
(記者)
小野市さんが桜並木の関係でかわまちづくりに取り組まれていますよね、こういう活用バージョンみたいなものでしょうか。
【市長】
県内の先行事例では小野市さんの桜並木かなと。かわまちづくりって、比較的に田舎の方にあるのだと思ってるんですけど、加古川は駅に近いところでこれだけの面積があるので、ちょっと規模の大きな事例になるのかなと思っています。
(記者)
そして、市長が仰っていた通り、資源としては非常に潜在力のある、 駅も近くて、神戸、阪神間にも近く、自然の魅力って、やっぱり加古川のコンテンツとしては、もうこれを使うしかないっていうことですかね。
【市長】
そうですね。実際、これまで何もなかった場所に民間の方の力を借りてするものですから、地方創生の最たるもので、成功させたいなと思っています。
(記者)
メインターゲットが若者と子育て世代ということなんですけども、回遊性ということで歩いて来てもらって、基本的には市内外を対象ということですか。
【市長】
そうですね、市内外ですね。
(記者)
あくまで歩いて来てもらうみたいな感じですか。なんか加古川って、自転車のイメージがありますけども。
【市長】
イベントがこのバイパスとJRの間でたくさんあります。ムサシさんご自身も土日は朝市でたくさんされると思いますからね。あとは、ニッケさんの駐車場にあまりご迷惑をかけられないので、やはり河川敷にも駐車場はきちんと整備していきます。
(記者)
優先交渉権者は、かわまちづくりの拠点整備のために結集したとかいうわけではない。
【市長】
いえ、そのためにグループ(コンソーシアム)を作られていますね。
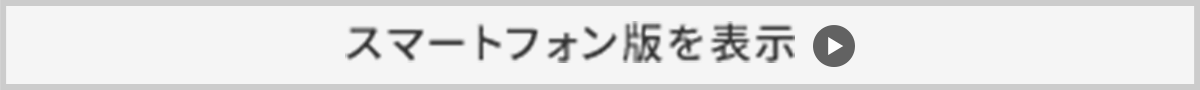








更新日:2024年09月12日