4件ということなんですけれども、それ以外になりますが4月16日に雹が急に降ってきましてですね。翌朝の9時からコールセンターや特設窓口を設けたりして対応しているんですけれども、 本当にたくさんのお問い合わせをいただいているという状況になります。
4月17日から4月23日までで集計してみましても、コールセンターへの問い合わせ件数だけでも1,614 件で、また特設窓口を1階に設けておるんですが、そちらの方にお越しいただいている方も列ができている時もありまして、23日までで1,186件とかそういうような状況になっております。
当初は件数も落ち着いてくるのかなと思いまして、今週限りで対応を終えようとも思っておったんですけれども、まだまだやはりその証明書、罹災証明とか被災証明とかを取られて何日かかかりながら補償の申請をされていくのでしょうし、まだまだ問い合わせが続きそうだという件数ですので、それぞれまた今日改めてリリースさせていただくことになっているんですが、窓口などの延長を発表させていただこうと思っています。またそれは別途プレスリリースさせていただきます。
みなさんとともに取り組むまちづくり
それでは、今日の4件に入らせていただきたいと思います。
まず1件目はお手元にみなさんとともに取り組むまちづくりと題したものが置かれているかと思います。これは近年ずっと続けてきております、補助金制度を通じて市内のいろんな団体の事業を応援させていただくという分です。プレスリリースの内容というところの真ん中あたりに採択件数32件の内訳を書いておりますように、いくつかのその型というか区分があるわけです。この型はここ数年変わっていないんですけども、この詳細も次のページからついてるかと思います。これ1番左の区分というところが表の方にあると思うんですけども、そこがこのプレスリリース表面の型というところと対応しています。簡単に申し上げますとホームページにもくわしく出ていますが、地域協働型といえば地域の例えばPTAや町内会などの団体が複数連携して取り組むような事業を応援したいので補助するものです。スタート応援型は2種類ありまして一般枠と学生枠とあります。一般枠は3年未満の事業に対して補助をさせていただくとしていて、もう1つの学生枠っていうのは人材育成の観点を兼ねてですね、補助率100パーセントとしておりますけども、20万円までお出ししますというかたちで学生の皆さんのチャレンジを本当に応援しようというものです。テーマ設定型というのはここのところのテーマとしましては、かわまちづくりのテーマを掲げていますので 、河川敷の空間を使ってイベントなどを開催していただける団体に100パーセントの補助率で100万円まで補助しますというやり方をしています。 課題解決型というのも2種類ありますが、行政提案枠というのは私たちの方から提案をしているわけでして、 いくつかの課が自分の課の所管する事業内容に応じたものを提案しています。例えば、認知症高齢者の支援に関する事業は何かありませんかとか、スマートシティを実際に実践しませんかとか、あと、婚活どうでしょう、 障がい者スポーツの普及とか、男女共同参画とか、LGBTQ+などそれぞれの課から提案するかたちで事業を募り、実際に提案があったものを形にしていこうとしています。
最後は市政全般いろんなことをしておりますので、総合計画などの中にあるようなことについて、民間の皆さんから提案のあった事業を審査の上で受けていこうとしているところです。やり方としましては昨年度中にですね、12月以降ぐらいで事前相談期間などを経て、相談に乗りながら実際提案をしていただいて、公開の場でのプレゼン審査を経て選んでいます。それらを予算の中に数字を詰め込んだかたちで3月までの議会で議決をいただいて、4月から実行できるというかたちにしているものです。特徴で言いますと、今回はスタート応援型の学生枠が昨年度1件だったのが4件に増えているいうところがあります。内訳を見ていただいたらと思うんですが、No5、6、7、8あたりですけども、兵庫大学や加古川南高の学生になります。また、32件のうち新規提案件数としては12件です。
テーマ設定型のかわまちづくりの分については、今年度でもう4回目同じやり方で取り組んでいることになりますけど、ハード整備もいよいよ動き始めている関係もありまして、この6年度に関しましては11月以降はちょっと事業ができない場所になるということで、今年度は5月から10月の間にぎゅっとこう開催日に詰め込んでいただくという調整をしてきております。昨年度もですね、かわまちづくりを国土交通省さんと一緒に進めているわけですが、例えば加古川バイパスからすぐ南のところの堤防の内側は国交省さんが階段状に座って、例えばソフトボールとかの観戦できるとかですね、そういうふうな堤防の内側に工事をしてきてくれてましたり、また河川敷に降りるスロープが南から行くとV字にかなり明確に右に曲がらなきゃいけなくて、曲がりきれないという声もあったので、ちょっと幅を広げてすごく改修していて、そういうのも動いてきてました。
一方で、市の方でも河川空間内の設計なども進めてきていまして、例えば河川敷の中の駐車場とかトイレとかの設置部分の設計も、この6月末までと申し上げながら、その後工事をしていく流れです。
また、ニッケさんのすぐ横になります堤防の高いところにですね、提案を募集して、お店などの施設誘致をしていこうとしていることにつきましても1月から募集開始をしています。昨年度の1月から募集を開始していまして、参加表明も得た上で今、事業者において詳細提案を進めておられるとのことです。 夏前には提案をいただく事になりますので、順調に決まれば7月にはこの事業者の提案というかたちで優先交渉権者というかたちで決まり、その後詳細をこう総合的に作って動き始めるというかたちになります。
子宮頸がん(HPV)ワクチン対象者に接種券を発送しました
2件目ですが、子宮頸がんワクチン対象者に接種券を発送しましたというふうにしております。こちらのリリースの表面にいろいろ書いておりますが、もうご存知の方も多いと思うんですけども、そこの内容にもありますように、元々は平成25年度に国の定期接種の対象になっていたんですが、その直後に副反応が懸念されるようになって、接種自体はできる状態だったと思うんですけど、積極的に行政が勧奨するのをこう控えてきているという状況が続いてました。そこがまただんだんやっぱりこのワクチン効果があるぞみたいなことは医療関係者もよく仰ってて、そういう流れの中で積極的勧奨を再開するというふうにまた方向性が変わった。これ全国的なことです。 ということで、行政から積極的な勧奨を受けられないままにその打つべきタイミングの年齢を過ぎてしまった方っていうのが一定数いらっしゃるので、その学年の方々に順次そのキャッチアップ接種ができますよ、ということで接種券を送付してきております。それで、今年度早々ですね、4月12日に発送しています。この高校2年生相当の年齢の方々約880人をもってそのキャッチアップ対象となるべき方の接種券の発送を一通り終えますということです。
広報かこがわをリニューアルします
3つ目にいかせていただきます。広報かこがわをリニューアルしましたということで、今日はサンプルも配付させていただいておりますが、変更点などはまさにそのプレスリリースに記載をしておりますとおりで、表紙のデザイン・ロゴを一新しております。また、構成というかですね 、それにつきましても8ページから9ページにかこすくひろばという子育て支援に特化したようなところをしっかりPRしたいということで特集ページを設けておりましたり、後ろの方になりますが29ページで縦になっておりますが、右側のかこがわスナップというところ、市の公式Instagramと連動して投稿されたこの市内の写真を紹介するとか、かこがわドリルっていうのも同じページにありまして、子どもも一緒に見て楽しんでいただけるようなきっかけにならないかなということで簡単なクイズがあったりします。また、29ページでかこがわドリルの月替わりでやるみたいなんですが、わたしのがっこうというコーナーがあります。6月号では、両荘みらい学園を特集にしようということになっております。
令和5年度 市民意識調査の報告書がまとまりました
4つ目なんですけれども、市民意識調査の報告書がまとまりましたのでホームページ上で公表してまいりますという件です。これはもうずっと続けて平成28年度から毎年やっている分で、満足度重要度調査などが主なものです。要は47テーマについて市の総合計画で進めているような取り組みのPDCAに使いたいという思いもありまして、その47項目で市民の皆さんが満足されていますかっていう満足度を聞いたり、またその分野についてどれぐらいあなたは重要だと思っていますかというふうなことで、重要さの推移を見ながら改善を図る予定です。
またそこに加えて、ここ2年なんですかね、ウェルビーングの調査を足しています。これは国が旗を振ってくれている地域幸福度っていうのを測ろうとするものでして、LWCIって略されますけれども、私たちもその市民の皆さんの幸福増進を念頭に置いていますので、まさにこれだという思いで連動して動いておりまして、国は国で全国的に、例えば去年でも8万5,000人ぐらいの方に地域幸福度調査のアンケートが実施されていまして、加古川市の方も450名ぐらいがたまたま対象になってたんですけど、市としては450じゃちょっと誤差も大きいので、改めてこの満足度調査に合わせて、一緒に地域幸福度調査のアンケートも差し込むかたちで、ここ2年聞いてきています。
ただ1つのアンケートにですね、地域幸福度の質問紙をどばーっと付けてしまったまま、満足度の前にボンと質問紙を足してしまったことで、ちょっと去年なんかはですね、ずっとやってきていた満足度と重要度調査の質問紙の前に、数十問のアンケートも入れてしまったんで、全体で180問みたいになってしまって、ちょっとアンケート疲れのせいなのか、満足度調査が軒並みとちょっとこう下がったような年になって、他に実際の原因があるんだろうかということでいろいろ振り返りもしたんですが、ひょっとしたら聞き方が変わったことによるものかななんていう話もしていました。いずれにしても数字は常に真実なのでその人の気持ちを表していますので、聞き方を統一というか安定させた状態で構成をしていかなきゃいけないっていう過渡期みたいな状態です。
この令和5年度分もですね、その幸福度調査が入ってから2回目になったんですけども、それに合わせて質問事項は減らしたんですが、依然としてこう100問超えみたいなかたちだったと思うんで、今年度6年度以降においては、アンケートを分離していずれにしてもどちらも無作為抽出で送りますので、満足度調査はまた分離したかたちで28年度以来やってきてたやり方に戻しながら、幸福度調査は別に分離して質問事項も減らしたかたちでやり続けていきたいなと思っています。
今日はお手元に少しカラーも入ったかたちでコピーを一部焼かせていただいています。丸々はホームページにございますので、例えば最初にありますのは、まちづくりの指標一覧いうことで、さっき申し上げました47の指標、一部二行同じのは体系だったりするんですけど47からの指標の満足度です。
見ていただきますと今申しましたように、令和4年度は質問紙が膨大になったので満足度が軒並み落ちています。令和5年度も同じような聞き方でもあるんですが、また下がって水色つけているのが多いというのは真摯に受け止めて、今後の施策で改善を図っていかなきゃなというふうに思っております。
オレンジ色のところは上昇の方ですので、見方としましてはこの表の最後2ページの1番下に米印で網掛けして色を付けているところは標本誤差2.16パーセントを超えて表したものを書いていますように、統計学的にはですね、25万人の人口規模18歳以上の対象ですから、もっと対象は少ないですね。その対象に対してこの2,000ほどの標本数がとれています。6,000人に送って2,034票回答していただいていますので、2,000のサンプルを取れていればですね、誤差の範囲としては2.16パーセントぐらいですので、そこの範囲の上下であれば誤差の範囲かなとなってはいけないんですが、そこを超えてこう前年度上がって下がってるところに付いてると思います。
その後にもう少し棒グラフなどがございますが、割と関心を持って見ていますということなんですが、定住意向についても 4つの選択肢があって住み続けたいとか移りたいけど市内ということで、このオレンジと水色がその2つなんですけど、じわじわ増えてきています。令和5年度も令和4年度よりはじわっと増えたんですが、これももちろん多少誤差もありますので、前年度比で言えば1.1パーセント増ですから、誤差の範囲でたまたま上がって見ているのかもしれませんが、2・3年前と比べると明らかに統計学的にも上昇と目立てられるというかたちになってきている数字ですので、近年いろんな広報宣伝には特に力を入れています。他市に負けないようないろんな取り組みもしてきていますので加古川に住み続けようかなっていう人もパーセントが増え続けてきているというふうな良い方向で見ております。
また、郷土愛、自分の地域に誇りや愛着を感じますかいうことも聞いていまして、これもポジティブなのが水色とオレンジちょっと上の色が違ってすいません。水色とオレンジがポジティブですけども、直近よりはじわっと少し合計値は下がっていますが、誤差範囲のレベルでして、過去に比べれば高まってきてるんだろうなというふうに思っています。
続いては、幸福度と認知度という棒グラフでのグラフがあるかと思いますけれども、これはですね、幸せ度がじわっと高まっているところもあります。その次のページにいっていただいてもいいかなと思うんですけど、こういう幸福度の全国っていうちょっと大きくした棒グラフがありますが 、右側はですね、先ほど申しましたように、国が8万5,000人ぐらいだったと思いますが、全国の方にアンケートを取られた対国民向けの幸福度調査で平均値が6.5ぐらい幸せだと。10がめっちゃ幸せで0は幸せではない。加古川市が改めて2,000人ほどアンケート結果を得た数値からすると、こうなっているので若干高いというふうに言えるかなと思っています。
ただ聞き方がですね、私たちは極力偏りが出ないように無作為抽出でアンケートをパサっと送って返してもらってるんですけど、国の調査の8万5,000っていうのは、どうやらその具体的なサイトは知りませんが、登録されているモニターさんみたいな人に8万5,000のアンケートをとっているらしいんで、そこらあたりからするとひょっとしたらなんかアンケートに答えようとする意識の高い人だったりとか、特定の年齢層による可能性はひょっとしてあるのかなとは思っていますから、厳密にこれと比べて全国的よりうちが幸せとかみんな言ってくれていると言っていいかどうかっていうところはちょっとまだ冷静になれないのかなとは思うんですけども、そういう結果でした。
さっきのページの認知度のところでは、あの手この手と広報宣伝をやってきまして、認知度が高まってきているような部分も見えます。特に、スマートシティは青がびゅっとこう伸びた形になっているところは意識して広報宣伝したようなことがありました。確かに我々の満足度などを聞くわけですけども、何をやっているかがそもそも伝わっていなかったら、その正確というかなんというか聞く意味すらなくなってしまいますので、とにかくこうもう年々やっていることを繰り返しお伝えしていくことをひたすらやらなきゃいけないかなというふうに思っています。その上でその中身について満足をいただいて。
国で配慮してもっと大きく取られてやるべきことだと思ってるんですけど、要はその皆さんが最初の質問紙であなたは10段階でどれくらい幸せですかっていうのを問うてまして、8と答える人もいれば2と答える人もいるという状況で、その続きの質問の中でですね、いろんな分野のことを問うてます。例えば、ここでいう健康状態っていうのが0.44となっていまして、相関係数っていうのが0.4を超えているわけですけども、これはもう前年度も高かったんです。 要は健康だと答えている人ほど幸せだと答えている、不健康だと答えている人ほど不幸せだと答えている、そのグラフの相関関係が統計学的にも強いというふうに見えております。ですので、ここでも例えば自己効力感っていうのが高かったり、住宅環境というのも0.4ポイント増えてるんですけど、 いわゆる自己肯定感が高い人ほど自分は幸せですと積極的に答え、また居心地の良い住環境を持っている人ほど幸せだと答えがちである。公共空間っていうのが4番目の0.35で前年度では公共空間も0.4を超えていたので、0.4っていうのが1つの相関があるといっていい境目といわれているんですけど、こういうことも見えてきました。私たちとしては、例えば自己効力感っていうのがですね、相関係数が高いので、教育委員会で協同的探求学習とかっていう前からやっているんですけど、そういうのでこう自己肯定感の高い子どもが育ってくれるはずだと思って現場でしてくれていますが、そういうことが大事になって目指す形になっていると思いますし、また文化芸術は今回0.31になっちゃったんですけども、去年は0.4超えてきていまして文化芸術に日常的に親しんでらっしゃる方が幸せだという方が多いというのもありますので、音楽のまちとかですね、そういうことを積極的にやっていくのが1つの根拠にできるのかなというふうに思います。
ちょっと4つ目長くなりましたけども、調査結果が出ましたので冷静に見なきゃいけないこととか真摯に受け止めなきゃいけないこととか改善を図らなきゃいけないこととか、今後しっかりやっていきたいと思っています。
そうしましたら、ご質問の方よろしくお願いいたします。
質疑応答
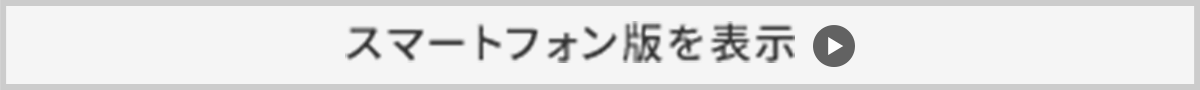








更新日:2024年05月14日