はまっ子の様子2022(1~3月)
3月24日(金曜日) 令和4年度修了式
昨日は卒業式が執り行われ、6年生106名が中学校へと旅立っていきました。
そして今日は修了式。1年生から5年生、各学年の修了の日です。
まずは、修了証を各学年の代表に手渡しました。

そして、学校長より。
「私は卒業生全員にアンケートをとりました。
1.コロナ禍での3年。嫌だったり、辛かったり、困ったりしたことはありますか。
★はじめの方は、行事がすごく減ったこと。
★給食が班にして食べられなかったこと。
★マスク生活で友だちとコミュニケーションがとれず、仲良くなるのが難しかったこと。
2.コロナ禍になったけど・・・よかったと思うことはありますか。
☆学級閉鎖のときでも、みんなとオンラインでつながれたこと。
☆グーグルミートができるようになって、学級閉鎖でも授業があったこと。
☆クロームブックを貸してもらえて、授業でわからないことがあっても、すぐに調べやすくなったこと。
☆手洗いをたくさん行ったり、マスクをつけたりして、自分で健康に気をつけるようになったこと。
☆今まで当たり前だったことが当たり前でなくなり、いろいろなことに感謝できるようになったこと。
このように、コロナ禍でありながらも、先輩たちは『あれできない』『これいやや』と後ろ向きに考えるのではなく、しっかりと学びを深めていて、大変感心しました。
5年生をはじめ、はまっ子の皆さん。
先輩たちがコロナ禍でありながらも、残してくれたよき伝統、よき遺産を受け継ぎ、4月からさらに素晴らしい浜小を作っていきましょう!」

次に、生活指導担当より。
「『教室でプチハッピーを見つけましょう!』という先生の話を覚えていますか。」

「みんな、プチハッピーがどんどん貯まって、『メガハッピー』になったと思います!」

「みんなで言ってみましょう!」
「メガハッピー!!」

「明日から、春休みが始まります。何よりも大切なのは『命』です。次の学年を気持ちよく迎えられるよう、次のことに気をつけて、春休みを過ごしましょう。」

「事故に合わないように。
交通ルールを守って。地域での自転車の止め方にも気をつけましょう。」

「事件に巻き込まれないように。
そのためには、地域の方々に顔を覚えてもらえるように、日頃から挨拶をしましょう。」
「インターネットを使うルールも守りましょう。
便利ですが、危険を伴うことは、何回も知らせて来ましたね。
『はまっ子憲章』を思い出して、上手に利用しましょう。」

「心の健康も大切です。
学校でもいいし、先日配ったプリントに載っていた相談できるところでもかまいません。
困ったり悩んだりしたときには、誰かに話してみましょう。
悩みがあることは、恥ずかしいことではありません。」
全校生が、自分の、そして周りの命を大切にし、この1年を終えられること、そして次の学年を迎えようとしていること、教職員一同、とても嬉しく思っております。
4月7日、新たな学年になり、胸を張って登校して来る子どもたちを迎えるのがとても楽しみです。

今年度最後の、全員での校歌斉唱。
5年1組からの配信に合わせて。
卒業式に向けての毎日の歌唱練習の成果が出て、素晴らしい歌声でした。
3月23日(木曜日) 卒業証書授与式
3月23日(木曜日)、卒業証書授与式を挙行いたしました。


未だコロナ禍の名残りはありますが、それでも卒業生は、実に3年ぶりに校内でマスクを外し、凛々しく、逞しくなった表情を見せながら入退場を行うことが叶いました。
また、5年生は教室でオンラインにて式の様子を視聴し、校歌の際には体育館を囲み、6年生とともに斉唱しました。そして、来年度に向けての心構えを高めることができました。

学校長式辞より。
「皆さんの小学校生活のうちほぼ半分の時間が、あらゆる活動に制限のかかる、思いも寄らない日々となってしまいました。
ややもすると、毎日の学校生活に価値を見い出せないときもあったでしょう。でも、皆さんは、本当に諦めず、『できる工夫』をもって突き進んでくれました。
その一つが、委員会活動です。オンライン配信を、また学校放送を活用し、時には感染対策に留意しながら対面の場も設定しながら、楽しい企画を次々と提供してくれました。日々の当番活動も実直に行ってくれました。皆さんの、このような真摯で前向きな取組は、きっと今後の浜小の『正の遺産』として、下級生に受け継がれていくことでしょう。」

「ここで、私が日々大切にしている言葉を、皆さんに送ります。それは、『成功より成長』、この言葉です。
うまく行かないことはあって当たり前。たとえ失敗しても、つまずいても、その出来事は、時間は『全てが成長のために必要なもの』と捉えましょう。
目先の成功にとらわれず、昨日より今日、今日より明日。努力した結果として得られる日々の成長こそが、皆さん一人一人の本質であり、大きな財産となります。」

社会はグローバル化に向けて日々進展し、またICTの進歩が、その社会の変化をさらに加速させています。このように、激変の時代を生き抜かなければならない。それが卒業生、106名です。
この予測不能な難しい時代であっても諦めることなく、「成功より成長」を胸に刻み、自分を高め続けられる人であってほしいと職員皆が願い、今後も応援していきます。



式会場の様子。
会場壁面には、「旅立ちに向けての『自分へのメッセージ』」を掲示しました。
一字一字丁寧に、毛筆で丁寧に書き上げました。


6年生の教室、廊下にも、本校職員からの熱いメッセージが掲げられました。
3月7日(火曜日) 盲導犬体験学習(5年)
盲導犬、そして盲導犬候補の子犬を預かるボランティア「パピーウォーカー」を迎え、盲導犬の仕事ぶりについて学ぶ体験学習を、5年生が行いました。
5年生は、総合的な学習の時間に「街づくりプランナー ~住みよい街をめざして~」と題し、ユニバーサルデザイン等を知るとともに、皆が暮らしやすい共生社会について学習を進めているところです。
今日は、実際にパピーウォーカーが子犬を育成しているときのエピソードをうかがったり、盲導犬と触れ合い、かつ歩行体験を行ったりすることで、補助犬の社会における貢献度を学び、そこから共生社会に向けて自分たちができることへの学びを深めました。
なお、この取組については、日本ライトハウス盲導犬訓練所のご協力のもと、学校と地域が協働した福祉教育推進のために、社会福祉法人加古川市社会福祉協議会が推進する「地域が育む福祉教育推進パワーアップ事業」の助成によって実施しております。
ゲストティーチャーの皆様です。

パピーウォーカー等、盲導犬に関するボランティアを20年以上続けられている松田様ご夫妻と、日本ライトハウス盲導犬訓練所の赤川様が来てくださいました。

松田家で生活し、盲導犬の繁殖犬として4回、28頭のお産をし、共生社会に貢献しているキルトちゃん。(9歳)

日本ライトハウス盲導犬訓練所のデモンストレーション犬(盲導犬の広報担当)のジョアくん(7歳)。キルトちゃんの息子です。

パピー(盲導犬になるための子犬)の生い立ちや、盲導犬の社会貢献について、紙芝居で教えていただきました。


視覚障がいを持つ方々の状態や支援の在り方等、赤川様から教えていただきました。

総合の時間にかなり調べていたため、質問もたくさん出ていました。

一部の児童は、歩行体験もさせていただき、英語での指示にチャレンジしてみました。

「盲導犬などの補助犬の役割がよくわかりました。ありがとうございました。」
代表児童がお礼を述べました。

5年生全員、すぐにお礼の手紙を書いて郵送し、学びの成果と感謝の意を伝えました。
3月1日(水曜日) 6年生を送る会
3月23日木曜日には、6年生の卒業式があります。
卒業式は、
「義務教育6年間を終了されましたね。おめでとう」
という多くの方からお祝いをいただく意味と、もうひとつ、6年生については、
「家族や学校、地域の皆さんのおかげで、無事に義務教育が終えられました。ありがとう」
という感謝を表す意味、その両方があります。
その卒業式には、残念ながら、1年生から4年生は出席し、お祝の場をともにすることはできません。
その代わりとして本日、「6年生を送る会」を開催しました。
今日に向けて各学年、心を込めて寄せ書きを作りました。
そして、このメンバーで歌うのも最後ということで、浜の宮小学校の児童であることを誇りに思い、校歌の練習を2ヶ月間続けて来ました。
3年以上をコロナに振り回され、自然学校さえ完全に行うことのできなかった6年生。友情を最も育みたい高学年の時期に、長い休校も経験しました。
それでも、行事や情報の発信など、自分たちにできることを探して、「知恵」と「工夫」を校内にもたらしてくれました。
6年生になってからは、『目を見て、おじぎ、聞こえる声で』の挨拶、『だまピカ掃除』など、常に正しい態度で礼節を示し、良き足跡を残してくれました。
卒業まで、あと15日。
最後の1日まで、はまっ子の代表として、胸を張って正しく過ごし、在校生に良き範を示してくれることでしょう。
浜っ子バンドの演奏「聖者の行進」に合わせ、6年生が入場!
中庭を取り囲んだ1~5年生が、拍手で迎えます。


各学年から、一言メッセージとともに、寄せ書きが手渡されました。

1年生

2年生


3年生


4年生

5年生
5年生と6年生の児童会委員による、「新旧引継ぎ式」も行われました。
「浜小をよろしくお願いします。」
「『目を見て、おじぎ、聞こえる声で』の挨拶、『だまピカ掃除』など、浜小の良き伝統をこれからも守っていきます。」


最後に、皆で心をひとつに「校歌」を全員で、声高らかに。
2ヶ月の練習の成果を発揮して!

退場のときには、校舎から『ご卒業おめでとうございます』のメッセージボードが!!
5年生からのサプライズです!!




5年生のみなさん。
児童会委員を中心に、今日の企画、運営をありがとう。
皆さんも、素敵な最上級生になれそうです!!
卒業に向けて・・・その2
~在校生のために運動場を整えました~
6年生は先週から、運動場に新しく入った土を運び、均す作業を行っています。

運動場の土は、雨風や、体育等の日頃の活動により、確実に減っていきます。
そこで、新しく入った土を運び、均し、整えるのが、本校では6年生の卒業前の作業となっています。
奉仕作業には、「特別の教科 道徳」の価値項目である「勤労・奉仕」「感謝」等、様々な学びの獲得が期待できます。
そして何よりも、「愛校心」を持って、周囲の人々に感謝し、卒業してほしいと望んで、取り組んでもらっています。

鉄棒やブランコ、遊具の下にもフカフカの新しい土を入れ、これで低学年の活動も怪我の心配をせず、安心して活動できそうです!
卒業に向けて・・・その1
~色紙に思いを込めて~
6年生は現在、卒業に向けて、「自分へのはなむけの言葉」を毛筆で色紙に書くため、その練習に取り組んでいます。

3年前、新学習指導要領が大きく改訂されたように、教育課程については国をあげ、約10年毎に社会の状況に合わせて修正が繰り返されています。それでも「書写」の学習は、50年以上もの間、必修科目に位置付けられ、削除されることなく残っています。
グローバル化が加速度的に進行する現代社会においては、国際社会に貢献できる人材を必要としていますが、その人材には「書写」を代表とする日本の文化や伝統を知り、それを発信できることが求められます。
今回、まずは日本における毛筆の歴史から復習。
「600年頃、中国から伝わりましたね。」
「かな文字は、日本で平安時代に生まれた文化です。」
「日本の文化を知ることが大切です。」

そして、筆を運びます。
教師の指導に真摯に耳を傾け、枚数を重ねるごとに字形も筆使いも整っていきました。


仕上がった色紙は、卒業式会場の体育館に全て掲示される予定です。
2月20日(月曜日) 認知症サポーター養成講座(5年)
5年生は、総合的な学習の時間に「街づくりプランナー ~住みよい街をめざして~」と題し、ユニバーサルデザイン等を知るとともに、皆が暮らしやすい共生社会について学習を進めているところです。
その一環として、2月20日(月曜日)には、「認知症サポーター養成講座」を実施しました。
認知症の方やその家族の支えとなるまちづくりに向け、専門の研修を受けた「キャラバン・メイト」を加古川市が派遣し、講座を開催してくださる取組です。
認知症は誰もが発症しうる病気です。認知症になっても、またその家族の立場になっても、安心して暮らせるまちづくりが大切です。その次代を担う子どもたちが、認知症への正しい知識と、適切な接し方を学ぶ有効な機会となりました。



「認知症って何?」
「どのように接したらいい?」
まずはそこから、正しく学んで行きます。
「誰でもなる可能性があるんだね。」


「もし、まちで認知症の方と出会ったら・・・?」
担任の先生も一緒に、ロールプレイで、対応のしかたを学びます。

講座終了後には、「認知症の方を支援します」という意思を表示する「オレンジリング」が贈られました。

キャラバン・メイトの皆さん、貴重な学びの時間をありがとうございました!
2月14日(火曜日) 全校朝会
2月の朝会です。
まずは、校歌斉唱からスタート。
3月1日の「6年生を送る会」でも、全校生で校歌を歌うことが決定し、最近は朝の時間に歌唱練習している学級が増えています。

配信は5年2組から。
良い姿勢で、しっかりと歌う姿勢が皆の手本となりました。
続いて学校長から。
「2年生の靴箱は、通るたびに写真を撮りたくなるほど、とても美しく揃えられています。
たかが靴箱、されど靴箱・・・。
2年生の皆さんの、整った心を表しているのでしょうね。」


と、全校生に紹介しました。
このように、「健やかな心」「豊かな心」に向けた成長は、日々の暮らしぶりに表れます。
校内造形展を終えて・・・
2月6日(月曜日)~8日(水曜日)、校内造形展を開催しました。


入口には付箋を貼るスタイルで、「ひとこと感想」をちょうだいしました。
ここに紹介するとともに、来年度の開催に向けての参考にさせていただきます。
★今年も素晴らしい造形展へのご招待、ありがとうございます。私を含む保護者一人ひとりに、喜びや嬉しさ、楽しさがこみ上がって来たことと思います。製作に取り組むみんなの姿を想像しながら、楽しく拝見しました。
素敵な機会をありがとうございます。来年も楽しみにしています。
★学年が上がるごとに難しいものにチャレンジしていて、とても感動しました。
作品を見る順路も特に決まっておらず、自由にゆっくりと鑑賞することができました。
★どれも心のこもった作品で、見ているこちらの心が洗われました。一生懸命製作している子どもたちの顔が浮かび、胸が熱くなりました。
★作品から力強い「元気」「パワー」をいただきました。子どもたちの力作に感動です。
造形展の開催、ありがとうございました。
★本日、2度目の鑑賞です!本当に素晴らしいです!!
★1,2年生とは思えない成長が感じられました。
3年生の「りゅう」の細かな作業、お面の質感がとてもよかったです。
★私もそうですが、3年生の子どもが高学年の作品を見て驚き、「スゲー!」「ムリムリ!」と叫んでいました。
★どの作品にも、子どもたちの素晴らしい発想が込められていました。特に目をひいたのは、なかよし学級の「陶芸」です。


2月7日(火曜日) 第3回授業参観
2月7日(火曜日)に、今年度3回目の授業参観を行いました。
昨年度はこの時期に、緊急事態宣言が急きょ発令され、参観日を中止することになってしまいました。
今年度は3回目も無事に決行でき、地区ごとに参観時間を分けるなど感染症対策には変わらず万全を期して、各家庭2名までご来校いただきました。

なかよし学級は、絵画でこの1年間を振り返りました。

1年生の「できるようになったよ」発表会。
大型モニターを使って、できるようになった折り紙を披露しています。

2年生の国語「かん字のくみ合わせ」。
Chromebook上で部首と部分を組み合わせ、漢字を作っていきます。

3年生の国語「これがわたしのお気に入り」。
Chromebookで自身のお気に入りを紹介するシートを作り、原稿を読んで発表しています。

4年生の道徳「うそってなんだろう」。
学習支援コンテンツ「スカイメニュー」の「ポジショニング」を活用し、「(場合によっては)嘘はついてよい」「嘘はついてはいけない」に分かれて意見交換を行いました。

5年生の算数「角柱と円柱」。
各自のChromebookで、デジタル教科書を直接操作中。

6年生の体育「サッカー」。
兵庫型学習システムの導入により、5,6年の体育、社会、家庭科・外国語は、担任3人でローテーションして授業を行っています。
2月は、そして3学期は早いです。あっという間に過ぎていきます。
進学・進級に向け、学習面・生活面ともに、よい締めくくりをさせたく、それに向けて取り組んでまいります。
2月6日(月曜日)~8日(水曜日) 校内造形展開催
2月6日(月曜日)~8日(水曜日)、校内造形展を開催しております。


昨年は直前に緊急事態宣言が発令され、鑑賞時間の制限など、保護者様をはじめとする外部の皆様にはご負担をおかけしましたが、今年度は感染対策に留意しながらも、ゆったりとご鑑賞いただいております。

なかよし学級「めざせ!陶芸名人!! ~世界に一つだけの作品~」

1年絵画「ちぎって はって 水ぞくかん」

1年工作「ごちそうパーティー」

2年絵画「ことばのかたち」

2年工作「くしゃくしゃ ぎゅっ」

3年絵画「物語の絵」

3年工作「ふしぎな仮面」

4年絵画「木版画 風の中の鳥」

4年工作「オリジナルウッドボックス」

5年絵画「地球を救うヒーロー」

5年工作「糸のこドライブ de かべかざり」

6年絵画「木版画de 自画像」

6年工作「My chair ~わたしだけのイス~」

浜の宮幼稚園の皆さんも参加。

50周年記念行事で製作した作品とともに展示されました。
子どもたちの製作意欲と頑張りと粘り強さが、体育館中に溢れ、素晴らしい空気感・・・圧巻です!!


来る!校内造形展!!
2月6日(月曜日)~8日(水曜日)
今年も、校内造形展を開催します。
昨年は直前に緊急事態宣言が発令され、鑑賞時間の制限など、保護者様をはじめとする外部の皆様にはご負担をおかけしましたが、今年度は感染対策に留意しながらも、ゆったりとご鑑賞いただけそうです。
1年生から6年生まで、図工の時間に取り組んで完成させた絵画と工作、両方を展示します。
なかよし学級の子どもたちが、生活単元学習で外部講師のご指導のもとで製作した「焼き物」も並びます。
浜の宮幼稚園の園児さんの作品も舞台上に展示される予定です。これによって、幼・小の円滑な接続を目指しております。
乞うご期待!!!です。

【鑑賞時間】
2月6日(月曜日) 12:30~18:00
7日(火曜日) 8:45~18:00
8日(水曜日) 8:45~12:00
【場 所】
本校体育館

1月19日(木曜日)
スクールカウンセラーにお話していただきました(6年)
卒業、そして進学を控えた6年生が、1月19日(木曜日)、本校のスクールカウンセラーからお話をうかがいました。
題名は「ストレスについて考えよう! ~みんなちがって、みんないい~」。
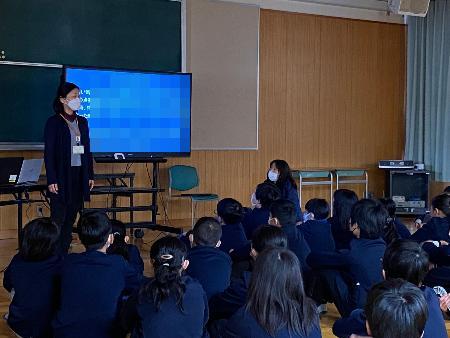
「みんな、ストレスの感じ方は違うんだよ。」
「相手は笑ってはいるけど、本当の気持ちと違うことがあります。」
と、『ストレスって何?』から始まり、
「うまくいかないときでも、それが成長のチャンスです。」
と、手なストレスとの付き合い方まで教えていただきました。
さらに、
「失敗をしたときに作戦をいっしょに考えていくのが、カウンセラーです!」
と力強いお言葉もいただきました。
スマートフォンを始めとするICTの進歩等、社会の変化は加速度的に進み、今後、社会はさらに変化すると予想されています。
予測不能な社会を生きていくこととなる6年生。
ストレスとうまく対処し、よき中学校生活を送れるようにと願っています。
1月17日(火曜日) 避難訓練・1.17集会
27年前の今日、1月17日は、阪神・淡路大震災が発生した日です。
この日を、この出来事を、そしてこの教訓を決して忘れることのないよう、今年も避難訓練と「1.17集会」を実施しました。
まずは避難訓練から。そして全員で、黙とうを行いました。

その後、教室に入って、「1.17集会」をオンラインで開催しました。
震災について語れる教職員も、ずいぶん少なくなって来ました。
今日は、当時ボランティア活動に参加した本校職員が、その経験を、当時の様子や目にした光景と合わせて、全校生に向けて話しました。

「この地震では、地震そのものだけでなく、火事で亡くなった方が大勢いました。
これが、最も火災の被害が大きかった長田の町の写真です。鎮火するのに、2日もかかったそうです。
私は、毎日のニュースを見て、親戚や友だちのいる神戸のことがとても心配になっていましたが、そんなときに『子どもたちの話し相手』という『保育ボランティアを募集していることを知り、2月の終わりから4月まで、毎日ひとりで長田に通いました。」

「2月はとても寒いです。
でも、人が多すぎて避難所に入れず、公園にテントを立てて過ごしている方々もたくさんいました。
大人は、住んでいた家の片づけや仕事で忙しく、子どもたちはとてもさみしそうでした。
『遊ぼう』と声をかけると、子どもたちが一斉にテントから出てきました。
鬼ごっこや縄跳び、おしゃべりをして、毎日過ごし、子どもたちにも笑顔が見られるようになりました。」

「公園の近くに、とある会社の社長さんがおられました。
お菓子を毎日取り寄せて子どもたちに配り、『子どもたちをよろしく頼む』といつも声をかけてくださいました。
長田の皆さんの、温かさ、力強さをとても感じました。」
学校長から。

「その後、この平成7年が『ボランティア元年』と呼ばれるようになるなど、自主的に困った人を助けようとする「ボランティア」という考え方やその活動が、日本中に浸透していったのですよ。」
最後にまとめとして、防災担当から。

「ぼうさいの基本は、
- 自分の身は、自分で守る
- できる準備をしておく
- 他の人と協力して生活する
今日の学びを、これからに生かしていきましょう。」
当時、神戸などを含む関西地方では、「地震は起こらない、起こりにくい」と言われており、危機感を持っていなかったのが実情でした。しかし、この震災をきっかけに、
・常に最悪を想定して、準備して生活すること
・自分の身は自分で守ること
の大切さを、日本の皆が学びました。
この2つの学びを風化させないため、忘れないため、学校では今後も、毎年1月17日には「1.17集会」を行っていきます。
1月17日(火曜日) 全校朝会
1月の朝会です。
今日は、3学期の学級委員長、副委員長の選任式からです。
2年から6年を代表して、6年1組の奥村昊平さん、平田英さんに、オンライン放送に出演してもらいました。

「委員長として、どんなことが目標ですか。」
「学校が楽しくないな・・・と思っている子がクラスにはいるかもしれません。その子たちが学校に楽しく来れるように、声をかけていきたいです。」

「副委員長として、どんなことが目標ですか。」
「小学校生活最後の学期なので、皆が楽しく過ごせて、また勉強も頑張れる学級にしていきたいです。」
その後、皆で校歌を歌いました。
もうすぐ、5年生、6年生は卒業式に出席します。特に5年生は初めての、正式な儀式出席です。
それだけでなく、愛校心を育むため、全校生で心ひとつに、ひとつのことに取り組むため、3学期は毎月校歌を斉唱することとしました。

配信は5年1組から。
お手本となるよう、しっかり歌う姿を見せられていました。
1月11日(火曜日) 書き初め大会
1月11日(火曜日)、校内書き初め大会を行いました。

一昨年度、新学習指導要領が大きく改訂されたように、教育課程については国をあげ、約10年毎に社会の状況に合わせて修正が繰り返されています。それでも「書写」の学習は、50年以上もの間、必修科目に位置付けられ、削除されることなく残っています。
グローバル化が加速度的に進行する現代社会においては、国際社会に貢献できる人材を必要としていますが、その人材には「書写」を代表とする日本の文化や伝統を知り、それを発信できることが求められます。それだけでなく、高齢化社会で重要視されている「生涯学習」の観点からも、「硬筆」「毛筆」は見直されています。
この日は全校生が私語することなく、一文字一文字集中して、鉛筆や筆を運び、自国文化に親しみました。
1年生「お正月」。
最後の色塗りまで丁寧に行いました。筆圧の向上に有効です。

2年生「ゆき」。
手本を横に置いて1行ずつ。反対側の手もしっかり添えて。集中して、絶対に消しゴムは使いません。

3年生「うめの花」。
初めて画仙紙に挑戦。文字の配置がとても難しいですが、バランスよくかけていました。

4年生「東のそら」。
朝一番の静寂時から、しっかり取り組んでいました。

5年生「春の山川」。
さすが高学年。全ての作品が並ぶと迫力があります。

6年生「太平の海」。
中学校では書写の授業がなくなります。それを踏まえ、「これでラスト!」と、皆が本当に黙々と画仙紙に向かっていました。



1月10日(火曜日)3学期始業式
今日から3学期です。
多くの職員は4日より出勤しておりますが、児童クラブに来ていた子どもたちが、自ら進んで、
「あけましておめでとうございます!」
と挨拶してくれ、
「新年早々、すがすがしい気持ちになった。」
と話していました。
始業式は、やはりオンラインで。
年末の新聞記事に、世界から注目されている日本の教育活動「TOKKATSU(特活)」のことが掲載されていたので、それを紹介しました。

「FIFAワールドカップのとき、選手たちの活躍だけでなく、応援に来たサポーターのスタンドのごみ拾いや、試合後の美しい選手のロッカーが、世界で話題になっていたことは、12月の朝会で話をしましたね。
このような日本人の礼儀やきまりを重んじる生き方は、「元々の日本の文化」だけではなく、「学校生活で身についたものだ」と、多くの国々から「TOKKATSU(特活)」と呼ばれて、今、大変注目を浴びているそうです。
教室の掃除や日直、委員会活動、給食当番などで、自分たちの生活を自分たちで成り立たせ、自然と規律ある行動が身につくこの取組がすばらしいと、大変称賛されています。
エジプトという国では、これを「日本式教育」として学校に取り入れているそうですよ。」

「このような、日本の学校が世界で認められていることに誇りをもって、自慢に思って、令和5年も学校を、友達を、先生方との時間を大切にして、日々過ごしていきましょう。」
次は、生活指導の先生から。


「命に関わること、クロームブックやスマートフォンのことなど、皆さんで解決できないことはたくさんあって当たり前です。
そういうときには、大人の人に相談できる力をつけましょう。」

「3学期の最後、修了式には、みんながメガハッピーになっていますように!」


長期の休み明けの朝、必ず6年生が自主的に前庭を掃き掃除してくれており、それがいつの間にか、浜小の伝統となっています。
このような「勤労・奉仕」「愛校心」という徳が、間もなく卒業する6年生から下級生へ、また引き継がれていくと嬉しいです。
あけましておめでとうございます!
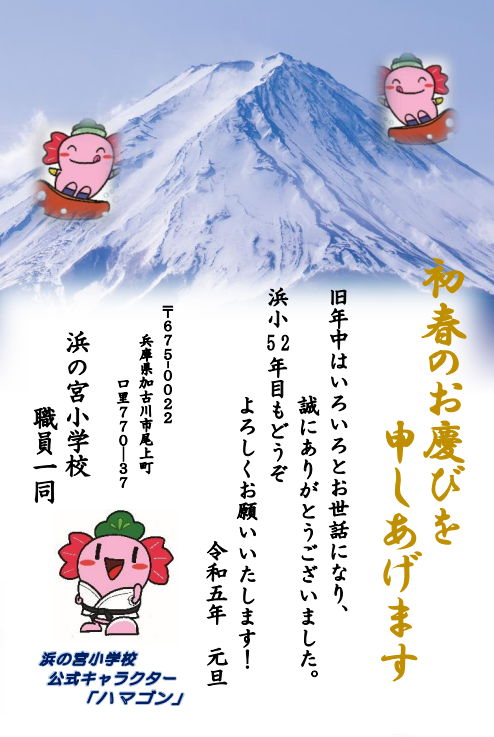
この記事に関するお問い合わせ先
郵便:675-0022
住所:兵庫県加古川市尾上町口里770-37
電話番号:079-423-2440







更新日:2023年03月25日