はまっ子の様子2022(7~9月)
9月27日(木曜日) かんきょう出前講座(3年)
現在、温暖化や自然破壊など地球環境の悪化が深刻化し、環境問題への対応が、人類の生存と繁栄に向けて、緊急かつ重要な課題となっています。
豊かな自然環境を守り、私たちの子孫に引き継いでいくためには、エネルギーの効率的な利用など環境への負荷の少ない、持続可能な社会を構築すること、そのためには、国民が様々な機会を通じて環境問題について学習することが大切です。
特に、21世紀を担う子どもたちへの環境教育は極めて重要な意義を有している、と言われています。
9月27日(火曜日)、「かんきょう出前講座」と題し、市役所環境政策課の方にお越しいただいて、3年生が「地球温暖化」等の環境問題と、その対策について学びました。
兵庫県では「環境体験事業」として、環境学習を行うことが県内統一で位置づけられています。
今回のテーマは、「クールチョイス」。
「『歯磨きのときは水を出しっぱなしにせず、蛇口を閉めましょう』
『使わない部屋の電気や、見ていないテレビは消しましょう』
『使っていない電化製品の電源プラグは抜きましょう』
温暖化を止めることは難しくても、緩やかにするために、小学生でもできることをしていきましょう。」
映像やクイズを交えながら、大変わかりやすく教えてくださいました。




今から80年後、2100年の夏の天気予報を予想。
なんとか、世界の平均気温上昇を1.5℃に抑える努力ができれば、
この気温で抑えられるらしいです。
それでも、高いですよね・・・。
9月27日(火曜日) オンライン児童集会
~いじめ防止啓発集会~
加古川市では、9月を「いじめ防止啓発月間」と設定しています。
それに向けての本校独自の取組として、児童会委員主催で「いじめ防止啓発集会」を開催しております。

例年は児童会委員のオリジナルストーリーによる劇によって、いじめのケースを提示していましたが、今回は日々活用しているChromebookから様々な情報を収集し、わかりやすく問題提起してくれました。

まずは、加古川市の「心の絆プロジェクト」児童会・生徒会代表者ミーティングに出席した児童からの報告。
「『いじりといじめの違いを知ろう』
『それぞれのいいところを認め合おう』
『相手がいやだと思ったら全部いじめです』
このことについて、他の学校の人と話し合いました。」
次に、サイトで見つけた記事の紹介を。

「朝日新聞デジタルの『いじめと君』というサイトで、美輪明宏さんがご自身の経験からお話されている記事を見つけました。
『いじめを見ているだけでは、いじめをしていることと同じです』
『いじめを見ているだけでは、後で後悔するでしょう。
まずは、声をかける勇気が大切です。』」



ここで、いじめに関する問題を。
「昨年、小・中・高等学校でいじめの起きた件数は?」
「中学校と小学校では、どちらの方がいじめが多い?」
「いじめが起きやすい教室の様子は?」
調べたデータをもとに、問題を作成しました。

さらに、友だちと仲良くできる方法について。
「でも・・・という逆説の言葉をいきなり使わず、まずは相手の話を受け止めましょう。」
「『ありがとう』と、感謝の言葉を伝えましょう。」
「明るいトーンで話しましょう。」

ところで・・・。
「いじめをしてしまった人にも、友だちのことや勉強のこと、家族のことなど、悩みや困ったことがあるかもしれません。
それにも気づいてあげたいですね。
そして、みんなが過ごしやすい学校を作っていきましょう。」
今回、児童会委員がChromebookで検索した情報をもとに、発表のシナリオを組み立てていたことに大変感心しました。
Chromebook等の情報機器は、ややもすると中傷等の書き込みに利用され、いじめ事案を生みかねない・・・という見方がされる場合もあります。
しかし、今回のように、的確かつ迅速に情報を集め、吟味し、周囲に発信する・・・。この上なく便利です。
今後も、その時代の風潮に合わせ、いじめの未然防止・早期対応に向けて教職員と子どもたちで力を合わせ、取り組んでまいります。
ミシンボランティアの皆さん・・・大活躍!
2学期は5,6年生が、家庭科の教育活動として、「ミシン」の使用、およびそれを用いた作品作りを行います。しかし、ここ数年の多様な教育課程の導入等により、家庭科に取り組む時間が非常に少なくなっており、担任の指導のみで技術を習得させることは非常に難しい状況となっています。加えて、見守りが少ないため、裁縫道具を使用した際の怪我等のリスクも想定されます。
そこで、今年度初めて、地域の代表者として民生児童委員の皆様、そして5,6年保護者様に向け、『ミシンボランティア』として児童の支援をしていただける方を募ってみました。すると、数名の方々が手を挙げ、早速支援にあたってくださっています。

引くコロナウイルスの感染拡大により、保護者様や地域の皆様とお出会いし、情報共有する機会も随分減っております。これを契機として、現在求められている学校と家庭、そして地域との連携が円滑に進むであろうと、大変嬉しく思っております。

6年生のナップサックづくりの様子。
ご自身のお子様がいる学級にこだわらず、すき間時間を見つけて来校してくださっています。

ミシンがけの前段階、チャコペンで縫う場所に印をつけるときから、ご支援くださっています。
自然学校に行って来ました!(5年生)
新型コロナウイルスのまん延状態が依然解消されないことを鑑み、市内全校2泊3日(本来は4泊5日)と短縮された自然学校。
本校も9月14日(水曜日)~16日(金曜日)、ハチ高原に行ってまいりました。
宿舎の方にうかがうと、例年にない、酷暑厳しい3日間になったようです。
それでも皆、熱中症には十分に留意しながら、また黙食を徹底したりお風呂での会話を慎んだりしながら、コロナ対策にも気を配りつつ、仲間との「宿泊」という初めての体験を楽しみました。
くじけそうなときは励まし合ったり、ぶつかりそうなときは譲り合ったり・・・。
人の温度を感じ、人と同じ空間を共有しないとできない、学校生活だからこそ提供される学びによって、今後、ぐんと高学年らしくなっていくことでしょう。

1日目のオリエンテーリング。
「暑いよ~!」
「でも楽しいよ~!!」

2日目の山のぼり。
「荷物、持ったろか~?」
そんな声も聞こえました。
自分もしんどいのにね・・・すごいな!

夕方からの雨により、キャンプファイヤーはキャンドルサービスに。
5年生のスローガン「真友(しんゆう)」の灯を灯しました。

3日目の沢のぼり。
全身がびちゃびちゃ・・・でも楽しい!
9月12日(月曜日) 自然学校1日目(出前学習)
新型コロナウイルスのまん延状態が依然解消されないことを鑑み、2学期の自然学校については市内全校2泊3日(本来は4泊5日)、あと2日は校内での実施と決定いたしました。
コロナに負けず、かつ十分な対策をとりながら、短縮されても自然学校ができることに感謝し、教師と子どもで、工夫した学びを生み出していきます。
できなかった2日分の活動は、校内で行うこととなっています。
出発2日前の9月12日(月曜日)、宿泊先でもあるハチ高原「ANNEXフォレストロッジ」から指導員の方にご来校いただき、宿泊に向けてのオリエンテーションが実施されました。
そしてその後は、一人一人「箸づくり」を行いました。
・温室効果ガスの削減に向けて、環境汚染につながるプラスチック使用を減少させようという世界的な取組の中、天然木や竹など、本来使われていた自然のもので製作し、その良さを感じる。
・自然を生かして生活してきた先人の知恵を知る。
このようなことが、今日の課題です。
出来上がった箸は、家でしっかり洗って、明日の給食時に使用する予定です。
あと2日で自然学校・・・。人の温度を感じてこそ得ることの学びの場に、いよいよ出発です!


まずは指導員さんから、自然学校の楽しいプログラムと、箸づくりの説明を聞いて・・・スタート!


皆、距離を保ちながら一方向を向いて。

ひたすら黙々と・・・。ナイフでけがをしてはいけません。油断は大敵。

出来上がった~!!オリジナルの工夫を取り入れて、「マイネーム」を刻印する子どももいました。
9月8日(木曜日) 相談行動促進学習(6年)
毎年、9月10日~16日は「自殺予防週間」と位置づけられています。
6日(火曜日)には、その啓発の取組のひとつとして、
「プチハッピーを見つけよう!」
「プチハッピーを貯めよう!」
を、オンライン児童集会で発信しました。

そして8日(木曜日)には、6年生が市のリーフレットを活用して、「相談行動促進」への学びを深めました。
「相談行動促進学習」として、
・自分の心の危機に気づき、相談する力を育てる
・友達の心の危機に気づき、それを受け止め、信頼できる大人に伝える力を育てる
ことの大切さを知り、理解する学習です。
まずは、心のビタミン「プチハッピー」を共有してアイスブレイク!

そして、今日の授業は「ペアでロールプレイをしよう!」。
「『テストの点、めっちゃ悪かった』と暗い顔で悲しそうにしている友だちに対して、どんな声かけをしますか。」
「その声をかけられたとき、どう思いましたか。」
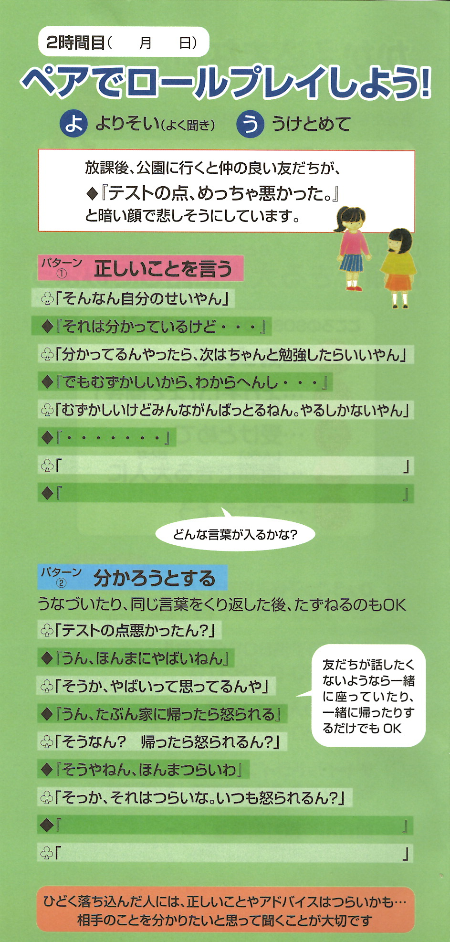
ロールプレイ(役割演技)で気持ちを確認し、ワークシートに書き込みます。

「確かに正しい」ことを言われたときは・・・。
「自分のこと、聞いてもらえないな。」
「ただでさえ、落ち込んでるのにな・・・。」
「威圧感あって、これからもう話したくないな。」

「あなたのことをわかりたい」と思う友だちに話を聞いてもらったときには・・・。
「なんとなく、すっきりしたな。」
「うなづいてもらえるだけで救われた気分だな。」
「私の言葉、繰り返してくれて、一緒に考えてくれてる感じがするなあ。」

「『励ます』『元気づける』『正論を言う』よりも、まずはうなづいたり、同じ言葉を繰り返したりしてわかろうとしてもらえると、安心できますよね。」

このように、児童がほとんどの時間を過ごすコミュニティで、教科書以外の多様な学びを充実させていくことも、学校としての重要な役割であると考えています。
9月7日(水曜日) 台風のあと・・・
本校を囲む松林については、訪れる皆さんが「素晴らしいですね」と、その景観を褒めてくださいます。
しかし、強風の後は松葉だけでなく、枝も山ほど落ちて来て、それは足の踏み場がないほど積もります。
今回の台風11号が去った後も、通路は悲惨な状態になっていました。
それをある職員が掃いていると・・・。
6年生2名が、
「掃いた方がいいですか?」
と、がんじきを持って手伝いに来てくれました。
また、6年生3名が、別の通路を掃いてくれていました。


「皆、歩けなくて困るんじゃないかな・・・。」
「車が通れないんじゃないかな・・・。」
5年半学校にいる6年生には、このようなことがわかるのでしょう。登校してすぐ、自主的に動いてくれていました。
このような「勤労・奉仕」「愛校心」に長けた上級生の姿を見て、下級生も日々学びます。
もしコロナがもっとまん延して、休校やオンライン授業のみになっていたら・・・。
このような、人が集まり、人が繋がる「生きた学び」は生まれないでしょう。
これこそ、学校というコミュニティの素晴らしさです。
9月6日(火曜日) 全校朝会
9月の朝会です。
今日は、2学期の学級委員長、副委員長の選任式からです。
2年から6年を代表して、6年2組の大谷嶺來さん、山本楓さんに、オンラインスタジオに来てもらいました。

「委員長として、どんなことが目標ですか。」
「6年生は修学旅行があるので、楽しい2日間になるようにしたいです。」

「副委員長として、どんなことが目標ですか。」
「2学期は音楽会があるので、皆の心が一つになるようにして、素敵な音楽会になるようにしたいです。」
そして今日は、2つの心の勉強をしました。

1つ目は、「プチハッピーを見つけよう!」「プチハッピーを貯めよう!」です。

プチハッピーがないときは、こんなとき・・・。

「なんだか元気ないな・・・。大丈夫かな。」
「話しかけようかな・・・でも、やっぱりやめておこう。」

では、プチハッピーがあるときは、こんなとき・・・。

「なんだか元気ないな・・・。大丈夫かな。」
「話しかけようかな・・・、よし!話しかけてみよう!」

「え!ちょっと悩みがあったんだけど、聞いてくれる?
聞いてくれてうれしいな! プチハッピーが貯まったよ!」
「今週はプチハッピーを貯める方法を、全国の小中学生が勉強する週間(自殺予防週間)です。」
「プチハッピーを見つけて、どんどん貯めて、いつも楽しい気持ちでいたいですね。
「そのためにも、辛いことや嫌なことがあったら、誰かに話すといいですよ。」
もう一つは、いじめに関する勉強です。

「この9月を、加古川市は「いじめ防止啓発月間」としています。」
「今日は、このようなチラシをもらって帰ります。
家の人にも、このチラシのお話をしてくださいね。」
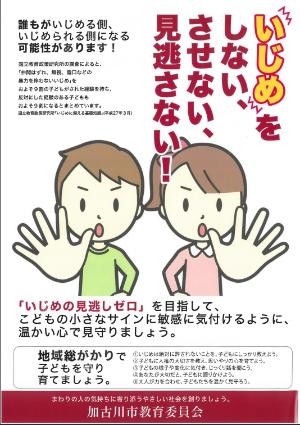
「家の人は自分の子どもがいじめたり、いじめられたりしていないか、いつも気にしておられるのですよ。」
「8月26日(金曜日)には、児童会委員さんが代表していじめに関する学習会に参加しました。
そして、それを9月27日(火曜日)に、全校集会で伝えてくれます。しっかり学びたいですね。」
2学期がスタートして、4日目です。
今学期も、いじめをせず、させず、見逃さず、そしてプチハッピーをいっぱい貯められるような学校でありますように。
皆がいつも楽しく学校生活を送れるようにしていきたいです。
9月6日(火曜日)~8日(木曜日) 夏休み作品展
今日6日(火曜日)から、夏休み作品展が開催されています。


感染対策として、ご来校いただく日時を下記のとおり割り振りさせていただきましたが、今のところ、保護者様にご協力いただき、円滑に進んでおります。
・1,2,3年保護者様 9月6日(火曜日)12:00~18:00
8日(木曜日) 9:00~12:00
・4,5,6年保護者様 9月7日(水曜日) 9:00~18:00

この夏休み、子どもたちは家族といるからこそ、長い休みだからこその学びを得られたことでしょう。
その学びの成果が存分に表れた作品展となっており、非常に嬉しく思います。
保護者の皆様のご支援にも感謝です。

浜の宮幼稚園の園児の皆さんも、見学に来てくれました。
「お姉ちゃんのがある!お母さんと作ってた!」
など、楽しそうに話しながら、見学していました。
9月は『いじめ防止啓発月間』です
加古川市は、9月を『いじめ防止啓発月間』に設定しています。
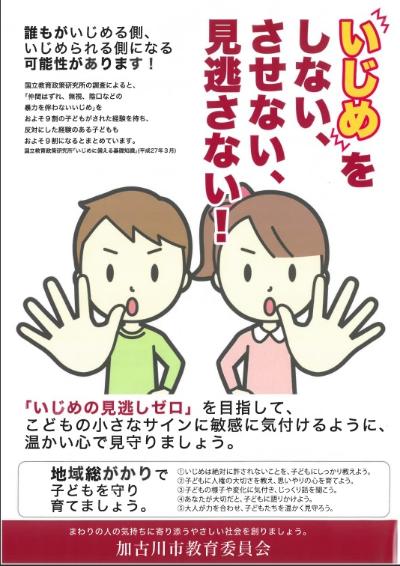
そしてそれに向けて、本市でも、そして校内でも、様々な取組を行っています。
8月26日(金曜日)には、本校の児童会委員が、中学校の生徒会役員に交じり、いじめに関する学習会「『心の絆プロジェクト』代表者ミーティング」に参加して来ました。


そのときに出た意見については、9月3日(土曜日)に市民会館で開催された「いじめ防止市民フォーラム」のパネルデスカッション等で共有されました。
なお、児童会委員がいじめ防止の在り方等、代表者ミーティングで学んで来たことを生かし、9月27日(火曜日)には校内で、「いじめ防止啓発集会」を開催する予定です。
現在、それに向けて児童会委員が、企画・準備を進めているところです。
9月1日(木曜日)2学期始業式
今日から2学期です。
登校時、「おはようございます」と丁寧にお辞儀も添えた元気な挨拶が校内のあちこちで見られました。
とても気持ちがよいです。
始業式は、やはりオンラインで。
新しい『ハマゴンスタジオ』のお披露目です。

「浜小50周年記念キャラクターとして誕生した「ハマゴン」が、1歳の誕生日を迎えました。
このように、1年間、夏、秋、冬、春という季節を皆さんと過ごしてきました。その記念のリニューアルです!」

「しかし、この1年間、なかなかコロナの猛威は収まりません。しかし、わが浜小は、常に皆でアイデアを出し合い、その危機を乗り越えて来ました。
先生方はChromebookを使った新しい授業や学習を常に研究、チャレンジしています。
また、5,6年生の各委員会は、自分たちの仕事や役割について、どんどん発表してくれています。
先生と皆さんと、協力しながら、コロナに負けない、すばらしい活動や学びを生み出して行きましょう。」
そのあとは、生活指導担当から。

「学校に今日、来られたことが何よりです。」
「ところで、1学期の終業式で先生とした2つの約束は覚えていますか。」
「まず、クロームブックを安全に使えましたか。もし、困ったことに巻き込まれていたら、大人の人に相談する勇気を出しましょう。」
「もうひとつ、自分の命や体を大切にできましたか。2学期も油断することなく、『手洗い』『マスクの徹底』『換気』『必要のない密は避ける』など、皆さんにできる、コロナから身を守る努力を続けましょう。」
児童会委員からは、1学期に行った「ウクライナ募金」の金額の報告がありました。

「38,628円集まり、振込を行いました。皆さん、ご協力ありがとうございました。」
始業式前にはこんな光景が見られました。

「2学期、気持ちよいスタートが切れるように」と、玄関前を自主的に掃きに来てくれた6年生の姿です。
その6年生の教室には、担任から黒板に熱いメッセージが・・・。

2学期も、とても気持ちよく、温かい気持ちで教育活動が進められそうです。
8月30日(火曜日) 「ENJOYチャレンジ」開催
2学期始業式まで、あと2日・・・。
子どもたちは、少しずつ授業モード、そして本来の学習のペースを思い出している頃でしょうか。
そんな中、本日は市教育委員会主催で、「ENJOYチャレンジ」が開催されました。
「英語」を通した外国人とのコミュニケーションの場を設け、加古川市の未来を担う子どもたちの英語力向上の一助とすることを目的として、ALTとの1対1の英会話体験を実施してくださいました。
あらかじめ希望していた6年生12名が学校に来て、日頃加古川市で従事しているALTと、マンツーマンでの会話等を楽しみました。
そして、今回参加した児童には、「Language Passport(認定証)」が発行されました。
このように、将来、国際社会で活躍する児童の育成に向けて、本市をあげて取り組んでいるところです。


「保護者の皆さん、ありがとうございました!」
8月20日(土曜日) 愛校作業
8月20日(土曜日)に、児童と保護者御有志との合同で、校舎周りの愛校作業を行いました。
実施に向けては、コロナの感染まん延、熱中症の心配等、多くの不安ごとが懸念されました。
しかし、愛校心や公共の精神など、この行事が児童にもたらす学びはたくさんあります。
そして何よりも、自分たちの学校を、自分たちのために、大人の皆さんが集まって美しく整えてくれたということ。きっと児童には感謝の心が芽生えたはずです。
おかげで運動場も中庭も学習園も、大変美しくなりました。本当にありがとうございました。
自分の周りを美しく整えると、自分の心が整います。自分の心が整うと、周りの人にも優しくなれます。
2学期も、様々な活動を充実させられそうです。
コロナによる中止が続き、3年ぶりの愛校作業の実施でした。例年の状態がわからない中、PTA本部、そして学年部の皆様、1学期から時間をかけて準備してくださり、重ねてお礼申しあげます。

運動場の端から端まで・・・。

駐車場も・・・。

中庭も・・・。

学習園も・・・。

浜の宮グラウンドとのすき間も・・・。

大人の方のみで、側溝にたまる泥を全て取り除いてくださいました。

「Google Meet Day」開催!!
1人1台のChromebook整備により、夏休み中でも、子どもたちの元気な顔を見られる機会を持つことができるようになりました。
夏休み中、持ち帰っているChromebook内の「Google Meet」を使用して、各家庭にいる児童と担任とのオンライン通信を実施しています(2~6年)。
新型コロナウイルスの感染状況は少し緩やかになってきたものの、2学期には台風等の発生による臨時休校も予想され、その際の連絡や学習保障において、「Google Meet」は有効にはたらきます。その点も踏まえ、活用に慣れておくことは非常に大切であると考え、夏休み中もオンラインの練習を行っています。
さらに、担任としては久しぶりにクラスの児童の元気な顔を見ることができ、一石二鳥です。
でもついつい、「登校日は20日だよ。宿題だいじょうぶ?」とか聞いてしまいそうですね!!

これは3年2組の「Google Meet」の様子です。
「元気だった?元気な人は手を挙げてね!」

参加してきた子どもたちの元気な笑顔を、画面上で見られます。

担任から「読み聞かせ」のプレゼント。


「先生にジャンケンで勝ったら、退出(「Google Meet」オフ)していいよ~!」
マイクオンの子どもからは、「え~!?」の声が!!
暑中お見舞い申しあげます ~令和4年の夏~
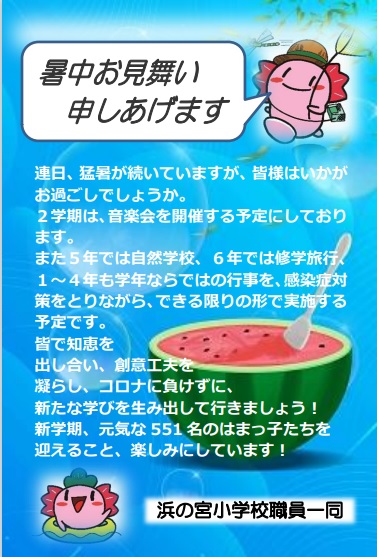
7月22日(金曜日)1学期終業式
本当は、1学期の締めである終業式は、外で顔を合わせて行いたいところでした。しかし残念ながら、暑さ指数が早朝よりどんどん上昇し、子どもたちの健康・安全を優先するため、オンラインで開催しました。
まずは、学校長から。
浜小の4月から7月を、「こうちょう先生ニュース」で振り返りました。

4月は「入学式のお話」。
「ハマゴンの『ハ』は、『はっきり目を見て、おはようございます』」
「ハマゴンの『マ』は、『まほうのことば、ありがとう』」
「ハマゴンの『ゴ』は、『ごめんなさいで仲直り』」

5月は、豊岡市立竹野南小学校の、登校班についての新聞記事を紹介しました。
「その後、お辞儀を添えながら挨拶のできる人が増えました。」

6月は、アサーションを取り入れた話し方について。
「『廊下を走ったらあかんで!』よりも、『廊下を歩きましょう』の方が、伝えたいことを聞いてもらえそうですね。」

7月は、絵本「へいわとせんそう」の紹介。
「朝は世界中、どこでも同じようにやってきます。
いのちは世界中、どこでも平等に生まれます。」
この後、皆でウクライナ募金を行いました。
たった4ヶ月なのに、学校全体でも、こんなにたくさんのことを学びました。
学校はやはり、素晴らしい場所です。みんなといるからこそ、学べることがたくさんあります。
学校はみんなの「学び合い」があってこその、「学校」なのですね。

次に、生活指導から。
「夏休みにしてほしいこと。
しっかり挨拶してほしいなあ・・・。
家のお手伝いをしてほしいなあ・・・。
もちろん勉強のしてほしいなあ・・・。
運動もしてほしいなあ・・・。」

「でも、一番してほしいことは、命を大切にして過ごすことですよ。
自分の命を守るために、防げることはたくさんありますよ。」

「またこの夏休み、加古川市の小学校が一斉にクロームブックを持ち帰ります。
『はまっ子憲章 ~インターネット編~』を引き続き守りながら、宿題を始め、どんどん学習に役立てましょう。
『グーグル・ミート・デイ』にもぜひ参加しましょう。」

最後にハマゴンから、心のケアについて大切なお話が。

「夏休み、とても楽しみですね。でも長いお休み・・・、悩みや困りごとが出て来たら、誰かに話すことがとても大切です。」
「この夏休みより、皆さんのクロームブックから『ひょうごっ子悩み相談』にすぐに繋がるようになりましたよ。
何かあったら一人で抱え込まず、利用しましょうね。」


「この後配られる、『ひょうごっ子悩み相談』のカードを見て、電話やメールをしてもいいですよ。」

どうぞ2学期、心も体も整い、無事にスタートできますように。
コロナに、熱中症に負けませんように。
皆が健康で、9月1日に登校できますように。
それが教職員一同の願いです。
2年生が1年生をご招待 「生きものランド」
2年生が生活の学習「生きものなかよし大作せん」のまとめとして、「生きものランド」を開催し、1年生を招待しました。


実際に生きものを見せたり・・・。


「生きもの新聞」「生きものクイズ」を作成して説明したり・・・。
この学習を通して、生きものの育つ場所や成長の様子に興味をもつこと、そしてそれらは生命をもっていることや成長していることに気づき、大切にしようとする学びの獲得を目指しています。
またそれだけでなく、2年生は「下級生の役に立っている」という自己有用感の向上、1年生は「こんな2年生になりたいな」というモデルケースの獲得など、各々の成長過程にアプローチしています。
なかよし学級4年生 国語「新聞を作ろう」
なかよし学級4年生が、国語「新聞を作ろう」の単元に沿い、新聞作りにチャレンジしました。

内容は、
・なかよし学級で飼育している金魚「金ちゃん」の紹介

・なかよし学級メンバーの『好きな遊び調べ』と、そこからわかったことについて

『好きな遊び調べ』では、結果を棒グラフで表したり、そこからわかることを記述したりと、算数の学びも高まっています。
昨年度からのChromebookの導入に伴い、なかよし学級でも児童の学びの向上に向け、個々に合わせた活用の在り方を吟味し、積極的に取り入れています。
もちろん、『書く』という作業についても疎かにせず、楽しんで取り組めるよう、工夫しています。
なかよし学級の皆さん、ありがとう! ~1年生より~
なかよし学級が1年生を招待し、オリジナル劇『たなばた物語』を披露したことは、先日このホームページで紹介しました。


そのお礼として、1年生が手紙を届けています。


習いたてのひらがなをひとつずつ並べ、一生懸命書き綴っています。
Chromebookの活用を始め、ICT化が加速度的に進んでも、『書く』学習は避けられません。
しかし本校では、1年生についてはChromebookの使用を2学期から、と定めています。まずは紙と向き合い、『書くこと』を大切にしてほしいからです。
『書く』という作業・・・。それは普遍的なものです。その労を厭わない子どもたちを育てていきます。
理科栽培委員会 ~その2~
理科栽培委員会が校内に咲く花について、給食時、各クラスに紹介しに行ったことは、このホームページですでにお伝えしております。
夏の花壇やプランターの定番、ペチュニアの紹介をしました。
現在、校内はペチュニア、ベゴニアの花でいっぱいです。
理科栽培委員が毎日、交代で水やりを行ってくれている成果です。


ここ最近は大変暑いときが多いです。また、水泳も始まって忙しいときがあります。それでも、時間を見つけて自分の役割を全うしてくれていることで、校内の花は見事に咲き誇っています。




7月12日(火曜日) 学び集会 ~美化委員会より~
学び集会は、児童が主体的に企画・運営する朝会です。
「おはようございます。」
「本格的な夏がやって来て、毎日大変暑いですね。心は健康で、学級の友だちとは仲良く過ごせていますか?」
司会者が進めていきます。
「今日は、美化委員会からのお知らせです」

まずは、6月の「美化コンクール」の結果発表がありました。

60点満点~58点は『ピカピカで賞』
57点~は『がんばったで賞』
次に、美化委員が、素敵な『だまピカ』を続けている、2階のトイレ清掃の様子を動画で紹介してくれました。



「どうでしたか。」
「場所によって道具を使い分けるなど工夫し、隅々まできれいにしていて、すごいと思いました。」
感想を代表で、児童会委員が答えました。

「見えないところまで、また隅々まで掃除されていましたね。
また、高学年になると少ない人数でたくさんの場所を掃除しますが、役割をきちんと分担できていましたね。
このように、普段見えないところも、物を移動させたり、端までよく見て気をつけたりすると、ピカピカに掃除をすることができますね。」
美化委員が、このように締めくくりました。

最後に、学校長から。
素敵な取組は他にも・・・。

「先日、理科栽培委員が、1年生から4年生の教室に、校内の花『ペチュニア』の紹介に行きましたね。
現在、校内はこのように、ペチュニア、ベゴニアの花でいっぱいです。
でも、放っていてこのように美しく咲き続けることはできません。理科栽培委員が毎日、交代で水やりを行ってくれているからです。」
遊ぶたいな・・・、休みたいな・・・、勉強の残りが気になるな・・・。高学年になると、学習面も生活面も大忙しです。
でも、まずは委員会の仕事を優先し、自分の役割を果たす。また、勤労の尊さについて身をもって知る。
自身の学びだけでなく、低・中学年にも素晴らしいモデルケースとなっている5,6年です。
7月6日(水曜日) 「校内の花を紹介しました 『理科栽培委員会』」 ~その1~
理科栽培委員会が校内に咲く花について、給食時、各クラスに紹介しに回っています。
これは、4年生に紹介しているときの様子です。

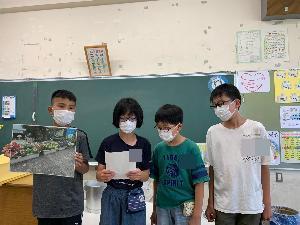
「この花の名前は何でしょう」「正解はペチュニアです」
夏の花壇やプランターの定番、ペチュニアの紹介です。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、未だ給食中の私語は一切なくなり、ただ黙々と食する状態が続いています。
その中、児童企画のこのような活動が次々に実行され、楽しく食事をする時間を持つことができています。
なかよし学級「たなばた劇」
7月5日(火曜日)、6日(水曜日)の2日間、なかよし学級が1年生に向けて、「たなばた劇」を披露しました。
昨年も行いましたが、今回は6年生がプロデュース側に回り、教師の手をできるだけ借りずに劇を仕上げようと努力していました。

ナレーションも・・・。

音響も・・・。

おりひめとひこぼしの最後の場面。手作り衣装が映えます。

教師と一緒に作った機織り機。

1年生も一切私語することなく、行儀よく真剣に鑑賞。
終了してから、なかよし学級担任が、
「頑張ってやり切りましたね。やり切ることが大切。」
と称賛していました。
また、1年生からはごく自然に、「ありがとう」「おもしろかった」という声があがっていました。
たなばたストリート ~その2~
給食委員も、給食室前にたなばたの短冊を掲示しています。


「世界中から食品ロスがなくなりますように」
「世界中のみんなが自由にごはんを食べられますように」
「世界中の人が安全に、安心して食べ物を満足に食べられますように」
子どもたちは、先日から朝会で戦争の話を聞いたり、ウクライナに向けての募金に協力したりしています。
これらのことが心の片隅にあるのでしょうか。世界に目を向けて、「食」について考え、願っています。
7月5日(火曜日) 全校朝会
7月の朝会です。
今日は台風による注意報が4つも・・・。それだけでなく、多くの視覚情報を適切に児童に届けるため、今日もオンラインで実施しました。
まずは、学校長から。
谷川俊太郎さんの文による絵本「へいわとせんそう」を紹介しました。

谷川俊太郎さんは、誰もが知っているお話「スイミー」を教科書のために日本語に書き直した方です。

へいわのワタシ・・・せんそうのワタシ・・・

へいわのどうぐ・・・せんそうのどうぐ・・・

みかたのあかちゃん・・・てきのあかちゃん・・・
「どの国にも平等に、新しい命は生まれることを言いたいのかな。」
実は今、5年生がやなせたかしさんの「伝記」、一生について、国語で勉強しているところです。
やなせたかしさんは、アンパンマンの作者、なんと54歳から94歳の亡くなるまで書き続けたそうです。

その学びについて聞きたく、代表して5年児童に来てもらいました。

「やなせたかしさんの大きな出来事、経験はどんなことでしたか。」
「戦争を経験したこと、そして弟を戦争で亡くしたことです。」
「やなせたかしさんは、そこからどんなことを感じていましたか。」
「『本当の正義は、人を生かすことであり、命を応援することだ』と感じたそうです。」
6月の学び集会で、「ウクライナに向けての募金」の提案が児童会委員からありました。
今日の絵本や、5年生の学びの話から、皆が自分の、そして周りの人の命を大切にする心を高め、さらにウクライナの子どもたちにむけて募金活動に協力しようという意欲を持ってくれたら嬉しいです。
たなばたストリート ~その1~
1階教室棟、1年生となかよし学級の教室前には、先週からたなばたの笹が飾られています。

日本の「たなばた」は、元来、中国の行事であった七夕が奈良時代に伝わり、その後、江戸時代に入ってから七夕祭りが全国的に行われるようになったそうです。
江戸時代から考えても、約400年以上続いている、日本の大切な文化です。
「特別の教科 道徳」でも学ぶべき内容項目として、「伝統と文化の尊重」が挙げられています。

「みんながしあわせになりますように」

「ひらがながきれいにかけますように」
自分の願いを文字にして表出できるようになったこと・・・。入学して3ヶ月、これも学びの成果です。
6月30日(火曜日)
体育委員会主催「1年生を楽しませよう! ~風船バレーボール~」
体育委員会が1年生に向けて、「風船バレーボール大会」を開いてくれています。
バレーボールのルールですが、ボールの代わりに風船2個を使うという、オリジナルのゲームです。
ここ最近、WBGT指数(暑さ指数)が31を超え、外遊びのできない日が続いています。
今日は体育館の窓を全開にして、ロングタイム(30分休憩)に楽しい企画をしてもらい、1年生も大満足でした。
このような児童主体の活動がどんどん提案・実行され、学校全体が活気づいています。猛暑が続き、気分もやや滅入りそうになりますが、子どもたちの元気は無限大です!

1年生の動きを、体育委員が優しくフォロー!

1年生がルール説明など行儀よく聞いてくれるので、進行もはかどります!
水泳学習が始まりました!
新型コロナウイルスの感染拡大により、一昨年はできなかった水泳学習ですが、昨年は少ない時間ながら行うことができました。
そして今年度も、市教委からの丁寧な取り決め事項をもとに実施できることとなり、本日7月1日、待望のプール開きを迎えました!
本校は幸い、「浜の宮市民プール」を市から提供いただき、水泳学習を実施しておりますので、水質管理等の感染対策が強化されております。
さらには、フィジカルディスタンスを確保するため、各1時間、大・小プール各1クラスのみで学習を行うこととしています。
(各時間、大・小プール2名ずつで指導を行います)
「授業中は不必要な会話や発声を行わない」と指導し、プール内で密集しないよう、プールに一斉に大人数が入らないように留意します。
以上のことを守った上で、技能面の向上のみに留まることなく、「自分の身は自分で守る」という安全教育の観点から、まずは「水慣れ」を重視し、指導していきます。
さらには、「どうやったら安全に、速く泳げるかな?」と課題を提示し、「主体的に取り組む態度」の育成も目指します。

1年生。待っている間のフィジカル・ディスタンスを上手に保てています。
「バディ(健康状態を確認し合うペア)」についてもすぐに理解し、安全に取り組めています。

6年生。コースロープを活用して、フィジカル・ディスタンスを保っています。







更新日:2022年09月29日