令和6年度「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて【野口小学校】
2月7日(金曜日)
「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて ~その6~
本市では「協同的探究学習」とICTの融合を目指した『加古川型スマート探究学習』を推し進めています。
その実践の6回目、算数での研究です。
2月7日(金曜日)には、1年3組担任が「大きいかず」の単元での授業を校内教員に公開しました。
20までの数は学習してきましたが、新たに100までの数について知り、その数に親しみながら学ぶことを目指す単元です。
課題は「28円のお金の出し方を考えよう」。
お金の出し方を考えることを通して、100までの数の構成を、多面的に捉えさせることが目標です。

28円というお金の出し方を自分で考え、学習支援コンテンツの「発表ノート」上で表していきます。

発表ノートの利点は、シートを変えて、自分の考えを2つ以上入力できることです。

「お話できるようになったら、2枚目作っていいよ。」
ただ知識として入力するのではなく、その都度、自身の考えに根拠をもたせ、後の協同探究につながるようにしておきます。

入力し終わったら提出。
「発表ノート」の活用によって、皆の意見を速やかに、かつ広く共有することができます。

様々なお金の組み合わせを、大型モニターで映しながら発表します。

その際、数え方のコツは「5とび」「10とび」。
12月に学習した数え方を、知識として有効に活用します。

皆の発表で、板書がどんどん埋まっていきます。
モニターだけでなく、多くの意見を視覚的に一度に確認できる板書をとても大切にしています。

ここで、お金の実物登場。
「少ない枚数の組み合わせの方が払いやすいな。」
「10円玉を持っていなくても、払えるな。」
「でも絶対、金額は28円だね。」
ここで「数の構成を多面的に捉える」という今回の学びの本質に迫らせていきます。


最後に、展開問題に取り組みます。
「では、今度は67円のお金の出し方を考えてみましょう。」
「あれ?50円玉があるよ!」

来年度も、今年度の研究の成果を礎に、ChromebookをはじめとするICTを効果的に使いながら、「個別最適な学び」に留まらず、「協働的な学び」の活性化を目指した授業の在り方を教職員で研究してまいります。
「Google Meet 」でつながります!
インフルエンザが猛威を奮っています。
学校では授業中も「ゲンコツ1個分」を目安に窓を開け、常時換気には気をつけています。
それでも、子どもたちの安全・安心の確保のため、学級閉鎖を決行するべきときもあります。
このような臨時休校中でも、1人1台のChromebook整備により、子どもたちの様子を知る機会を持てるようになりました!
持ち帰っているChromebook内の「Google Meet」を使用して、各家庭にいる児童と担任とのオンライン通信にて、毎日の健康確認を行っています。
担任としてはクラスの子どもたちの家庭での元気な様子、また元気になった様子を見ることができ、安心する時間でもあります。

「〇〇さーん!」
ミュートを解除して「ハイ、元気です!」

参加児童をモニター上でも確認中です。
表情も見られて、元気の度合までわかります。
12月18日(水曜日)
Chromebookの活用をすすめています ~その2~
Chromebookが導入されて、約4年が経ちます。
昨年度を本校は「Chromebook元年」と捉え、授業者も子どもたちも、積極的にその活用の在り方を研究してきましたが、今年度はその活用にずいぶん慣れて来た感があります。
今学期は、新しい学習支援コンテンツ「オクリンクプラス」がChromebook内に導入され、その活用も少しずつ進んでいます。
これは6年国語「冬のおとずれ」という単元で、俳句を綴る授業です。通年で、春夏秋冬を俳句で表現する学習に取り組んでいます。
まずは、冬の題材集めを。
Chromebookで写真を撮り、保存します。

冬をテーマに俳句をつくり、その写真とともに『オクリンクプラス』のシートに貼って提出BOXへ。


「協調したいところや付け足したいことは、手書きで入れてね。」
『オクリンクプラス』の利点は、手書きで書いたり、色をつけたり塗ったりが容易なことです。
これなら、低学年も活用できそうです。


それだけでなく・・・。
「提出BOX」ではなく、「みんなのボード」に提出することで、教師やクラスメイトが加筆することができます。

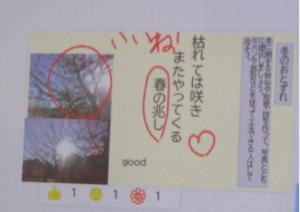
これなら、教師がまちがいを修正したり、友だちの考えに「いいね!」と書き加えて称賛したりすることができます。
速やかに、そしてより多くの意見を共有することのできる学習支援コンテンツの可能性が、また広がりました。
12月3日(火曜日)
Chromebookの活用をすすめています ~その1~
Chromebookが導入されて、約4年が経ちます
昨年度を本校は「Chromebook元年」と捉え、授業者も子どもたちも、積極的にその活用の在り方を研究してきましたが、今年度はその活用にずいぶん慣れて来た感があります。
これは2年算数「三角形と四角形」の授業です。
「三角形」「四角形」「どちらでもないもの」の図形を、学習支援コンテンツ「発表ノート」を用いて教師が配信しました。

子どもたちは、「直線」と「角」に着目しながら各自分けていきます。

三角形は3つの角と、直線が3本・・・あれ!?
コロナ前なら、紙媒体に図形が印刷された用紙を配り、それをはさみで切り分けて・・・、という作業を行っていましたが、モニター上で簡単に振り分けられ、「なぜそう分けるか」という理由を思考する時間を存分にとることができます。

角を「頂点」、直線を「辺」という新しい用語を覚える時間も十分に確保できました。
11月22日(金曜日)
「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて ~その5~
本市では「協働的探究学習」とICTの融合を目指した『加古川型スマート探究学習』を推し進めています。
それに向けて、本校の実践の5回目です。
11月22日(金曜日)には、5年2組担任が国語「やなせたかし ―アンパンマンの勇気―」の授業を校内教員、および播磨東地区の2年目教員に公開しました。
子どもたちに愛され続ける「アンパンマン」。
その生みの親である、やなせたかし氏の生き様を形作った、その生い立ちや戦争体験、そしてそこから得た自身のポリシーである「本当の正義」を東日本大震災のときまで貫き続けた一生涯を綴った伝記が教材です。
課題は「やなさたかしさんが『どんな人なのか』を交流しよう。」
まずは、それぞれが「一人学び」で見つけた「〇〇〇な人」をChromebook内のアプリ『ふきだしくん』に入力していきます。


子どもたちは画面を見ながら、
「『あきらめない』は右下ね。」
『努力家』は真ん中に集まろう。」
と声をかけあい、似た意見のふきだしをグルーピングしていきます。

グループごとに色を変え、より見やすくして意見の共有。
Chromebookの利点を生かし、各自で友だちの意見を速やかに確認し、協同探究の前により多くの考え方に触れておきます。

そして、『協同探究』場面で各々の捉え方について意見交流を。

皆の意見交流で、板書がどんどん埋まっていきました。

「やなせたかしさんは、はじめ評判の悪かったアンパンマンをあきらめてもよかったのではないか」
とあえて揺さぶる発問をし(設定型発問)、やなせ氏が戦争体験を基に考え、貫き通した「正義や命の大切さ」という本質に迫らせていきます。

最後に『展開問題』として、「東日本大震災後、92歳のやなせさんがどんな願いをもって活動したのか」について・・・。
本読みを行い、文章に今一度立ち返ってから・・・。

各々の考えを書き留めました。

「私は、やなせさんは震災で傷ついた人たちに勇気を与えたい、元気になってもらいたいという思いをもって活動していたと思います。
アンパンマン=やなせさんで、アンパンマンは自分の身を削ってでも誰かを助けようとしますが、やなせさんもその通りです。」
「わたしは、やなせたかしさんは人々に笑顔になってほしかったんだと思います。
92歳のときに東日本大震災が起きて、体が手術の跡だらけだったけど、『傷ついた人々のために何かしたかったのだ』と書いてあるから、きっと笑顔を取り戻してほしかったんだと思います。」
このように、「書く力」も育てるため、デバイスへの入力のみで終わらない「書く」学習活動も取り入れていきます。
今後も、6年生に向けて、さらには中学進学まで見据えて、「個別最適な学び」「協働的な学び」の推進をより意識しながら、「協同的探究学習」を取り入れる授業の在り方を教職員で研究してまいります。
11月13日(水曜日)
「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて ~その4~
本市では「協働的探究学習」とICTの融合を目指した『加古川型スマート探究学習』を推し進めています。
その実践の4回目です。
11月13日(水曜日)には、6年3組担任が国語「『鳥獣戯画』を読む」の授業を校内教員に公開しました。
スタジオジブリで数多くのアニメーションの名作を監督として手がけた宮崎駿氏が、「国宝である『鳥獣戯画』は、漫画の祖だけではなく、アニメの祖である」という持論を、斬新な切り口をもって明確に評価していく論説文です。
「論の展開」「表現の工夫」「絵の示し方」と、筆者の書きぶりがもたらす効果についても非常に掴みやすく、後に続く「発見、日本文化のみりょく」のパンフレットづくりにも取り入れやすい工夫が随所に見られる教材文です。
まずは、それぞれが「一人学び」で見つけた書きぶりの工夫について、Chromebook内の学習支援コンテンツ『ムーブノート』に入力し、提出します。

今回は、速やかに共有しやすいよう、「論の展開」「表現の工夫」「絵の示し方」と名付けたシートを自分で選択し、そこに提出しました。


Chromebookの利点を生かし、各自で友だちの意見を速やかに確認し、協同探究の前により多くの考え方に触れておきます。

そして、『協同探究』場面で各々の捉え方について意見交流を。

その際、友だちの意見で気になったことは、すぐにChromebook
でも確認を。
6年生ともなると、意見を聞きながら視覚的にも確認し、並行して学びの効果をあげることができています。

皆の意見交流で、板書がどんどん埋まっていきました。
最後に『展開問題』として、自分がパンフレットをつくる際に取り入れたい工夫を書きました。

「ぼくは日本刀のパンフレットをつくるので、その切れ味のすばらしさが伝わるように、体言止めを取り入れたいです。」
「絵を2回に分けて見せているところを取り入れたいです。その特徴がより伝わると思うからです。」

このように、「書く力」も育てるため、デバイスへの入力のみで終わらない「書く」学習活動も取り入れていきます。
今後も、6年生については、中学校への円滑な接続が行えるよう、「個別最適な学び」「協働的な学び」の推進をより意識しながら、「協同的探究学習」を取り入れる授業の在り方を教職員で研究してまいります。
10月17日(木曜日)
「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて ~その3~
本市では「協働的探究学習」とICTの融合を目指した『加古川型スマート探究学習』を推し進めています。
その実践として、10月17日(木曜日)には、4年4組担任が国語「未来につなぐ工芸品」の授業を校内教員に公開しました。
職人たちが生み出す工芸品のよさを伝える仕事をしている筆者が、「工芸品を残すことは、日本の文化や芸術、そして環境を未来につないでいくことになる」と主張する説明文です。
本時は、その説明文の要約に挑戦するため、まずは皆でキーワードを探す学習を、Clomebookを活用して行いました。
「『中』の部分で要約に必要なキーワードを探しましょう。」
ここで、『個別探究』としてChromebook内の学習支援コンテンツ『ムーブノート』に配信された課題に取り組みます。


課題はムーブノートの「ひろば」に提出され、皆の意見が視覚的にすぐに確認することができます。

そして、『協同探究』場面で課題の解答について意見交流。


板書がどんどん埋まっていきます。

最後に『展開問題』として、最終的に自分が要約に使いたいキーワードを選び、今日の学びも書き留めました。


このように、「書く力」も育てるため、デバイスへの入力のみで終わらない「書く」学習活動も取り入れていきます。
今後も、ICTというツールを活用しながら、「協同的探究学習」を存分に取り入れる授業の在り方を教職員で研究し、子どもたちの「生きる力」育成に取り組んでまいります。
10月9日(水曜日)
「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて ~その2~
本市では「協働的探究学習」とICTの融合を目指した『加古川型スマート探究学習』を推し進めています。
その実践に向けて、10月9日(水曜日)には、3年1組担任が国語「ちいちゃんのかげおくり」の授業を校内教員に公開しました。
お父さん、お母さん、お兄ちゃんと「かげおくり」をして楽しく遊んでいたちいちゃんですが、戦争によってだんだんそれができなくなっていきます。
今日は、空襲によって家族と別れ、ひとりぼっちになったちいちゃんが、「お母ちゃん、お兄ちゃん」と呼びながら空に吸い込まれて・・・。
お父さんとお母さんとお兄ちゃんが、笑いながら歩いて来るのが見えた、ちいちゃんの命が空に消えていく四場面の学習です。
「四場面で、ちいちゃんはしあわせだったのでしょうか。」
教師が、本時の課題を提示し、学習の見通しをもたせます。

ここで、『個別探究』としてChromebook内の学習支援コンテンツ『ポジショニング』を活用。
「ちいちゃんは家族に会えてしあわせだったのか」
「ひとりぼっちのまま死んでしまって幸せではないのか」
自身の考えを、『ポジショニング』に入力します。
『ポジショニング』は考えの2択ではなく、その考えの度合いまで示すことができます。

「それはどこでわかったのか」「どこに書いてあるのか」「なぜそう思ったのか」という根拠を明確にもたせるため、ワークシートに記述して、整理させます。
端末への入力だけでなく、このような書く活動も大切にしています。

皆の『ポジショニング』の位置をモニターで共有。
『ポジショニング』では、位置における人数とその入力者もすぐにわかるので、教師の指名や意見の共有が、大変スムーズに進みます。

そして、『協同探究』場面で意見交流し、板書がどんどん埋まっていきます。

ここで、再度ポジショニングを活用し、他者と交流した協同探究で深めた学びを基に、「ちいちゃんは幸せだったのか」について再考します。

「はじめは『少し幸せじゃない』にしていたけど、皆『天国に会えたから』という意見を聞いて、『幸せである』の方に寄せました。」

「『家族に会えて幸せ』にしていたけど、ひとりぼっちで死んでいることがわかって、『幸せじゃない』に変えました。」

場面後の『展開問題』場面では、毎場面ごとに書き留めている『ちいちゃんへの手紙』に取り組み、本時の学びと捉えを振り返らせます。
このように、「書く力」も育てるため、デバイスへの入力のみで終わらない学習活動も取り入れていきます。
今後も、ICTというツールを活用しながら、「協同的探究学習」を存分に取り入れる授業の在り方を教職員で研究し、子どもたちの「生きる力」育成に取り組んでまいります。
6月27日(木曜日)
「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて ~その2~
本市では「協働的探究学習」とICTの融合を目指した『加古川型スマート探究学習』を推し進めています。
その実践に向けて、6月27日(木曜日)には、2年3組が国語「スイミー」の授業を校内教員に公開しました。
「まぐろが小さな魚たちを一ぴきのこらずのみこむ」という事件が発生し、独りぼっちになってしまったスイミー。
しかし、海の素晴らしさを体験し、元気を取り戻したところで、自分とそっくりの小さな魚のきょうだいたちを見つけて・・・。
「なぜ、スイミーは『いつまでもそこにじっとしているわけにはいかないよ』と言ったのでしょう。」
教師が本時の学習に見通しをもたせます。

ここで、『個別探究』としてChromebook内の学習支援コンテンツ『ポジショニング』を活用。
「岩かげにいた方がいいのか」「外に出た方がいいのか」というスイミーの心情について、『ポジショニング』に入力します。
『ポジショニング』は考えの2択ではなく、その考えの度合いまで示すことができます。



「それはどこでわかったのか」「どこに書いてあるのか」「なぜそう思ったのか」という根拠を明確にもたせるため、スイミーの心情を吹き出しに記入させます。
端末の入力だけでなく、このような書く活動も、引き続き大切にしています。

皆の『ポジショニング』の位置をモニターで共有。
『ポジショニング』では、位置における人数とその入力者もすぐにわかるので、教師の指名や意見の共有が、大変スムーズに進みます。


そして、『協同探究』場面での意見で、板書がどんどん埋まっていきます。


今後も、ICTというツールを活用しながら、「協同的探究学習」を存分に取り入れる授業の在り方を教職員で研究し、子どもたちの「生きる力」育成に取り組んでまいります。
5月14日(火曜日)
「加古川型スマート探究学習」の実現に向けて ~その1~
今年度も、本市では「協働的探究学習」とICTの融合を目指した『加古川型スマート探究学習』を推し進めています。
そのために、ICTというツールの強みを生かせるスキルを、低学年のうちから向上させることが必要です。
2年生、3年生はChromebookを活用し、生活・理科の観察を行いました。
3年生は、モンシロチョウになる幼虫の成長を、撮影して記録しました。


2年生は、自分で植えた夏野菜の苗を、撮影して記録しました。皆、収穫への期待が膨らんでいます!


この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-0012
住所:兵庫県加古川市野口町野口493
電話番号:079-424-1890







更新日:2025年03月24日